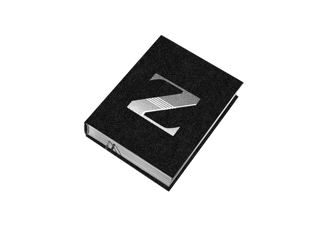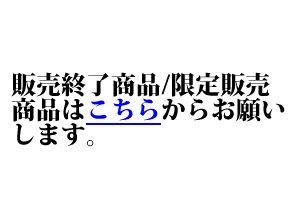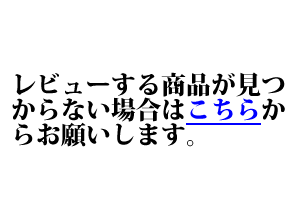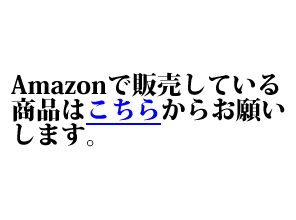レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
ドジョウ(8cm)を釣りに行ったら、ウナギが釣れました。
【Z1000-Siena(2回目)】
10月10日の試聴会に続き、10月17日のZ1000-Siena試聴会2回目に参加してきました。13時からの一番早い回で30分ぐらい早く着きました。始まるまで個人試聴OKとのことで前回の宿題を復習させて頂きました。さらに13時台は参加者は2人でしたので時間内の試聴も通常の倍時間を頂けましたので十分確認できたと思います。音の感想を文字でお伝えするのは難しいですが、前回のレビューと併せてお読み頂ければ更にイメージし易いと思います。前回の内容と異なる部分は今回の方を訂正版とお考え頂ければ幸いです。
宿題に入る前に長くなるのでZ1000-Sienaの私の結論を書きたいと思います。Z601-Modena系で私の持っているのは、2018年マークオーディオOMMF5用バーチキットにOMMF519を入れたZ601-OMMF519(Z701-OMMF519ではありません)です。板厚は12mmですがバーチ材ですのでカンカンと硬い音で強度不足は感じません。このユニットは現在でもCHN519としてレギュラー品で売れているそうです。FS : 106.25HzとSiena(W3-1878)の 75Hzと比べあまり低域を狙ったユニットではありません。それでもダブルマグネットの採用などで低域を増強、前モデルのOMMF5より10Hzぐらい下がったはずです。元々マークオーディオのユニットはシングルバスレフ推奨でBHBS/ダブルバスレフと必ずしも相性が良いとは言えないためか、あるいはOMMF519専用でないためか、このセットは中低域に盛り上がりを感じボヤケ気味の音でバランス的にはチョイ難あり?です。Z1000-Sienaは全く別物で音工房Z大山マジックでグッドバランス、低域は40Hz以下は厳しいですがそれさええ気にならなければスーパーツイーター無しのリアルフルレンジでクリアーで自然、且つ明るく艶やかな音が聴ける最高のブックシェルフスピーカーと思います。但し8cm(MAX25W)大音量には向きませんので、マークオーディオが好きで明るい音が欲しい方にうってつけです。(マークオーディオのウェットな音も捨てがたいですが)
宿題は以下の3点です。
1)スーパーツイーターは必要か?
2)中低域の違和感(バックロードホーン/BHBSのネガな部分)はあるのか?
3)他に欠点はあるのか?
この課題は大山さんが一番気にされていた点でした。前回の私の感想は「無くていいんじゃないと思いました。」でした。正直なところ私には有無が分からなかった(感じられなかった)ということです。私は現在65歳で、けして耳のよい方ではありません。完全音感どころか和音の聞き分けも怪しい老駄耳です。15kHz以上は聞こえないと思います。しかし、過去5年間に参加したした試聴会でスーパーツイーターの有無は分かりました。今回のスーパーツイーターはZ501(V2)ですが、過去はほぼZ502だった気がします。この差が影響している可能性は否定できませんが、再試聴しても今まで程の違いは感じられませんでした。
試聴位置をスピーカーの前ニアフィールドに移動すると違いは分かり易くなりました。また試聴機のコンデンサーは0.56μFでしたが、隣に1.5μFを付けた同じZ501(ウォールナットの限定品)を置いて頂き比べると一聴1.5μFの方はスーパーツイーターの有無は分かりましたが、ここまでやるとやり過ぎで煩いと感じました。音質もZ1000-Sienaのバランスを崩してしまう感じでした。最後の方に大山さんがこれなら分かるでしょうとマライヤキャリーの曲をかけてくれ、さすがにこれは分かりました。
大山さんは付属を1.0μFに変更しようかと迷われていましたが、市販のスーパーツイーターも1.0μFが多いと思います。この場合クロスは20kHzとなりますが、効果は分かるはずと云うことで採用されているようです。但し、高能率のホーンツイーターなどは0.22μF等のずっと小さなコンデンサーが使われますので、個々のツイーターとベースのスピーカーにより最適値は変わってくるので、最終的には好みで選ぶしかないようです。また、部屋の影響も大きいので推奨値を参考に前後を確認してみるのが近道だと思います。
スーパーツイーターを空気感のアップに使う場合などでは、今回の設定がハイレゾ音源などでは効果的だと思います。逆に古い音源やソロボーカルや小編成のjazzなどでは効果は感じ難いと思います。
私個人の感想ですがSiena(W3-1878)とZ501は音色がとても似ていると思います。またZ501の能率が88dB(ショートホーンで+2dB=90dB)であまり高くなくSiena(W3-1878)も88dBとほぼ同じためか、いかにもZ501が鳴っていますという感覚は皆無です。大体、スーパーツイーターを付けると音像が上に引っ張られる感じがしますが、このシステムでは音像の変化は全く感じません。
Z501の開発ストーリー(https://otokoubouz.com/z500/501.html)に「私が目指したスーパーツィーターは20KHz以上の人間の耳に聞こえるか聞こえないか分からない帯域を問題にするのではなく、 8KHz~20KHzあたりのいわゆるうるさい音と言われる帯域より上の高域をホーンで持ち上げることを第1に考え、、4KHz以下の耳につくツィ-ター帯域の音は極力でないようにする。これに尽きます。 」とありますが、Sienaとの組み合わせではこのような変化はあまり大きくありません。
また、④低音のキレがよくなる「超高域が増すと中域から低域の質感が改善することは普通に起こります。これは8KHzから15KHzあたりの可聴域の増加が音全体のバランスを変化させるためで、低音自体は一切変化していなくてもその効果は全帯域に及びます。超高域というたった一つのスパイスがスピーカー全体を引き立たせてくれます。」との部分ですが、経験されたことのない方には分かり難いですが、スーパーツイーターを追加すると超高域だけでなく低域も伸びた(厚みが出た)ように感じます。これはスーパーウーファーなどの様な迫力が増すといった類ではなく、質感が上がった感じで、音工房Zとは別の試聴会でも体感しています。今回はこちらの変化も感じませんでした。Z1000-Sienaは高さがH297mmと低いのに対し、変化のあったスピーカーは高さが2~3倍あるトールボーイタイプのバックロードホーン/BHBS系のシステムだったのが原因かもしれません。
以上、思い付いたことをつらつら書きましたが私の結論は、1000-Sienaはそれ自体非常にバランスが良くフラットで纏ったスピーカーで、スーパーツイーターを付けなくとも私には十分満足できるシステムです。スーパーツイーターの効果はありますが今回の条件の場合、大山さんには申し訳ありませんが是非にとお勧めはしません。試されたい方はAmazonで販売しているスーパーツィーターキットがユニット自体は同じはずで価格も1/3程度、コンデンサーも1.0μFが付属しますのでお勧めです。こちらで試されて納得されてからZ501を購入されても遅くはないと思います。Z501はタモ材(オスモカラーによるオイル塗装)とウォールナット(ウレタン塗装の限定モデル)が選べますので1000-Sienaと色を合わせられ見た目も魅力的です。余ったスーパーツィーターキットは予備部品や他のスピーカーと組み合わせるなど使い道はあります。
2)中低域の違和感(バックロードホーン/BHBSのネガな部分)はあるのか?
1)が長くなりましたが、2)を検証します。私の空耳ではなかったようで、音源を色々変えて聴いてみるとやはり曲によってBHBSの癖は感じられました。具体的に表現できるまで追えませんでしたが確かにアレと感じることが有りました。ただ、瞬間的な部分で曲全体に感じるようなものではなかったので、ある特定の周波数の音(楽器)にそのようなネガを感じるのだと思います。Z701-Modena(V5)を5年前に初めて聴いたときはずっとこのネガが付いて回りました。Z701-Modena(V6)になり大分緩和されましたが、Z701-Modena系に違和感を感じる人や密閉型好みの方は気になる部分と思います。
低域を伸ばすとその影響で中低域に盛り上がるなどの癖が出易いとのことですが、今回は超低域は欲張らなかったことで中低域の癖は極力抑えられているのだと思います。バックロードホーン/BHBSは今では特殊な形式です。長岡先生が亡くなられてからバックロードホーンは勢力が衰えたとの声を聞きます。この方式は科学的?に理論説明が難しく、理論の完成したバスレフなどと比較して傍流となりましたが、好きな方にはたまらない音であることは確かだと思います。(私も最初は違和感がありましたが慣れました。)
3)他に欠点はあるのか?
前回、『大山さんはメルマガで「フラットで重厚。どんどん音を上げてゆきたくなるような音でした。」と書かれていますが、音量を大小何度も変えてみましたが音量に関わらずバランスが揃っており音量をどんどん上げていっても煩くなく、下げても低域が痩せたりすることもなく同じバランスで鳴っていると感じました。』と書きました。今回は意地悪く更に音量を上げてみました。さすがあるレベルを超えると音が崩れてきて、大山さんからダメ出しが入りました。入力は RMS 12W MAX 25W ですので調子に乗って上げると限界を超えてしまいます。しかし、そこまで上げられる(上げたくなる)ユニットはそうそうないと思います。家で聴いているときの5~10倍ぐらいの音量で普通煩くて聴いていられないようなレベルです。逆に音量を下げていったときに真価を発揮します。解像度の低いユニットは音量を下げていくと、低音高音は勿論中音域も聞き取りずらくなり聴こえない音が出てきます。特に人の声などは誰でも分かります。自分の家で何時ものテスト用の肉声(私の大好きな映画の中のセリフ)を聴いてみたいです。
今回フルオーケストラを続けてかけてみましたが、スケール感はやはりマルチウェイや大口径にはかないません。しかし、音量によるスケール感はあまり変わりませんので、口径の大きなスピーカーで音量を絞って聴いたときより生き生きとしていながら聴き疲れしない音と思います。以上、なかなか欠点を見つけられませんでした。このサイズでは今まで聴いた中でトップクラスです。
欠点というより要望ですが、Siena(W3-1878)のユニット価格は42、800円でキット価格がMDF 54,800円、バーチ 64,600円ですが、ユニットをW3-2141に変更するとユニット価格が20、000円と仮定で、キット価格がMDF 32,000円、バーチ 41,800円ととても魅力的なプライスとなります。純粋に音だけで比べればSiena(W3-1878)がいいのは確かですが、入門機としてコストパフォーマンスを考えるとW3-2141のレギュラー品と云うのも捨てがたいものを感じます。MDFキット 29,800円の戦略価格を展開すればバカ売れの可能性もあるかもです。
最後にYAMAHAの9㎝フルレンジコンテストの続報です。以下のYAMAHAのホームページに入賞の10作品の他多数の作品が公開されています。
https://member.jp.yamaha.com/topics/3300?utm_source=ymmembers&utm_medium=email&utm_term=20241018&utm_content=link02&mkt_tok=MzU0LVRKQi05NDgAAAGWPctRPee4jxXvW1-XcjZh1bqyjGedNlBOPjRP-SyxWiemF1hUcHE8HwdhYMCBQdDOeZolh1uhDNyEtZ-We9G01su9Gcsf-LmtQKyYxx-B
8cmフルレンジとは思えないZ1000-Sienaの良い音に満足しました。
【Z1000-Siena】
音工房zの試聴会には初めての参加でした。
8cmフルレンジとは思えないZ1000-Sienaの良い音に満足しました。
試聴会では最初はスーパーツィーターZ501(0.47μFコンデンサ)有りでしたが、無しの試聴でも高音域の不満は無かったです。ゆったり聴いている分にはスーパーツィーター無しでもトライアングルやシンバルの音に不満は無かったです。スーパーツィーター有り無しの差は、気を付けて聞き比べをして初めてわかる程度の差でした。
中音域も明瞭で不満無し。低音域もしっかり出ています。
全般的にとても生々しい元気な音をしていました。
自分の持っている古くて安い10cmフルレンジSPとは雲泥の差でした。
ウォールナットカラーの完成品もありまして、そちらのほうが正面バッフルの集成材の継ぎ目が目立たないので、個人的にはそちらが好みでした。標準塗装だと集成材感が目立つかな、と思いました。
完成品のZ1000-Sienaと、キットのZ701-Sienaで価格差がだいぶあるのですが、試聴会後に来ました音工房Zメルマガ 2024/10/20「Z1000-SienaとZ701-Sienaの違いについて」の「プロの組み立てと塗装」のところを読み、なるほどそうだよなと価格差に納得した次第です。
それから、試聴室が自宅よりもライブ(残響多め)だったことも好印象だったのかなと少し思いました。自宅環境はカーテン有り、カーペット有りなので試聴室よりもデッドでなので自宅に音響パネルを導入してもいいかなと少し思った次第です。
オーディオ店とかの試聴でも、売り場フロアはスピーカーの外側はほぼ開放ですし天井も高いし、試聴室だとしてもそれほどライブな環境ではないことが多いですので、試聴会の部屋環境は興味深いものでした。
立ち上がりの良い綺麗な音
【Z1000-Siena】
Z1000-Sienaの試聴をさせていただきました。
音工房Z様からデモいただいた音源の全体の印象では、とても8センチとは思えない音が、立ち上がり良く鳴っていました。
持ち込んだ音源で感じたのは、特にピアノの中高音がピュアサウンドといった感じで、クセなくて聞きやすかったです。
ただ、持ち込んだ音源の音量が大きめになっていたようで、コントロールしなかったせいか、ベースの重低音が少ししんどかった箇所がありました。大音量には不向きとのご紹介が体感できたように思います。
一方、スピーカーのルックスでは、立体バッフル並びに特製の木製ダクトが、高級感あふれ、とてもいいです♪
ハイグレードコンパクトスピーカー
【Z1000-Siena】
10月19日/14:00~からの試聴会に参加いたしました。試聴室に入って見た新作のZ-1000 Sienaの第一印象は小さくてかわいい。スピーカーのセンターキャップが赤い銅色で愛嬌がある。 じっくり観察するとフロントバッフルの点音源を意識した彫りの深いカットがりりしく、又剛性の高そうなタモ集成材削り出しのダクトが高級感を漂わせている。側板のタモの板目模様も美しい。高さもA4サイズであり、ダクトの取付位置も前面配置なので本棚に置いても上手くフィットしそう。仕上げは高級家具のレベルで非の打ち所がない。音工房Zさんは一流のスピーカービルダーであると同時に一流の家具ビルダーでもあると感心致しました。
肝心の音ですが一聴すると、まず非常に音が拡がる音場の大きさ、それと生々しい臨場感がある。低音域は締まりのある立ち上がりの早いパワー溢れた気持ちの良い音質だと感じました。低音がこれほどパワフルで厚みのある8㎝フルレンジは初めてです。完成度の高いBHBSです。大山さんも説明していましたが今までのハイ上がり(高音過多)な音質とは違うスピーカーユニットのようでZ-501(スーパーツイーター)が最初から取付てありました。ただ高音が目立つセッティングではないとのことでしたので取り外しても違いは僅かでした。しかし高音の拡がりは明らかに取付時の方が良かったです。あえて弱点を上げれば中音域の情報量の多さや密度の濃さや、細かい音の解像感は少し甘いように感じました。それと重低音の体に感じる振動のような音はさすがに出ません。しかしこのような音質はニアーフィールド(狭い空間)でスピーカーに近接して聞く状況ではむしろ耳に煩わしくなく心地よいはずです。
最後にあくまで私の勝手な私見ですがこのスピーカーの性能を発揮する場所ですが例えばBHBS独特のパンチのある低音、拡がりのある中高音、しかもコンパクトであるのを生かしてTVのホームシアター用の仕様。それと同時にHiFiのステレオシステムにもなる今風な高級ホームオーディオ。 あるいはハイエンドオーディオシステムを持っているリッチな方が仕事部屋でセカンドシステムとして仕事の合間に一人静かに音楽に浸る等の様子が思い浮かびます。
一言でまとめるとZ-1000にふさわしい高級感を感じるハイグレードコンパクトスピーカーでした。
なかなか
【Z1000-Siena】
今回の視聴は有意義でした。
ルームの音響改善でスピーカーの音質、定位が確認し易く成っていた事と試聴者が3名で比較的リスニングポイントが良かった事があります。ただ背後の壁が近い為その反射音が気になります。リスニングポイントは1メートル程は前か壁の吸音処理が必要かと。床に座ってユニットの中心軸上でも試聴出来たのですが、その状態でないとSPの特性が分かりずらいのは明確です。
試聴者3名共追加ツイターを外す事を望みましたが、そこで考えたことがあります。大山さんはSPチーニング時どの様な状態で
試聴なさっているのでしょうか。SPのスタンドの高さからして椅子での試聴では身長の高い大山さんですとユニットの中心軸上
よりかなり耳の位置が高くなります。高域は指向角度が狭くなるのでユニットの中心軸上をズレるほどレベルが下がって聴こえますのでツイーターを追加していたのでは無いのでしょうか。
エージングについてですが誤解をしている人が多くいます。ユニット自体の振動による時間経過でエイジングは有りますが
それより大きいのはユニットを固定しているネジの緩みです。ウーハーなど大きなユニットが顕著ですが小さなユニットでも
起こります。ネジの緩みは一律では無くSPのLRによっても異なります。緩みによりエンクロージャーとユニットの間に不要振動が起こり音がぼやけ定位が曖昧な方向になります。各メーカーがどの程度の圧力で締めているのか興味が有りますがデータが出ている情報が無いので確認した事がありません。緩みの少ないミッドシップマウントが好みです。
SPの設置角度ですがミクシングスタジオのモニターSPは30度ほど内側に向けています。角度を付けず設置してありましたが
0度ですと仮想センターの音量が下がって聴こえます。ヴーカルものですとオケとの音量差が少なく成ります。
30度付けた状態で音楽は作られていますので収録状態の再現性で言えば角度は必要です。
さて試聴SPですがパッと聴いた感じアナログアンプのNFBを少し強めにかけた音の感じがしました。
NFBを強めにかけると周波数特性が向上しますが音の厚みが無くなります。そんなふうに聴こえました。
ただ再生機器自体の音の状態がわからない為、SP自体の音の特性は掴み切れません。
感でしか無いのですがアンプにより音楽的な方向になると思います。
使用したCDは『ウルトラ・マドンナ・グレイテスト・ヒッツ』Qサウンドを多く使用したCDで90年発売のものです。
調整されたSPで聴きますとQサウンドにより180度程度音が広がります。SPを角度30度にして正三角形頂点で床に座りユニットの中心軸上で試聴させていただきました。見事に180度広がりましたよ。やはり点定位と位相の良さが認められました。
だだマドンナのヴォーカルの低域の音が少なく痩せた音に成っていました。AADのCDなのでアナログの柔らかさが有るのですが
残念ながらその表現はあまり見受けられません。
同席した方がダイナミックレンジ、定位の確認に良いCD素材をかけてくださったので非常に参考になりました。
コストなどトータルとしてかなり優れていると思います。
ただSPスタンドをそこそこの物にしないと鳴らし切れないと感じます。
精緻で落ち着く音でありながら、パッションも光る!
【Z1000-Siena】
Z1000-Sienaを聴かせていただきました。音のバランスから、低音の周波数を下げすぎないよう箱を設計をされたとおっしゃっていましたが、とても美しい低音だとおもいました。私は、低音の周波数をさらに下げる必要を感じませんでした。低音の音圧は充分に強く、生々しさが心地よかったです。中音もとても好きな音でした。ツイーターですが、今回ご用意してくださった0.47uFのコンデンサで私は納得でした。比較しなければ、ツイーターがなくても違和感を感じない方は多いとも思いました。
私自身、近所迷惑を考えて、音量を落としてニアフィールドでスピーカーを聴くことが多くなりました。ニアフィールドでも綺麗に聞こえるような気がします。Z1000-Sienaはそこそこ小さいので、コンピュータの横にも頑張ればおけるかもしれません。
奇しくも大山さんがおっしゃっていた「長く聴いていたい音」について最近よく考えます。オーディオショウなどでも綺麗な音のスピーカーは沢山ありますが、長く聴いていたいスピーカーってどういう特性を見ればいいのですかね?音域があまり広くなくて、周波数特性もフラットとは言えないのに聴いていないスピーカーってありますよね。「聴いていたい」音の正体はなんですかね。ユニットの特性で説明できるのですかね?「聴いていたい」の正体は私にはわかりませんが、このスピーカーは1日中没頭して聞けそうです。
素晴らしい!
【Z1000-Siena】
フルレンジの印象をくつがえす、澄んでいてワイドレンジで感心しました。
こうした小さなユニットをボリューム上げて、そのユニットの能力を最大限に引き出して音楽を聴くのは楽しくて好きな時間です。組み立て式を買おうかなと思います。
Z1000-Siena 8㎝のパワーとは思えない
【Z1000-Siena】
今回、音工房zさまからの音源と視聴者持参のCDを聴く中でジャズやロック、歌ありのジャンルに合う感じしました。カメラで例えるとSONYのカメラは他社より輝度が高いと個人的に思っていますが、このスピーカーもある音域に来るとストレートのパンチを受けた感じがし、8cmのスピーカーとは思えない音圧でした。
スーパースワンを超える中高音の美しさ!!!
これは!!!
かつてない美しい音の解像感と音場感です!!!
ユニット丸裸に近い音が聴けるエンクロージャーとして名機スーパースワンがありますが(ヘッドを丸く円筒形に作ったのもあります)それ以来?いえ!おそらく音の流れがいちばんきれいなのではないと思われます
某社エッグシェル形状のスピーカーよりも痩せてますしね〜。。。
ただ。。。低音が出ないことでもこれまでのもの以上です
使っていてついつい「低音ほしーな〜〜」って思っちゃいます
解決法はちょ~ニアフィールドリスニング!
あとはサブウーファーかな〜(←欲しい!!)
Cannonball100はきっと聴く人を選びます
聴く音楽ソフトも選びます
ソロやデュオ少人数の音楽なら最高です!
あとたぶん
マニアな大大先輩方がお持ちの
現地録音マイク2本だけで録ってきました〜的なソフト
フツーに多チャンネルミキサーで編集された一般的な音楽にはしっかりウファー使ったスリーウェイとかをお薦めします!
それでもこのスピーカーの音の美しさは一聴に値します!
人生観が変わります!
生きててよかった!!
この音に出逢えて幸せ〜て必ず思います!!!
これから組み立てる方へ
大山先生の組み立て動画は必ずご覧になり
(そしたら誰でも作れます!)
上手くいったゾーといい気にならないで最後まで気を緩めないで作ってくださいね
↑
最後の最後で3ミリずれました〜(´;ω;`)〜
さくら
使用機材:
TEACの小さいCDプレーヤー
YAMAHAのいちばん安いプリメイン
FOSTEX FE108sol
注 アンプもCDプレーヤーも何台も持ってますがこういうシンプル系のスピーカーにはよく肥えたオジサマ仕様の高級アンプって何かが出てこない気がします!
松尾優「ピアノウタヒメ」
XNMU00001 IMU Music Japan
↑
おすすめです!
追記
スタンドに置くだけよりもマジックテープでグイっと縛りつけると音の輪郭がよりハッキリするような気がします〜
音場再現的には空間に浮かせられればベストなのかもですが。。。
完成度の高いキットとして5評価
詳しい制作レポートをダウンロードしてその説明通りに制作したが音頭版4と1の外側が口があく以外(1を押さないようにとのことと思う)すべてピッタリの部材加工精度だ。M8の全ネジと部材を痛めない圧縮木製のクランプで702Modenaのとき購入したもので各ステップ思い切り締めていったが最後のバフルの締め付けに長さが足らずホームセンターに走ったこととクランプが1本バフル締めで折れたことがあったが左右で細作に時差がつけていて難無かった。手持ちの足場用レンチ小を使った。マークオーディオのユニットとやら最初片方で鳴らせたらカタイ音と感じた(あらためてSP外観見るとその感じだ)がやがて手持ちDVDのギドンクレーメルの演奏が浮き上がってくるのを感じた。低音もこれだけで十分出てこれがメインになってしまった。
2匹目のドジョウ(8cm)は見つかったのか!
【Z1000-Siena】
今回は次期Z1000のZ1000-Sienaの試聴会ということです。2年ぶりのBHBSの新作ということと、大山さんが聞き惚れたというTangband W3-1878 を採用した自信作とのことでしたので期待が高まります。
本題に入る前に何時ものように前置きを書きます。今回の試聴会の一週間前には、MJオーディオラボで丸一日YAMAHAの9㎝フルレンジのコンテスト入選作品10点を試聴してきました。更にその一週間前にはMarkAudioの試聴会で2時間半試聴してきました。MarkAudioについては説明の必要はないと思いますので書きませんが、YAMAHAの9㎝フルレンジについてはMJ誌やネットでの作例公開など限られた情報しかありませんので文末に私の感じた(知りえた)情報をお知らせしたいと思います。
個人試聴のソースは1枚目はEAGLESのアルバムhell freezes overからhotel california (ライブ版)で音工房Zではお馴染みのデモ曲、2枚目は何時も持ち込む image 2 です。なお、今回からCDプレーヤーが新しくなったようでARCAMだったと思います。
外観は最初見たときチッチェ(失礼)と感じました。元々Z601-Modena ベースで開発された経緯があることとメルマガのZ1000-Siena 開発6、7を見てコンパクトにした理由が腑に落ました。Z1000はフラッグシップという先入観と過去のZ1000が大きかった刷り込みでそう感じてしまったようです。仕上げはバッフルは立体削り出し&他の5面は15mmバーチ合板突板貼りで艶消し塗装仕上がとても高級感があります。インターナショナルオーディオショウで見たヨーロッパ系の高級機にも遜色ない出来と思います。バッフルどころか箱全体を多数の面で構成するのが流行りの様ですが、価格が数倍から桁違いまでと私には無縁の世界です。箱が小さく内部構造がシンプルなのが幸いしてか、Z1000としては破格の22万円(キットはMDFが5.5万円、バーチが6.5万円)とリーゾナブル?Z1-LivornoS(V2.1)ウォールナットエディション 20万円と価格が近く選択肢が増えました。Bergamoの後、フルレンジのノーマルな箱は出されておらず、キットは止める方向ですとのことでしたが、私の願いが届いたのかキットもラインナップされ嬉しい限りです。5千円ぐらいの安いユニットも探されている由ですので、チープオーディオマニアの私には期待が高まります。
さて、話が本題から逸れてきましたので戻します。
商品説明の後デモの開始の手はずでしたが。なぜかPCの調子が悪く修復の間個人試聴を始めることになりました。私は2番目でしたが1人目の方の時最初はある違和感を感じていました。今回のユニットW3-1878は大山さんが絶賛されていましたので、何時ものBHBSサウンドが展開されると身構えていましたが、何故か低域から中低域に力感が感じられず、何時もの迫力がないように聴こえてしまいました。5年前に初めて試聴会にお伺いした時、Z701-Modena(V5)を聴いて感じた低域を無理に持ち上げているようなバックロードホーンのネガな部分が垣間見えるように感じてしまいました。箱が小さいのと基本がダブルバスレフの性かななどとも思いました。私の番になりhotel california/ image 2 からシンドラーのリスト、アディエマス変奏曲、マイ・フェイバリット・シングスを聴き、その後PCが治り10曲のデモの後個人試聴の再開と続きました。
3時以降は空きがあるので時間のある方はもう一度試聴OKとのこと、喜んで延長戦に臨みました。さて、このころになると不思議なことに最初に感じていた低域から中低域の違和感が全く感じられなくなっていました。2回目は image 2 からグリーン・ディスティニー、ジャスト・ウェーヴ・ハローなどフルオケ、バイオリン、女性ヴォーカルなどを次々に試聴しましたが何時もの音工房Zの音で何の違和感も感じなくなっていました。2時間弱足らずで急にエージングが進むとは考え難く、大山さんに実働時間を聞いたところ、やはりかなりの時間鳴らしているとのことでスピーカーが変化したのではなく、私の耳が慣れたと考えるの妥当だという結論に達しました。前置きで書きました通りこの2週間、音工房Zとは対極のスピーカーに慣れていたため、BHBSの癖が最初は気になったのだと思います。MarkAudioはシングルバスレフで音量はあまり上げられないが非常に反応が良く中域をとても綺麗に奏でるスピーカーです。これは中島社長のJAZZ好きを反映した音で木の響きを重視した自然な音ですが、正直低音の迫力はあまり感じません。YAMAHAの9㎝フルレンジも低音が出にくいユニットで、元々高級電子ピアノ用に開発されたユニットで色付けがないクリアーで反応が早いのが特徴です。つまりどちらも低音域はあまり上げない(伸びない)タイプの鳴り方のため、対極の低音モリモリの音工房Zの音に最初バックロードホーンの癖を感じたのだと思います。
以上の理由のためこれからは2時限目の試聴の感想をメインに書きたいと思います。多面構成のバッフルの効果か音離れが良く、FOSTEXのバックロードホーン程ではありませんが音が前に広がりとても8cmとは思えないスケール感が感じられます。フルオーケストラでなければ20cmと比べても十分戦えます。さすがにフルオーケストラではそれぞれの楽器の分解能力や広々としたホール感は負けますが、逆にソロパートやボーカルなどの美しさ、定位の良さ、小口径のレスポンスの良さでは楽勝です。また、BHBS(601ではダブルバスレフと解説)の効果で下は30Hzまで伸びているそうで、サブウ-ファーの必要性は感じませんでした。大山さんは高域にスーパーツイーター追加を勧めれれていますが、老耳にはW3-1878だけで十分で差はBergamoの時のように明確には感じませんでした。大山さんはコンデンサーのクロスをもう少し下げるか迷われてましたが、私は無くていいんじゃないと思いました。スーパーツイーターの金額でW3-1878がもう1セット買える金額ですので私ならW3-1878をもう1セット買います。(スイマセン嘘です、高級ユニットを4個も買えませんので、涙)
大山さんはメルマガで「フラットで重厚。どんどん音を上げてゆきたくなるような音でした。」と書かれていますが、音量を大小何度も変えてみましたが音量に関わらずバランスが揃っており音量をどんどん上げていっても煩くなく、下げても低域が痩せたりすることもなく同じバランスで鳴っていると感じました。音がクリアーなのも小口径のメリットで、口径が大きくなるとコーンの剛性が足りない場合歪が出やすくなり、剛性確保のため対策すると重くなりレスポンスが鈍くなったり他の部品にも影響が出るようで、このユニットのMms 2.0g と低いことが切れ味の良さの一因と思います。Qts 0.28 とバックロードホーンとの相性も良くこれだけ好条件が揃えばいい音がしない方がおかしいくらいです。19日の試聴会はまだ空きがあるようですので購入を検討されている方は是非試聴されることをお勧めします。限定30セットの目途がついたとおっしゃっていましたので残りは少ないようです。
キットの試聴会では完成品との聞き比べができるように要望しておきました。どのくらいの差に収まって来るのか今から楽しみです。キットの方も順調に予約が入っているそうで発売キャンセルになることはなさそうです。因みに、Z601をすでにお持ちの方はそのままユニットを交換するだけでほぼ同等の特性を得られるとのことですので、ユニットだけ買うのもアリと思います。
今回 Tangband のユニットを多数調べて頂いたこととても感謝しております。石田師匠クラスでないとこれだけの数量を購入して箱を作るのは現実的ではありません。現在、国内で扱うお店が少なく海外は送料などの問題もあり慣れている方でないと二の足を踏むと思います。今回が成功すれば(売れれば)他のサイズも製品化があり得るそうなので、年一ぐらいで出してもらえると楽しみです。
最後になりましたが、YAMAHAの9㎝フルレンジについて書きます。残念ながら高級電子ピアノ用でユニット単品としての発売はないそうです。オーディオ業界の活性化の一つとしてMJとタイアップしてイベント企画したとのことで、商品の詳細はあまり公表できないとのことでした。実は私も応募して出品予定でしたが、製作途中で暑さに負けて作業が進まず時間切れとなってしまいました。入選された方の作品を見るとどれも素晴らしい出来栄えで手間暇を掛けたことを物語る手の込んだ作品ばかり、自分の不甲斐なさを反省しきりです。MJ冬号に小澤さんが全作品をデータ付きで記事に書かれるそうなので詳しくはそちらご覧ください。
このユニットの特徴は、コーン紙はヤマハ独自の振動系素材テクノロジーを採用した新開発素材で開発に10年掛かったそうです。Mms ( = M0 ) は 2.8g と平均的な重量と思います。高剛性の割には軽量ですが内部損失が非常に高く歪が少なくクリアーな癖のない再生音が特徴とのことです。定格入力は15Wですがエッジにこれも新開発のヤマハオリジナルの発泡ゴムを採用しているため、定格を超えたかなりの音量でもボイスコイルが底付きすることは無く歪まずに再生可能とのことです。通常のゴムエッジではフルレンジでこの性能は出せないと説明されていました。発注部署からの性能への要望がかなり高く、結局フルレンジに近いものになってしまったとのことでした。電子ピアノは電気的にアコースティックピアノの音を再現するため、スピーカーは色付けのないクリアーで歪の少ない性能が要求され対候性にも優れていないといけないといった点にも配慮しなければならないそうです。最低共振周波数は110Hzと高めのため口径の割には低音は出にくい面があるようです。作品でもバックロードホーンやBHBS以外のバスレフ系は概して低音はあまり出ていませんでした。MJオーディオフェスティバルでも石田師匠のBHBS以外は低音はあまり出ていませんでした。Q0(Qts)は0.66で推奨エンクロージャーはバスレフです。とはいってもそもそも開発の主旨がオーディオ用ではないのでそれをとやかく言うのは野暮かもしれません。
MJオーディオラボで賞典外(締め切り過ぎたため)の方の作品が、お昼休みにデモされました。この方はプロのスタジオエンジニアで、avexの半分近くはうちのスタジオで録られたとおっしゃっていましたので3流エンジニアではないと思います。普段スタジオの現場では大型モニターSPを使用することは1割ぐらいしかなく、9割はYAMAHAのNS10Mを使用しているそうです。理由は音楽ソースのユーザーに近い環境の音で作業するためと、大型スピーカーは音場が広がり過ぎ(音がボケる)正確に細かなチェックをするには向かないからだそうです。作品は左右一体型で方CHが5L幅が60cm程度のほぼ直方体、バッブルは左右の干渉を軽減するため中央から5度外に向いています。中央に8cm×12㎝角程のフェルトが張られておりこれでも音が変わるそうです。内部には縦横奥の3方向に1/4波長の共鳴管を仕込んで定在波を0に抑えており、吸音材は極少量しか使っていないそうです。アクティブスピーカーでアンプはこのスピーカー用に専門技術者が作ったデジタルアンプで、低音が不足するので6dB低域のみ上げてあるそうです。確かに丁度昔の大き目のラジカセぐらいの大きさです。音は皆さんにはつまらない音に聴こえるでしょう、とおっしゃられる通りフラットでクリアーですがいい音色という類ではありません。ある意味無味乾燥と云える音とでも言ったらよいのでしょうか。昔からモニタースピーカーへの憧れはオーディオマニアならきっとあったと思います。スタジオ紹介の写真には必ず正面の壁に大型スピーカが埋め込まれ、ミキサーの上にはオーラトーンかNS10Mが置かれていました。本文には小型スピーカーはラジカセなどでの使用のチェック用で大型スピーカーがメインといった内容が多かった気がします。時代が変わったのか当時の記述に誤りがあったのかは定かではありませんが、雑誌や評論家の信憑性はよく考える必要があると改めて考えさせられました。
率直に驚きでした。全音域が迫ってくる感じ
【Z1000-Siena】
Z1000-Sienaの記事に惹かれ、初めての試聴会に大阪から出向き参加しました。伺ってよかったと痛感しました。拙宅には大はパラゴンから小はKX-5Pまで並んでおりますけれども、もっと早く出会えていれば投資も少なくて済んだのになぁとまで思いました。スーパーツィーターも繋いでいただきましたが、恐らくそれをカバーする領域まで本体で出ているし、下は30か40の手前くらいまで充分に再現していたと思います。御社のスピーカーを更に聞き込んでみたいと思っています。ありがとうございました。
小さな巨人
【Z1000-Siena】
御社HP初見して10年 宣伝に決まってると思いながらも清水の舞台から飛び降りたつもりでz800-fw168hr入手 何回も裏切られたオーディオ製品のなかでも最良の品物でした 以来御社のファンになり試聴会の機会を狙っていた折に当会参加 フルレンジのものと最高値のものとでは役者が違うと思いきやまたしても大逆転 この図体でよくこんなにスケールの大きい音がだせると思い驚きました 他社の同サイズのものとは役者がちがいます まさにMIGHTY! MIGHTY! 小さな巨人です
z1000sienaは小型spのホームラン王です
小口径スピーカーと比較的小さな箱からと思えない音場出現
【Z1000-Siena】
スピーカーユニットの性能を決定づけるパラメーターなど理解するところではないが、磁界をより強くして減衰ファクターを大きめにするとかそうした根本的な所から独自に開発されたユニットとのこと。それがよくまとまった良い音を再生させ、様々なボーカルからクラシックまで広範囲にびっくりするほどの低域からスーパーツィーターとマッチする高域まで実に自然な音場をくせなくなめらかに作り出していると感じた。
極小振動板で極美の音楽再現
【Z1000-Siena】
Z1000-Sienaの試聴会に参加しました。
8㎝フルレンジスピーカーユニット自体は実際に見ると本当に小さいという印象。
しかし音工房Z様はこれぞフルレンジの王道とおっしゃる。
その8㎝フルレンジスピーカー最高峰を極めるという意気込みが外観の風格に確かに現れております。
聴く前は半信半疑でしたが、実際に放たれた音は見た目とは裏腹に、この振動板でここまでの高音圧と広帯域は予想外でした。
さらに点音源の特質なのか部屋の端で聴いていてもステージの拡がり感が実に広大で心地良く、全帯域が均等に表現されており、高忠実度再生とはこのことなのだと実感させられました。
大きいほど良いという先入観は粉々に打ち砕かれました。
ギターソロ、サキソフォーン等の管楽器、弦楽アンサンブル等の小編成では伸びやかさ艶やかさ粒立ち全方位に拡がる音粒子の拡散等の要素でZ1000-Sienaは全世界のスピーカーを相手にしても勝ち目が十分にあると感じました。
ですが、入力強度の限界を超えると少々危うくなる場面もありました。具体的には大編成オーケストラの最強奏では飽和感を感じてしまいました。当たり前ですが物理的限界はあるということです。
その特性を理解して適正範囲内で響かせるのであれば音楽の風景が快楽の光で一変すること間違いなしです。
この度の試聴会では音工房Z様のスピーカー開発への熱意と努力、音楽再生に対する感性の高さに触れることができて大いに触発されました。これからのご発展を心から願う次第であります。
導入してよかった!
Z600-Cannonball100との組み合わせです。
Z600-Cannonball100+OM-MF4-MIKAではさすがに低音が厳しいのでZ506-Livornosub2追加しました。当初仕上げは何もせず、全面を覆うサランネット枠を作成しましたが出来が悪く、バッフルは5mmのアガチス板、上面は6mmシナ合板でオイル仕上げとし、だいぶ見かけが良くなりました。
低音に拘ると大がかりになるので、今までやせ我慢していましたが、相当解消しました。コルトレーンを気持ちよく聞ける(いままでなかなか達成できなかった)のが私にとってはうれしい驚きでした。小編成のものが好みで、ライブでスピーカーを通さない生の音を再生できたらと思っていますが、かなりいい線行っていると思います。
主な機材:Soundgenic→AIT研究所ES9038PRO DAC(バランス電流出力)→Z600-Cannonball100自作PX4シングルアンプこれは直結: Z506-Livornosub2はBehringer CX2310 (80Hz -24db/oct)→ BakoonProducts 現行品ではAMP-5521MK4相当品(15年位前にキットで購入、出力段の電源はチョークインプット、抵抗は可能な場所はVishey VSRなど相当改変してます)
写真のZ600-Cannonball100とZ506-Livornosub2の間に横置きしているのはZ700W-OMMF4MICA+ModenaでAVアンプ(Marantz Cinema70)につながっており、フロント用です。(センターはZ1-Livornoサラウンドは2019年マークオーディオ)
大正解のスピーカーです。
良いスピーカーです。
届いてポン置きでも、素性の良さが感じられました。
重心低めで、高音の伸び、低音の出方、低中高音のバランスも自然で、モニター的な音と言うのでしょうが、多数の方々が、これで満足されるのでは?と思えるレベルで、価格を上回るパフォーマンスだと思います。
Nautilus805を越えるものを作った的な触れ込みも、決して誇大ではないと個人的には思います。
ただ、他の方のレビューにもありましたが、低音が膨らむとありましたが、正に私もその調整に苦労し、このレビューの書き込みまで、約半年掛かりました。
色々な調整方法があるのだとは思いますが、私の場合、バスレフは触らず(途中、色々な材質、量で、吸音材入れたりしましたが、曲やアルバムにより良かったり、イマイチだったりなので。)、結果、ケーブルを単線に変更、スタンドを剛性の高いもの(と思われるもの)にすることで、思い描く出音となりました。
スタンドはクライナ製で、別の目的で所有していたため良かったのですが、新たにに購入するには、結構、お値段はるものではありますので、音工房Zさんには、手頃で相性の良いスタンドを併せて提案頂けるなど工夫を講じて頂けると、より良かったとは思いました。
なお、ちなみに、私、Nautilusではありませんが、805Dのユーザーでした。
環境の都合で5年ほど前に手放し、中古も含め、価格的に大掛かりではないシステムで楽しむつもりで、手頃な価格のものを6セットほど試してみましたが、しっくりくるスピーカーに出会えない中、音工房Zさんのホームページを拝読し、何となく出音のイメージが浮かんだので、これならばと考え購入に至りました。
結果、大正解でした。
当然、当時とは、使いこなし方も環境も違うので一概に比較は良くないかも知れませんが、私にとっては、805D同等以上の好みの出音となりましたので、この先、一生使い続けるスピーカーとなることでしょう。
良いスピーカーのご提供ありがとうございました。
もっと、世に拡がることを願っております。
初めてのスーパーツイーターがZ501でよかった!
まずはセオリーに従ってこのあたりかな、と設置して聴きはじめ、数ミリほどの前後調整はしましたがとりあえず6~7時間あたりのところです。
再生環境は10㎝フルレンジとZ501、真空管のプリアンプとトランジスタのパワーアンプでシンプルにドライブしています。
ソースはワンポイントマイクでの収録音源、CDなどが多いです。
製品自体は工芸品のような佇まい。10㎝ユニットを収めたキャビネットとの見た目の調和も良好です。
私の期待値による思い込みもあるかもしれませんが、3時間あたりから化け始めたように思います。ベースやチェロなど楽器の輪郭が浮き上がりゾリゾリした生っぽい感じであったり、ボーカルの歌詞が聞き取りやすくなり、ヴァイオリンは響きの厚みと滑らかさが向上しています。空間表現においては演奏会の場で聴いた記憶の音に近づいた感じがします。
驚いたのは音量を絞っていったときでも、低音部はこういう風に弾いていたんだと輪郭がぼやけずにわかることです。
今もまだ音は変化し続けているようです。変化の仕方はゆっくりになりましたが音楽の潤いが向上していっている感じがします。
スーパーツイーターは他社からも数多く発売されていますが、自分にとって価格は容易に手を出せるものではなく、まあなくても聴けるものだし、程度に考えていました。ですがご縁あってZ501の開発経緯を拝読し、価格は意外なほど。今回賭けという買い方ではなく、確信に近い購入となりました。
先にインプレッションを述べましたとおり、誇張のない自然な高域の拡張は自分には初めての経験ですが、Z501を迎え入れて得たものは言葉だけではとても表現しきれません。初めてのスーパーツイーターがZ501であったことにただただ感謝です。
期待したとおりの音でした
評価に使用したアンプ,SUN AUDIO SV300BE(電源コンデンサ追加,パスコン交換,オーバオールNFB推定5dB前後追加),FOX-BAT MK-3(整流回路ノイズ低減対応済み),トリリオンCleverish400(電源平滑コンデンサー周辺配線大幅改修済み),音源mrantz HD-DAC1 出力を前記アンプに直結して聞いてます。(コントロールアンプ経由では大幅に情報量が低下するので評価の時は直結しています)
Z1-LivornoS2到着から16日、使用時間およそ30時間前後ですがほぼ期待した音が出ています。
パイオニアS-9500よりは軽快で心地よい音として感じています。
TAD TL-1601b+箱バックロードホーン,2インチホーンTD-4001+ATT:GA300 とは聞こえ方が異なるので良い悪いとは言えませんが、切り替えて楽しめます。 TADの聞こえ方は少し重いがゆったり広がった聞こえ方、Z1-LivornoS2は軽快で一の定まった聞こえ方です。 使用している部屋は7畳程度の洋間作りで石膏ボードの壁に囲まれているので、葦簀で反射音を抑ています。 この葦簀がないときはホーンの反射音がひどくて音が360°全方向から聞こえるような感じでした。 他の設置環境だとどのように聞こえるのかわかりませんが気に入ったおとでなっています。
TADでは前記のアンプ3台で音が違うように聞こえるのですが、Z1-LivornoS2ではTADほどの違いは感じられません。 能率の低い分だけアンプ出力を大きくして聞くので違いを感じにくくなるのか、使用時間が短いためなのかわかりません。