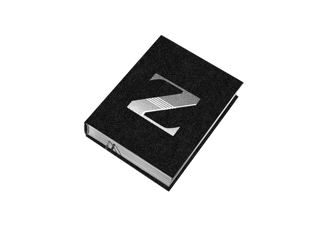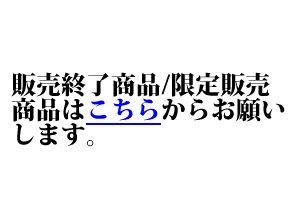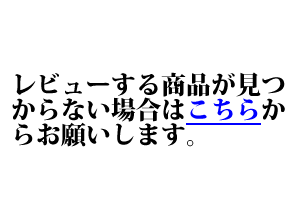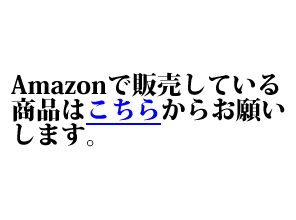レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
評判通り、素晴らしいスピーカーでした
レビュー遅くなりました。
R3年3月末にキットが届いておりましたが、忙しく直ぐに製作に取り掛かれず、4月末にやっと製作開始、精度の高い板カット&ダボ穴に助けられ、セミナー動画を見てGW中に箱は完成。
セミナー動画を見て染色&2ウレタン塗料による塗装に取り掛かりました。単身赴任先で模型用のエアブラシで挑戦しましたが、失敗&サンディングを繰り返しエアブラシはあきらめました。
その間にネットワークの半田付け作成、ブチルゴム&ゴムグロメットでフローティング化。
自宅の車&バイクメンテナンス用に使っているエアコンプレッサーを活用してのエアーガン塗装に変更、早速工具用品店でエアガン購入。
セミナー動画を何度も見直して、着色、下塗り3回、上塗り3回。乾燥には3日おいて溶剤の匂いがしなくなったところで#1200サンディング、コンパウンド粗目・細目・極細で磨きあげました。筆塗やエアーブラシより楽で綺麗に仕上がったと自負しております。メーカー製同等の出来に自己満足。
翌日、ネットワーク&ケーブル端子&ツィーター&ウーハーを取り付け音出し開始。
エージングが進むにつれて、バランスの良い音が出て来ており大変満足しています。
しばらくZ1リボルノを楽しむつもりです。
次は、Z800+Z505にするか、開発中のZ1000も楽しみです。
アンプ ヤマハRXV483 マランツSC5F・BB5F・SM5F
CDプレーヤー DENON DCDSA11
友人宅へ持ち込みテスト アキュフェーズC240&P300X
クイーン 松任谷由実 レディガガ&トニーベネット
エリッククラプトン レッドツェッペリン 竹内まりや
思っていた以上!!
これまでMonitor Audio, Bronzeを使用していましたが、音出しした瞬間今まで聞こえていなかった音が沢山聞こえるようになりました。低音のめりはりも格段に上です。これからエージングを進めればさらに向上すると思いますが、現時点では値段の数倍の価値はあると思います。また事前にメールで連絡したら、予定納期よりも3週間以上繰り上げて送っていただけました。ありがとうございます。自作は初めてでしたが組み立ての質問にも一日で返信いただきサポートも完璧です。
使わない環境には戻れない
【スピーカー能率補正機能付スピーカー切替器】
Z800-FW168、D-55(FE208ES-R付)、jazzman J-01X、(この他にもあり)という能率がかなり違う機種をソースごとに選んで鳴らしています。
これまでそれぞれの特色は分かっていたつもりでしたが、音量を揃えた上での瞬時切り替えで、きちんと比較することにより、それぞれの特色が鮮明になりました。個性をこれまで以上に楽しめるようになり、それぞれのスピーカーと改めて出会ったかの思いです。使用しているアンプ(ROTEL RA-980BX)には音量リモコンが付いていなかったこともあって、環境がとても快適になりました。
不満はまずデザインです。プリアンプユニットとセレクターユニットとの一体感がありません。ユニット間の接続端子の場所が表と裏とに異なっている理由も分かりません。電源スイッチが後部にあるのも不便です。
また、取扱説明書は少々分かりにくいです。スピーカー接続端子への番号の振り分けは、なぜこうしたのか不思議に思います。将来的にはスピーカーユニットの増設も考えていますが、この取扱説明書を見ると、私にはハードルが高いかもと思えてしまいました。
それはともかく、今の私には必需品です。ご紹介いただきましたことを感謝いたします。
貴重な経験に基づいたもので大変役に立ちます(と思います)
大山様の過去の長い経験から得た貴重な内容だと思います。
ですが、私のような経験と知識の少ないものにとっては、とても数日で理解できる内容ではありません。これからじっくりと読ませていただこうと思います。
自作スピーカーは、さまざまな工夫ができる点が最大のメリットだと思いますが、
スピーカーユニットと箱のそれぞれの素性の良さがベースにあって、
そこからのさまざまな工夫が無駄にならずに生きてくる、と考えています。
既成品スピーカーでは飽き足りず、自分で一から箱を設計するような知識も技量もありませんので、今回、販売を予定されている「Z1000-FE168SSHP」のキットを使わせてもらって、
「自作ハイエンドスピーカー大百科事典」を参考に、いろいろ楽しく自分だけのスピーカーの世界を構築していければと期待しております。
絶対お勧めです。
何年か前に買った、Z600-SAF80AMG を今まで仕事の都合で連休が出来たので、去年の秋やっと組み立てた。
クリアラッカーつや消し仕上げで奇麗だ。
8㎝とは思えない音に Z701-Modena(V5) が再発売されるのを待ってスタンドも一緒に、注文した。
クランプも8本足して12本とし、ベニヤ万力も揃えてある。
音道で心配な部分には、ウッドパテで内側から補強しました。
若い頃、コーラルBL20Dをラックスキットのプリとメイン(三極管PP)の管式アンプで鳴らして、圧倒的迫力を楽しんでいた。
月刊誌「電波科学」でクリススキットを知り、トランジスタ式にかえ、マルチセルラホーンを作ったり、ついにマルチアンプになった。
JBL LE14H(200㍑密閉箱)とコーラルM100(マルチセルラホーン)の2way。
その後Ampの配線は秋田のヘルパーYさん頼むことにした、15年くらい経っても全く問題が起こらない(もっと経っているかな)。
Z600とは違う低音です、低音を強調しているいる感じではないのですが、ここだと言う時にしっかり出ています。
1つの世界がつくられているのではないでしょうか。
CDプレーヤー、このSPとプリ、10W×2位のアンプがあれば、それで満足できる世界が広がると思われます。
現実に夜遅くなったら、このSPだけで聴いています。
サブのSPはクリスキットの管式プリと真空管整流のWE300BとRCA2A3のシングルアンプをDiatone,sysで設計、今はなきラフトクラフトに発注した、米松合板付板張60㍑バスレフのDiatoneP610Bに繋いで聴いています。
このSPは横置きにするとメインSPの上に丁度置けるように設計したのもで、大震災の後(宮城県なので)縦置きに出来るようにキャスター付きのスタンドを作りました。
上記のマルチアンプに匹敵する音を楽しめます、P610Bの完成度の高さを感じます。
Z701-Modena(V5) はEL84シングルアンプ(6W弱)で聴いてましたが曲により音が飽和する時があります。
WE300Bを繋ぐと、どののCDでも、圧倒的な迫力が静寂の中から音が出てくる。
友人のJJ300Bではさわやかなサウンド、明らかにWE300Bと違うのがわかります。
CDによってはコーンが飛び出るのではと思える時もあります(Romantic Jazz Trio。so In Lave 、「A Perfect Match Ella and Basie」などは
最近スペアに用意しているクリスキットのプリMark8DとP-35IIIに繋いでいます。
「夢のあとで」ローランド・ハナ・トリオ、「シャイニーストッキングス」ジェニー・エバンスを聴くとほかのSPは要らないのではないかとも思える。
「Best of The SWINGLE SINGERS」・「Swingin’ on Broadway」などはどはまりだ。
「耳でわかるシステム診断」のCDではメインSpでもZ701-Modena(V5)でも50Hzは完全に聞こえる。
つでに私の耳で10,000Hzも聞こえます、以前はメインシステムで12,000Hzも聞こえてましたが年のせいか聞こえない(残念)。
家内はどちらのSPがなっているかわからないと言います。
なおリスニングルームは軽く防音をした7帖半の洋間です。
ちなみに真空管アンプはなき父の作品です。(父の昔のアマ無線仲間にチューニングしてもらっています)
先日友人にZ600-SAF80AMG、 Z701-Modena(V5) とEL84シングルアンプを貸したら、時々飽和するが、
他のアンプに繋いだら、すごいSPだと言ってました。
今作るべきか迷っている2wayのSPはどうかは判りませんが、 他にspを持っている方にも、Z701-Modena(V5) はコストから見ても一度は作ってみるべきSPではないかと思います。
メインのSPと比べて楽しむのもいい。
今もベースソロが朗々と流れる「夢のあとで」を聴きながら、この文章を入力してます、
絶対お勧めです。
テレワーク環境が充実して大満足
大昔に長岡先生の設計したスピーカーを3台自作したことがあるのですが、オーディオはお金もかかるので、今の家に引っ越すときにすべて廃棄して、ポータブルスピーカーとサウンドバーで良いかとあきらめていました。
ですが、テレワーク用デスクの購入を検討している時にZ600-OMMF4発売のメールを見て、タイミングの良さに我慢できずに注文しました。
機材も何も持っていなかったので、音工房Zさんのデスクトップオーディオラックキットへの収納を前提にして、DACはFX-AUDIO- DAC-SQ5J、アンプはお勧めのNOBSOUND DOUKAUDIO M3にしました。また、PCやiPhoneから有線接続したくなかったので、Soundgenic HDL-RA3HGを購入しました。(音工房Zさんのブログにレビューが掲載されたので、プロでも購入するものだったのかと嬉しく思いました)
日本、海外問わずポップ・ミュージックを中心に聴いていますが、クリアな音と定位の良さに大満足です。お勧めのアンプを購入したので、サブウーファーの発売も楽しみに待っています。昔と比べて安価でコンパクトな機材で良い音を楽しめるようになり、良い時代になりました。
実は、Z600-OMMF4の音を聞いたことで、サウンドバーに我慢できなくなり、Z701-Modena(V5)も注文しました。テレビの横に設置するのにZ102スピーカースタンドキット(V2.2)も必要なので発売待ちです。サブウーファーと併せてよろしくお願いします。
満足!!
機材は、fx-audioのプリ(tubu01j)とパワー(fx501j×2)。2か月ほどエージングしていますが、音がまともに聴けるようになりました。音の解像度が高いのか中高域がクリアで満足しています。低域は、このユニットの大きさとしては驚くほどよく出ていますが、しいて言えばバスレフっぽい音と言うか、少しボンつくような感じがします。また欲を言えば、もう少し音に艶やまろやかさが欲しいところです。全体としては、このサイズでこの音質のスピーカを購入して満足しています。
BHBSに興味が湧きました
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
スピーカー視聴会 2021/06/24
一言で「BHBSに興味が湧きました」
ハンドルネーム:ぱつら
●こんな耳の持ち主のレビューになります。
オーディオ歴1年。
正直、オーディオ装置の良し悪しは、よく分からない。
形容詞で語られても、全くイメージがわかない。
なので、数値(論理)で語っているオーディオ本を読み漁る。
いただいた「趣味のAudio」上下巻も、一通り読破。
理想のオーディオ装置を理屈では理解できたが、実際にそれがどんな音なのか結局分からない状況にある。
ただ、自分が好きな音がどんな傾向なのか、最近やっとわかってきた。
少なくとも「右肩下がり型」や「かまぼこ型」よりも、「ドンシャリ型」が好み。
プレゼンス帯域がうるさいのは、耳が痛いので嫌い。
音楽との関わり状況。
趣味でトランペットを45年ほど、ジャンル問わず吹いている。
そのため音源の聞き方は、「演奏のための参考用」として聞くスタイルで聴くことがほとんど。
よって、細かいニュアンスが見えやすいモニター的な再生装置が好き。
ヘッドホンで言えば、MDR-CD900STが好き。
自宅には自由に音が出せる環境がなかったので、ここ1年ほどはカーオーディオとヘッドホンでオーディオを楽しんでいた。
最近、小音量であれば自宅でも音が出せる環境が作れたので、アンプとスピーカーを調達。
アンプは、ディスクリート部品で組んだ手のひらサイズの自作品(出力1W:8Ω時)。
スピーカーは、音工房ZさんのZ601にZ-Modena MK2、同じく音工房Zさんのスーパーツイーターを、amazonで調達。
我が家の環境では、1Wのアンプでもうるさいくらいの音量が得られている。(SRC造)
複数のスピーカーをスイッチで切り替えて試聴するのは、初めての体験。
レギュラー製品の試聴も可能とのことで、勇気を振り絞って応募。
また、入手したスーパーツイーターのセッティングにも悩んでおり、ヒントがもらえればと。
正直なところ、Z1とZ701の試聴が主な目的であった。
●試聴したスピーカーは6種類
1.Z1000-FE168SSHP + T90ASE
2.D37 + T90A?
3.B&W802
4.Z800-FW168HR
5.Z1-Livorno
6.Z701-Modena
・箱の分類としては、3種類。
・バスレフ
・バックロードホーン
・バックロードホーン・バスレフ
・スピーカー構成としては、3種類。
・フルレンジ一発
・2way
・3way
・スピーカーユニットは、全て異なる。
これだけ条件が違えばやはりどれも個性豊かで、素人同然の私でも瞬時に切り替えればそれぞれの音が違うのがハッキリと分かる。
●持ち込んだ音源
作曲家・河合奈保子のアルバム「ブックエンド」より「心の窓に光りを」。
イントロから1分40秒間を、繰り返し再生。
スーパーツイーターのセッティングに悩んでおり、そのヒントが欲しくて10kHz以上の超高域が痛めのこの曲を選択。
スネアの音色、金物類の音色、「さしすせそ」の音色などに注視して試聴。
また、間奏のギターソロの後ろで聞こえる子供たちの遊ぶ声(たぶん6人)での分解能の確認。
試聴の時間は恐らく数分であろうと想定し、絞りに絞り込んで初めての試聴会にのぞむ。
●初試聴会の感想
・音の個性は、箱の個性が相当に強く出ることを体感。
重低音や超高音はスピーカーユニットの性能がものを言いそうだが、それ以上に箱がものを言っていると感じた。
スピーカーユニットの性能を、箱で如何に引き出すか。
音工房Zさんをはじめとする「スピーカーの自作をサポート」するメーカーさんが、市場に無い個性的なキット製品を開発し世に提案する意義を、はっきりと理解することができた。
・高域から超高域は、どのスピーカーも過不足なくバランス良く出ているようで、金物類や「さしすせそ」は、どのスピーカーもかなり落ち着いて聞こえる。
間奏のギターソロのバックの子供たちの声の位置もハッキリと聞き分けが可能で、そういう意味では大きな差異が見られない。
耳に刺さらないようなバランスというものを体験でき、自宅のスーパーツイーターのセッティングに非常に参考になった。
・一方で中低音、低音、重低音の違いが、確実にそれぞれのスピーカーの個性となっているように感じた。
バスレフとバックロードホーンのそれぞれの特徴を、形容詞では耳にしたことがあるが、実際に聞き比べてその形容詞の意味が何となく理解できた。
バックロードホーン・バスレフ(BHBS)は、確かにそれぞれの良いトコ取りのシステムだと感じた。
●Z1000-FE168SSHP + T90ASE の感想
経験が浅く絶対的な基準を持ち合わせていないので、あくまでも比較による感想。
傾向としては先にも書いた通り、好みのヘッドホンはMDR-CD900ST、どちらかといえばドンシャリ型が好きな耳による感想となる。
・ベース音域の量感が素晴らしかった。
ソースにもよると思うが、他の5機種のどれよりも量感があった。
BHBS仕様であり低域の音の立ち上がりが僅かに遅れるのが気になったが、純粋なBHであるD37に比べると遅れが大きく改善されているのがはっきり分かる。
開発レポートにあった「38センチウーファーのJBLS9800」と比較して聞いてみたかった。
管弦楽のような比較的音の立ち上がりが柔らかな表現が特徴のソースには、とてもふくよかに聞こえてよく合うと感じた。
バスレフの3機種は、低域の立ち上がりは確かにクリアに聞こえる。が、BHBSと比較すると量感が物足りなく感じた。
Z701の低音の量感には、噂には聞いていたが8cmの音には思えずとても驚いた。
これがうまく設計されたBHBSの凄さなのだろうと思った。
・高域はうるさくもなく寂しくもなく、ちょうど良いバランスと感じた。
持ち込んだ音源は、高域がかなり痛めだったはずなのだが、とても自然に聞こえた。
スネアドラムの音色も、打点とひびき線のタイミングやそのバランス等も違和感はない。
他の方がお持ちになられた音源も聞かせていただいたが、どれも違和感は感じなかった。
フルレンジ一発のZ701はツイーター無しのせいか、金物の音色に違いを感じた。
・総合的には、耳にした音源の範囲では、低域から超高域までバランス良く再生出来ていると感じた。
ツイーターの繋がりも良かったと感じた。
BHBSの個性と思われる低域の過度域の特性も、十分に許容範囲と感じた。
●試聴後に「Z1000-FE168SSHP エンクロージャー開発」レポートを改めて読み直すと、開発1から開発7までのテストがそれぞれ何のためにやっていたのかの理解が、非常に進んだ。特に開発7の聴き比べは、何が目的なのかが実際に聞いた音なのでピンときた。
やはり音は実際に聞いてみないことには、何も分からないことを改めて学習。
貴重な機会を与えてくださり、ありがとうございました。
P.S.
おかげさまで、自宅のスーパーツイーターのバランスが納得いくレベルになりました。
位相の問題だったようで、設置位置を調整したら落ち着きました。
すっかりBHBSに興味が湧き、Z701を注文。
7月末の納品が楽しみです。
私のような1Wアンプで音量十分な環境では、逆にZ1000-FE168SSHPのような楽に低音が出せるスピーカーの方が小音量でも心地よく聴けるのかもしれない、とも思いました。
まずはZ701でBHBSを聴き込んでみます。
他社製品買わず待って良かった!
PC用として使用してます。ニアフィールドSPとしては超おすすめです。バランスが良いので、個人的にはSWの必要性は感じません。出れば購入してしまう可能性大ですが… 今回初めて潰し塗装に挑戦しました。出来は80点ほど、過去製作したSPの塗装し直しに現在はハマっています。塗装セミナー動画 ハイCPです。続編期待しています。
読書机に置いたら、音が良すぎて本に集中できない!
音工房Zさんとのお付き合いは、Z701-OMMF4、Z505-TRENTO(サブ・ウーファー)に続いてこれ、という変な順番です。本当はZ800-FW168HRが本命でしたが、その前の腕試しにZ701を作り、OMMF4ユニットの実力と、音工房Zさんの設計・製造の素晴らしさに感心しました。
そこで、デスクトップのBose M3(Micro-Music-Monitor)に飽きてきたこともあり、ニアーフィールドスピーカーの更新を思い立ちました。Z701とは異なり、シングルユニットで、スーパーツィーターもないので、「お手並み拝見」のつもりで部品到着を待つ間、たまたま音工房Zさんで試聴会があり、Z600の実力を自分の耳で確認することができました。当日は3D構成のデモもありましたが、3Dウーファーを止めてもかなり下の方まで低音が出ていて、何よりも中高域の解像度、定位の良さが素晴らしく、Z600キットの到着が待ち遠しくなりました。
Z505-TRENTO(1本25キロ以上)を完成させた直後だったので、Z600はか弱そうに見えましたが、組み上げて塗装を施すと、かなりしっかりと、重量もあることがわかりました。簡単なエージングの後、試しにZ505につなげて、リスニングルームで鳴らしてみたところ、「本当にこの小さな箱からの音?」と戸惑うほどで、こういう使い方もアリかな?と思ったくらいです。
それから1ヶ月ほどエージングして、本来の読書机の上に納まり、Nobsound TA-21という、Bluetooth受信機能付きのデジタルアンプ(Amazonで¥4,980)をつなぎ、音源はiPod Touchに入れた室内楽中心の静かな曲という組み合わせで聴いています。一言レビューに書いたように、これでBGMを流しながら読書していると、「あれ、この曲、こんな音入っていたかな?」とか、「え?この定位、奥行きまでわかる」とか、音が気になり、ついつい音量を上げてしまいます。
スピーカー間隔60センチ、そこを底辺とする正三角形の頂点あたりのニアフィールドで聴くと、ヘッドフォンでは味わえない開放感の中で、箱庭のような音の世界が楽しめます。
想像してたとおりだった。
音工房の自作スピーカーはこれで9作目。バックロードホーンに比べると箱を組んで配線してはい出来上がりと、とても簡単お手軽だった。音出しが我慢できず、まだ塗装してません。今までは色んな塗り方をしてきたので今回は木目調塩ビを貼って仕上げようと思ってる。
さて音の方だが、これまでの物も大変安価で素晴らしかったのだが、どうしてもオーケストラの強奏するヴァイオリンの音色に不満があり、B&Wに勝るとも劣らずの真相を確かめるべく購入。写真のように職場にてオンキョーのスーパーウーファーSL-10と組み合わせて使用。アンプはソニーのAVアンプDA5500ESを2チャンネルで使用。TEACのDAC UD-H01 にMacBook ProからのUSB接続、Apple MusicとAmazonHDの二つのサブスクを利用して聴くのがメイン。時折CDも聞くが手軽さで前者ばかりになってる。
ヴァイオリンの音は自分の理想に一歩近づいた。がまだまだ時折解像度不足かヒステリックで潰れた音になるのはDACが安物のせいかも。女性ヴォーカルが実に心地よく音像は比較的大きく豊かで艶と色っぽさもしっかり出てくる。
柔らかめの音色で刺激は少なくハイハットも潰れたりしない。ファーガーソンのシャープなトランペットのハイトーンも幾分ソフトになる感じはある。スーパーウーファーはスイッチで55HZでクロスと言うことになってるが、つながりがよく、オーケストラもジャズも実に心地よい。とにかく音色が素晴らしい。この値段で高級スピーカーを味わえること間違いなし。因みにクラシックはAmazonをジャズはApple Musicを使用して聞いてる。あと上に乗ってるスーパーツィーターは結線されていません。
ワンルームはこれで十分
単身赴任のため、ワンルームで聴いております。狭い部屋ですので、そこそこのボリュームで聴くと、ボーカルはとても素直に響き、サックスは耳に優しく、ベースも意外にも良くうなり、満足しております。
明快、クッキリ した音場。
WindowsパソコンでCDとかAmazon musicとかで聞いています。power ampはそちらの記事に写真が見えたので、安価なELEGANTEというのをAmazonから買いました。この組み合わせで今まで使っていたBOSEをお払い箱にして、クラシック音楽を楽しんでいます。しっとりした味わいなどは期待できないが、ふくよかさを楽しみにスーパーウーファーを期待しています。
BHの欠点を克服しつつ分解能はB&Wと互角、強靭で生々しい再現性
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
試聴会はAudioマニアにとって興味深い長岡式BHとB&Wの比較視聴が出来るまたとな
い機会でした。また同席された方々の試聴ソースも参考となるものが多く、貴重な
な機会を提供してくださった音工房Z様に感謝いたします。
まずはリファレンスとしてB&W、低域の豊かなスケール感は断トツで、更に缶詰の
様な録音のソースでもワイドレンジなHiFiに聴かせる点は、さすがと言えます。し
かし、一発録りの生録の様なソースでは、D37やZ1000に比べるとベールを一枚被っ
た様に聴こえ、面白みに欠けます。
D37は中低域で膨らんだ共鳴音が耳につき、この帯域を土台としたソースでは、B&W
やZ1000にかなり差をつけられていました。しかしながら、小編成の室内楽やJAZZ、
女声は、B&Wより好ましく聴こえていました。古いSPでだいぶエージングが進んでい
るせいなのか、長岡BH形式の個性なのか判りませんが、BHBSのZ1000に比べると軽や
かに抜けた音の出方をしていたのが、印象的でした。小生は好きです。
Z1000はフルレンジSPシステムの活きの良い音の再現に加え、マルチウェイSPシス
テムに互角以上の分解能を有した再現能力を示し、オケとコーラスのffでも綺麗
に分解し、ppでも色褪せる事が有りませんでした。クラシックのライブ録音では
B&Wより生の雰囲気を再現して入る様に感じました。
ないものねだりかもしれないけれど
Z600-OMMF4について。
机の前は部屋に向いているのでデッドな空間です。
映画では爆発音や雷鳴がおとなしく、Adam Ben Ezraのベースの低音側2本の弦が存在感ないので、寂しいです。
PCスピーカー用のスーパーウーファー6月かと思ってましたが話が立ち消えたみたいですね。どうするか悩んでます。Z601を作って机の上に置くか、市販のスーパーウーファーを買うか。
工程について。
吸音材Bは工程7と8の間に貼り付け、工程8と9の間に塗装しました。過去の動画確認は必須ですね。いろいろ買い足しました。
色はスーパーツイーターキットにあわせて黒く塗装しました。
音は良好!〈でも購入は保留〉
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
◉スピーカー視聴会 2021/06/24
一言で「音は良好!でも購入は保留」
※型番等について思い違いがあるかもしれません。その際は、どうかご容赦ください。
下記の5台について試聴いたしました:
①Z1000-FE168SSHP〈16cm〉
②長岡鉄男氏設計のD-37〈16cm〉
③B&W 802 Nautirus〈20cm〉
④スピーカー Z701-Modena〈8cm〉
⑤Z1 Livorno〈13cm〉
比較した印象は次のとおり:
①迫力ある音圧とアタック感は十分。
②音圧とアタック感は①と同様だが、最初に説明があったとおり、経年劣化のため中低音がブォンブォンとビリつくため、コンボのモダンジャズを聴く分には十分かもしれないが、交響楽や室内楽には向かない。
③再生音は①に近いが、比較して聴くと中低音の広がりと残響音が断然ふくよかで、高音の伸びも艶やか。
④自宅のニアフィールドで聴く分には十分だが、①と比較するとボリュームを上げないと互角にはならない。口径が倍も違うとこれだけ変わるということを実感しました。
⑤見かけは①の半分しかないが、意外と互角に再生。
四人が持ち寄ったCDを各自10分で試聴した結果、③が1番、①が2番、⑤が3番と評価しました。
購入したいのはヤマヤマですが、現在製作途中のスピーカーが2組あるため、購入は保留いたします。どうか悪しからずご了承ください。
試聴楽曲は次のとおり:
〈村治佳織の『亡き王女のためのパバーヌ』ギターのとりわけ低音弦の響きが余韻をもっている。鈴木勲の ”BLOW Up! “ ベース音が目の前で弾いているかのように生々しく響く。CS&Nの “Guinevere” アコースティックギターと男性三声ハーモニー。
次の方〈ヴェルディ『レクイエム〜怒りの日』、ムソルグスキー『禿山の一夜』〉
その次の方〈ビッグバンドの『茶色の小瓶』『チャタヌガ・チューチュー』『ムーンライト・セレナーデ』〉
さすがの高級機でした
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
2021年6月25日Z1000-FE168SSHPの試聴会に参加させて頂き有難うございました。 私は、このような試聴会は初めてなのでいい経験になりました。
Z1000-FE168SSHPは大きな音で聞くと高音から低音まで音が前面に出て素晴らしいと思いました。低音も圧倒的でした。比較すると長岡先生のバックロードは音が少しおとなしく感じました。私はB&Wが最も気に入りました。音が前面には出てこないのですが、音に品があり全体が豊かな音で最も好きな音でした。
当たり前ですが音源により音は全く変わりますが、ドラムの音を大音量で聞くと本物の音のような素晴らしいを音になりますが、私が持ち込んだグールドのピアノの音は小音量にしたせいかよくなく、極端な言い方ですが自宅のスピーカーとそれほど変わらない印象でした。今回の試聴会は、初体験で非常に有意義でした。
ロック系の迫力◎です
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
6月24日、貴社の試聴会に4月に続いて2回目の参加をさせていただきました。
開発段階の製品で試聴会をやっていただける、一回に4人という少人数で、自身の持ち込みの音源で試聴できるという、貴重な体験です。お忙しい中で、こういう機会を用意いただいたことに感謝申し上げます。
今回、一時間に4名の試聴ということで、私以外の方がお持ちになった音源を聴かせていただいてのレポートから記述させていただきます。
一人目の方
ロック系の音源
まず、開発機168の低音のエネルギー感が非常に印象的です。インスト系は、この168、16㎝ユニットながら低音の迫力がある点、◎です。
女性Voは、168はちょっとかすれた感じになり、B&Wの方が艶っぽくてきれいです。
ただ、語尾がかすれるVoこそ、色っぽくて好き、という方も多いです。(好みの問題)
ただ、168は、私の好みから言わせていただくと、Voにインストの低音がかぶってしまうところがあり、ちょっと気になりました。
(あくまでも、短時間・少数の音源だけでの第一印象ですが・・・)
E・クラプトン
B&Wは、gとVoが、すっきりきれいに分離しているところが印象的でした。
大地真央の生録
B&Wは、Voがきれい。168は、Voにインストがかぶった感じになるところがあります。
(上記ロック系と同様)
二人目の方
R・カーター/The Man with the Bass
168迫力あり良、B&WちょっとJazzっぽくない寂しい音に感じたが、Poを上げるとB&Wは鳴り出した。(ボリュームがかなり低めの試聴で、日頃こういう聴き方をされているのかな、と思います。私は、Jazzライブに月1,2回行くので、いつもそのイメージでかなり大音量で鳴らしています。)
168は、ボリューム上げるとバックロードっぽくなるところがあり、私は締まっていて、しかしきちんと主張する低域が好きです。(表現が難しいですが・・・)
少し膨らませた低域の方が迫力があって好き、と感じる人もいると思います。(好みの問題)
四人目の方
三味線の音
168、悪くはないが若干おとなしく感じる。B&Wの方が、三味線の音がより三味線らしく、フォーカスもB&Wの方がいいかな、と感じた。
私のかけた音源について
ほぼ1週間、時間があったので、約50枚の候補を挙げて、自分の持っているスピーカー・アンプの組合せをテストし、どこをポイントに試聴するかを検討して、7枚準備してお伺いしました。
1.Jim Tomlinson/the gentle rain
トムリンソン、デビュー2枚目のCD、ボサノバ集。4曲でステイシー・ケントが参加。
”the gentle rain”は、S・ケントのVoの舌の動きがきちんと出るか、間奏のtsがいい感じでバランスするか、が私のチェック・ポイントです。
今回の試聴会の時間では無理な話ですが、曲によってそれぞれの楽器の場所(定位)が変わるところもチェック要です。
2.Jheena Lodwick/You Raise Me Up(JVC XRCD)
今回のような試聴会や友人のシステムを聴きに行くとき、私としては外せないCD。
ポイントにしているのは、
①ボーカルとバックのバランスがいいこと
Voのバックのインストは、インストとしての主張はしながらもVoを邪魔しない。
②口が見えるような、舌の動きがわかるようなカワイイボーカル
③前奏0:20~バックのbが、メロディーの後ろでキチンと鳴っていること
しかも締まっていて膨らみすぎないこと(きちんとフォーカスしているイメージ)
①②③とも、スピーカーやシステムにより、大きく鳴り方が違うところがチェック要です。
3.フランクのヴァイオリンソナタ(A.デュメイ、M.ピリス)
曲◎、演奏◎の定番中の定番CD。
響き・倍音感があること、特にvlnは、艶っぽい音が出るか。
自分が鳴って欲しい鳴り方をするかどうかですが、文字で表現するのは難しいです。
4.SOLVEIG SLETTAHJELL/My Heart Belongs to Daddy
曲は、Jazzの有名中の有名スタンダード。しかし、2001年ノルウェーのライブは、21世紀の現代音楽かと思うようなds・tp・bのクールなイントロ、これから何の曲がはじまるのか、と思ったら、”わたしの心はパパのもの”・・・意外性の極致
私にとっては、このクールな”何だろう”と思わせるイントロとシュレッタイェルのスローな語りかけるように唄うVoのバランスをチェックするトラック
新開発168を中心に試聴の印象
開発機は、低域をいかに出すか、という開発方針でエンクロージャにBHBSを採用されており、ロック系など、迫力のある鳴り方をしているところは◎です。逆に音源によっては、中低域がVoにかぶるように鳴ってしまうところがあって、少しチューニングで下を落とした方が私は好きです。(好みの問題だと思います。)
⇒スピーカーとしては、膨らみすぎないように下を落とし、エネルギー感を出したいときは、プリで出すのがいいのかな、と私は思います。
上記2.の00:20からのbは、膨らんで少し歪みっぽい鳴り方なので、締まった低音にしながら、量感のある鳴り方をしてほしいです。(表現が難しいですが・・・)
B&Wも私の好みからすると、このb音に関しては量感不足です。
クラシックは、開発機168、B&Wとも響き・倍音感、艶っぽさともに私の好みからすると不足です。アンプ(プリか?)、部屋の影響かもしれません。ごく短時間の試聴なので、もうちょっと聴かないと、とは思います。10分ではクラシックは無理がありますね。
試聴が、168とB&W中心で、あまり時間をかけて聴くことができなかったZ1-Livornoですが、小ぶりなサイズながら、バランスが良く、しっかりと中低域が再生され、いろいろな音源に対応できる良さを持っていると感じました。帯域はあまり欲張らず、バランスのいい設計をされているところがいいのでは、と思います。(重心は、低め)
次回、視聴会に参加出来たら、50年代のJAZZなども聴いてみたいと思います。
以上、失礼なことも書いてしまったかな、と思いますが・・・
非常に楽しい催しでした。
本当にありがとうございました。
【試作版】はパンチ力あり明るく高音が伸び低音もそこそこ。中音がいまいち出ていない。
【試作版 Z1000-FE168SSHP】
音工房Zのような箱作りに熱心な工房を訪ねるのは初めてであり、また試聴会も初めてであり、とても有意義な時間を過ごすことができました。スーパーツイータの視聴やネットワークの話も聞きたかったのですが時間がなく残念でした。学生時代にパイオニアの16cmフルレンジを大きな箱に入れて聞いていた頃が懐かしいです。ツイーターを自巻きコイル+コンデンサネットワークで繋いだのも懐かしい。箱で低音の出方が大きく変わることは知っていますが、ユニットの限界というのもあります。今回の単体FE 168SSHPはかなりの優れものと思います。それぞれ視聴した印象を述べますと、【試作版 Z1000-FE168SSHP】は、現代的というか若々しい明るい音、高音に伸びがあるのはツイーターのおかげか。低音もそこそこ出ているかなあという印象。長岡式BLHはユニットのヘタリか、パンチ力解像度に難あり。低音もボケていた。B&Wはホール間というか音の広がりというか、箱の構造によるものが大きいと思うがさすがだと感じた。ただし、Zに比べてメリハリが無いですね。古臭い印象です。3ユニットともに重低音はほとんど出ていなかったように思う。具体的には”CANTATE DOMINO”のパイプオルガンの30−40Hzは聞こえず、迫力もなかった。Zは中音をもう少し前に出して、スーパーウーハーを追加すれば完璧ではないかと思った。その分高価にはなるが市販品に比べればずっとお得では。