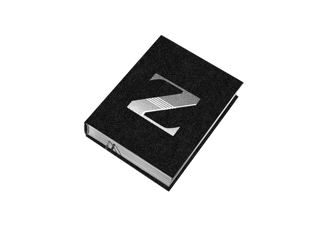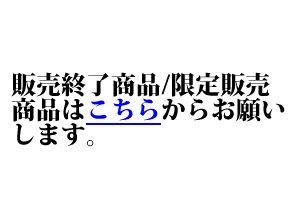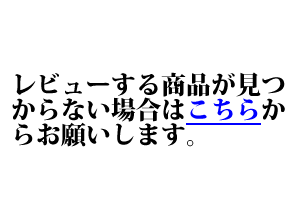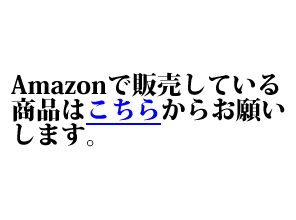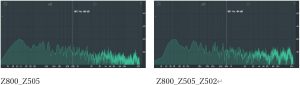レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
憧れのバックロードホーンを手に入れた!
セミリタイアしている66歳男性です。
バックロードホーンについては、20歳代の頃からあこがれていまして、いつかはバックロードホーンを手に入れてやるぞと心に秘めていました。
60歳での定年退職を機に、アンプとCDプレーヤーを買い換えてしばらく楽しんでいました。それまで聴いていたオンキョーMONITOR2000Xも悪くなかったのですが、何か新しいスピーカーをと探していたところ、インターネットで音工房Zに巡り合いました。
音工房Zからスピーカーを購入したことはなく、実機での音も聴かずにで、一抹の不安もありましたが、フォステックスの評判の限定ユニットを使用していること、また、インターネットで見る限り、音工房Zのスピーカーづくりは信頼できるとの思いで、私の懐事情では決して安くないZ1000-FE168SSHP+TA90A-SEの購入に至りました。
音工房Zからはエージングを1日6時間×2週間程度とのコメントがありましたが、私の場合は、1日1時間で2カ月ですので、まだ少しエージング不足かもしれません。
現時点での音ですが、MONITOR2000Xと比べて、締りのある低音や音がスッキリしたことを感じています。私は、ヴァイオリンが好きなのですが、より艶っぽくなったと思います。また、DSDとPCMの違いが今まで以上によくわかるようになりました。巷で言われるバックロードホーンの癖は、私には感じられません。どのスピーカーにも当てはまることでしょうが、音を出してから1時間程度のウォーミングアップとそこそこの音量が必要なようです。
現在は、スピーカーやリスニングの位置を変えて試行錯誤しているところです。私の評価ですが、☆4つにしました。なぜ、☆5つではないのかというと、エージング不足、セッティング不足によるものでしょうが、もっと生々しいスピード感溢れる音が聴ける筈だとの思いからです。これからも、このスピーカーの持っている性能を引き出すために、アンプをセパレートに買い換えようか、DACを変えてみようかなど、妄想が膨らんでいくばかりです。
ソース
・ホテルカリフォルニア/イーグルス 192kHz/24bit flac
・富嶽百景/音太鼓座 192kHz/24bit flac
・シューベルト ピアノ五重奏曲「ます」/アンネ=ゾフィー・ムター 96kHz/24bit flac
・ケルンコンサート/キース・ジャレット 192kHz/24bit flac
・ペールギュント/カラヤン ベルリンフィル SACD
オーディオ機器
・SACDプレーヤー:デノン DCD-SX11(DACとしても使用)
・プリメインアンプ:アキュフェーズ E-370
自分だけのコンサート会場ができました
Z701-FE168SSHPとT90A-SEとの組み合わせで6畳のミニコンサート会場ができました。
前のスピーカーでは、面白くなくて聞く事の無かったCDが素晴らしい音楽として響いております。棚に眠っていた宝を再発見しています。
6畳の小さな部屋で大音量も出せない環境ですが、全帯域にわたってバランスの良い自然な音が出ているのではないかと思います。
今思いつく印象は、
・スピーカーが鳴っている感じではなく、音楽が演奏されている感じです。
・全帯域に渡って、頑張って音を出している感じは全く無く、堂々として余裕がありながら、さりげなくすんなりときちんと全ての音を再生できいる感じです。ユニットもエンクロージャも大きいからでしょうか。
・余韻(残響)が非常に美しいです。
・太鼓やドラムの音がレスポンス良く響きを持って演奏されます。
・クラシック(大編成・小編成・独奏)・ジャズ・その他どのジャンルでも、しっかりと忠実に再生してくれる様です。その意味で、特に苦手というジャンルは無いかと思います。
・声の質感や楽器の音色については、好みに差があって評価が難しいですが、誇張や色付けが少なく、そのまま再生されている感じで、私は気に入っています。
ハイエンドの音というのはスピーカーだけでは成しえないので、たとえ数百万円のスピーカーでも、音楽を聴きたくならないスピーカーなら私には何の価値もありません。
粗末なオーディオ機器類で、これだけの音が再生できて、自分だけのミニコンサート会場ができたという事実をもって、大山様(音工房Z様)の理念はほぼ実現できているのではないかと思います。
あくまで私個人の印象ですが、このスピーカーは、
FOSTEX様の優秀なユニットと音工房Z様の多くの経験と高い技術力によってできた
「いろいろな音楽をもっと聴きたくなる貴重な良いスピーカー」だと思います。
これから長く使っていける傑作(銘機かも)と思います。
今後も良いスピーカーを作り続けてください、応援しております。
[機器]ひまじんの粗末なオーディオ機器類(色々と涙ぐましい工夫はしています)
[音源]CD・DVD・BD、クラシック・ジャズ・その他
真打ち!Z1000-FE168SSHP!
・Jazzライブ名盤、BILL EVANS TRIO、WALTS FOR DEBBY のMY FOOLISH HEART を聞いてみます。すると、演奏の開始とともに、会場にすっと引き込まれライブ演奏を楽しむことができます。これで十分と思えます。その理由を、私の見解でレポートします。まず、音が澄んでいます。こもった感じが全くありません。次に、極小音量まで明瞭です。そのため、楽器の余韻までスムーズで、会場内のざわめきもリアルに感じます。さらに、各楽器が分離し、しっかり定位します。周波数特性は、低音は引き締まり、高音は煩くなく、中音は出しゃばりません。以上の特徴から、ピアノ、ドラム、バス、さらに観客のざわめきが自然に響き、楽しむことができます。
・これらの音を楽しむため以下の準備をします。装置は部屋の中央で、スピーカとの距離は1.5m前後の比較的近距離での聴取です。まず、高域に影響を与えるサランネットは、カッコいいのですが取り外します。次に、音の指向性が強いので、リスナーは左右のスピーカーと正対し、左右の軸の交点付近のスイートスポットを探します。さらに、音量を上げすぎないようにして、聴覚の負担を減らします。迫力がないくらいの音量で良いと思います。あとは、少し部屋の照明を少し落として目を閉じれば、準備完了です。
・REBECCA Ⅳ、May be TomorrowのHot Spice を聞いてみます。こちらは、メリハリのきいたロックナッバーです。聴き所は、NOKKOの溌剌としたボーカルです。このボーカルを最初に聞いたとき、知っている声と微妙に違うな!と感じました。しかし、すぐに慣れてしまい気にならなくなりました。他のミュージシャンのソースでは、最初から違和感がない場合もあるので、相性もあるように思えます。ボーカルの再生音は、好き嫌いが分かれるかもしれません。
・以上をまとめると、Z1000-FE168SSHPは、ボーカルはソースとの相性があるものの、高解像度なユニットを、熟慮された箱に納め、バランス良い周波数応答を実現した、臨場感あふれるスピーカーといえます。そして、音質は真打ちレベルと思います。
・私は、気分により、またはソースにより、端正にまとまった音が聞きたくなるときがあります。この場合、Z800-FW168HRの出番です。設置は部屋の制約から、Z1000-FE168SSHPの上に置いています。そしてツィーターの高さを合わせるため、ウーハーを上側にしています。音は上方向から降ってきますので、少し背筋を伸ばして耳の位置を高くして聴きます。Z800-FW168HRは、各楽器やボーカルがうまくミックスされるので、安心して聴くことができます。
・最後に、スピーカーメーカーのFOSTEX、その性能をフルに引き出す箱メーカーの音工房Z、さらに様々な情報提供をいただく全てのオーディオ愛好家に、深く感謝します。おかげさまで、楽しい音楽ライフをおくることができています。ありがとうございます。
・使用機材‥AMP:DENON PMA-QSA11、CD player:DENON DCD-QSA1、Record player:DENON DP-57L、カートリッジ:DENON DL301Ⅱ、Z1000-FE168SSHP ツィーター:T90A-SE
Z501(V2)とスーパーツィーターキットを比較試聴してみて
1月19日にZ501(V2)が我が家に届きました。
スーパーツィーターは ”キット” を3年以上前から使用していますが、ほとんどの方のレビュー同様その効果は素晴らしく常に繋ぎっぱなしです。
Z501の購入は何度か検討したのですが同じユニットを使用していて価格が4倍ほど違うというところがネックでした。
今回は”期間限定商品”ということで思わずポチしてしまいました。
“限定”という言葉には弱いです。
早速「Z1-Livorno」と「自作JBL」に取り付けてのレビューです。
Z501の効果はもはや周知のことですので、今回は「Z501(V2)」と「キット」の音の違いを確認するのが目的です。
まずは外観から、
Z501は思ったより小さくて手に取ると愛着のわく可愛い出来で、ウォールナットの仕上げは大変美しく手間をかけた家具の趣です。
色合いも思ったより明るくて白木のエンクロージャーともよく合います。
付属の滑り止めパッドは、普段よく使用している「山本音響工芸のブチルゴムGS-8」より少し柔らかく粘着性があり、太めのコードを使用してもZ501がずれることは全くありません。
さて、音の方ですが、比較試聴しやすくするために写真の様にスピーカーセレクターを使用しました。
アマゾンで購入した”Felimoa”という安価な中国製のセレクターですが、同様の他社製品が「スピーカー端子のバネが飛んだ」とか「2〜3回の使用ですぐに壊れた」とか散々なレビューの多い中で、比較的好評な評価を得ている製品です。
今のところ健在で、いい仕事をしてくれていますがスピーカー端子の直径が3mmほどしかなくかなり細めのコードしか使えないのが残念です。
このセレクターに「Z501」と「キット」を繋ぎ、瞬時に切り替えて違いを確かめることにしました。
キットのコンデンサーも1.0μFに合わせてあります。
まずはZ501(V2)を繋いでいつものYumingから、
「ただわけもなく」は冒頭のギターの響きがどう聴こえるかがポイントですが、やはりZ501のホーン効果でしょうか、ピンポイントで前に出てくる感じで音がまとまってくる分、音圧も少し高くなったように聴こえます。
Z1-Livorno」+ 「キット」 では今ひとつ満足できなかったYumingの歌声もZ501 を繋ぐことで細かいニュアンスが浮かび上がり「キット」より表情が豊かになったように聴こえます。
Eddie Higgins Trioの「懐かしのストックホルム」でもZ501の方がシンバルのハイハットがよりリアルに聴こえ、ピアノも艶っぽくなりました。
Z501 のホーン効果は絶大なりと感じたのですが、
小澤征爾・サイトウキネンのバッハの “Air” を聴いた瞬間「んっ?」となりました。
キットの方が高域がフワーッと部屋に広がりまさに「天上の音楽」を聴いている感があります。
バッハで高域が突き刺さってきては興醒めです。
バッハやモーツァルトを楽しむには「キット」の方が相性がいいこともあるようです。
何時間も試聴して結局のところ、Z501メインで、どちらも「あり」かなというのが私の結論です。
何を聴くかによって使い分けを楽しむということでしょうか。
一つ確かなことはキットを聴いて「いいな」と感じた人は、Z501 も必聴だということです。
もっと早く読むべきでした!
昨年11月に自作SPを完成させたばかりでした。(添付画参照下さい)
ターミナルは音工房Zさんの商品を使っています。
もっと早くこの大百科事典を読むべきでした。
たくさんの情報を頂きましたので、次のブックシェルフスピーカー制作の準備を始めます✋
素晴らしい!
こんなに詳細なレポートとは思ってもいませんでした。とても感激しました。有難うございます。
200時間エージング後のZ1-Livornoを聴いてみて 《その2》
前回 製作編をレビューしましたが今回は肝心の音の方です。
8月末にエージングを始める前に2〜3時間聴いてみたのですが、我が家の自作7台目のJBLとの比較には厳しいものがありました。
自作のJBLは約60リッターのバスレフでユニットはJBL2115B (20cmフルレンジ、インピーダンス16Ω) を2台パラレルで繋ぎ、ネットワーク3105でツィッター2405を鳴らしています。
エージング30年以上の (ちょっと長過ぎかも….) 年季の入ったベテランです。
10年以上前に広島の「サウンドデン」でエッジを全て天然セーム革に張り替え若返りを図っています。
エッジをウレタンからセーム革に張り替えたことでクラシックもある程度聴けるようになりました。 (それはJBLらしさが無くなったということか……)
まず女性ボーカルで綾戸智絵の「New York State of Mind」とYumingの「スラバヤ通りの妹へ」をかけてみたのですが、
JBLの方は何色も色を重ねた油絵のような深みがあるのに対してZ1-Livornoはポスターカラー一色で描いた青空のようなイメージでした。
流石にエージング30年と0時間ではハンデがあり過ぎました。
が、しかしです。 念の為と思い小編成の弦楽アンサンブル (イムジチのモーツァルトのディベルティメントK.136ほか)をかけた瞬間、私はその場に釘付けになってしまいました。
なんと清涼感のある”弦”でしょうか。
瑞々しい新緑の風が吹き抜けて行くイメージです。
このさわやかさは私のJBLにはありません。 ちょっと落ち込みました。
Z1-Livornoを漢字一文字で表すと「爽」でしょうか。 (清水寺の管長か!!)
この瞬間、大山さんが目指していたZ1-Livornoの音作りのコンセプトがはっきり見えた気がしました。
さて、200時間エージング後のZ1-Livornoはどう変貌してくれたのか。
十分に暖めたAccuphaseに繋いでみました。
まずはボーカルから。
エージング前の単調な感じからかなり変化していると期待したのですが、まだ十分ではなかったようです。
JBLで聴くとYumingの微笑みながら唄う口元が見えるのですが、Z1-LivornoではYumingの顔が見えません。
やはり単調な、少し距離を置いた歌声になります。
またバックの演奏の中にYumingが沈み込んでしまいます。
このサイズのエンクロージャーとしては信じられないほど低音がよく出ていて感動ものなのですが、私には少し低温が鳴りすぎの感じがしました。
そこで以前、スピーカースタンドZ102のレビューでも書きましたがaudio-technicaのAT6099をZ1-LivornoとZ102の間に
挟んでみました。
これはかなり効果がありました。
まず私には出過ぎと感じていた低音が少しおとなしくなり、バック演奏に沈み込んでいたYumingのボーカルがフッと浮き上がり存在感がグッと出てきました。
かなりバランスが取れてきた感じはしますが、やはりボーカルの微妙なニュアンスがもう一歩です。
New York Trioの「Blues in The Night」の ブラシワークなどの高域にも不満が残ります。
いきなり厳しい評価になってしまいましたが、この後聴いたモーツァルトやバッハでは水を得た魚のように実に生き生きとした表情を聴かせてくれました。
鈴木秀美のチェロの響きは感動的です。Z1-Livornoはスピーカーの存在を忘れさせて音楽に没頭させてくれます。
やはりZ1-Livornoの真骨頂は弦楽アンサンブルや室内楽、器楽曲にあると思います。
エージング前に感じた「疾走する爽やかさ」は健在です。
もうモーツァルトやバッハはZ1-Livornoなしでは聴けません。
非常に完成度が高く、一生使い続けたくなるバスレフですのでもう少し高域の表現が豊かになるといいのですが…..
ちょうどZ501(V2)ウォールナット仕様が届いたので、コンデンサーも色々変えて試してみたいと思います。
少しでも高域の表情が豊かになりますように……..
このわずか10リッターほどのコンパクトなエンクロージャーからは想像もできないような豊かな音楽が流れ出すのは実に気持ちが良いです。
大山さんのことですから必ず「Z1-Livorno – II」を考えていると思いますので是非ともツィーターのグレードアップをお願いしたいと思います。
最高です。
御社の自作スピーカー(8cmフルレンジバックロードホーン)を聞く機会があり、フルレンジスピーカーが良いのではとぼんやり知識としてあったのが想像を超えていました。
カフェで聞いたのですが機材はCDプレーヤーSONY XA50ES アンプは管球アンプ(メーカー不明)
ソースはJAZZ(トリオ)でした。ウッドベースの弦の弾き音、胴鳴りの再生音に感動しました。
大満足のスピーカーです。
スパースワン+FE108SOLをメインに使用していました、以前二子玉川にあったFOSTEXのショ-ル-ムでFE168NSの視聴会があり、確かに16センチは迫力があり良いとおもっていましたが、金銭的な面とスパ-スワンを導入して日が浅かったので断念していました。
その後音工房Z様の大百科事典を知り、その内容とメルマガ読み共感し興味がわいていました。
ユニットFE168SS-HP発表後、ブログのZ1000-FE168SSHP制作過程を見ていると購入意欲が抑えらなくなり購入しました。
同時発売のT90A-SEをつけての感想です。
フルオケースロラを聴くと、まずあたかも会場が広くなっようなです、ぞれの楽器の音色が明確になり楽器の位置が見えるような感じで余韻の音が消えていく最後まできちんと聴こえ感激ものです。
芸能山城組の輪廻交響楽、AKIRAを聴くと、これまた驚きの連続で音の立ち上がりも早く低音も凄まじく今まで聞こえなかった音も聴こえます、リスナーの周囲をぐるぐる回るコーラスのところもスパースワンよりぐるぐる回ります。
井筒香奈江さん、ウィリアムス浩子さん等の女性ボーカルを聴くと、楽器とボーカルがハッキと分かれ聴きごたえあります。(ただし曲によってはボーカルが広がり過ぎると感じる時もあり、そのときはFE103A搭載の7LエンクロージャーBOXで聴きます。)
上記感想はZ1000-FE168SSHPが出す音は癖がなく、広範囲全域にフラットな特性によるものと思います。
よくバックロードホーンは特有の癖があると言われて、今までは具体的にどのようなことか?分かりませんでしたが、スパースワンと聴き比べて今は分かるようになりました。
大変良い買い物をしたと喜んでいます。
メイン使用機材;DENON PMA-2500NE,DNP-2500NE IO DATA Sundgenic
落ち着いた高音、輪郭がはっきりした中低音、期待を大きく上回る製品です
ONTOMOオリジナルのボックス(出版物なのでサイズの制約はあります)と比べ、高音は落ち着きが増し中低音は強固でしっかりした音が出ます。 特に低音の質感は期待以上。 スーパーツィーターを追加してエージング中です。 今後どうなるか楽しみです。 試聴機器:プリメインはMusical Fidelity A3,5、DACはOPPO SONICA、ストレージはIOデータHDL-RA3HGです。 LPはこれからチェックします。
本家が作ったものを是非手に入れたい、そしてそれに負けない自作をしたい、と思った。
まだ、自分が使っている工具から使えるものをピックアップして不足分を揃える段階です、工具から揃え直しです。
完成品のスピーカーの購入方法を教えてください
弦が美しい
・初めてスピーカーを自作しました。
→自作と言っても音工房様のキットですが。。
・でも小生にとっては全く初めてなので色々工夫して作成しました。
・仕上げは木目の塩ビシートを貼りました。
→スピーカーらしく綺麗になりました。
・アンプはPMA2500NE
・比較のスピーカーは同じく音工房様のZ800完成品+trents完成品
・第一印象は、バイオリンがとても綺麗。
・今まで聞いたことのないとろけるような弦の響きでした。
・きっとスーパーツイーターの影響が多分にあるのかもしれません。
・バイオリンのソロ、コンチェルト等聞きましたが、やはり弦が綺麗です。
・またバロックを聞くとチェンバロが今までになく生々しくハッキリと聞こえます。
・ピアノも綺麗です。
・高温、中温が美しいです。
・低温はZ800+trentsにはやはり負けます。
→低温はZ800+trentsではゴーンと響くのがガーンと響く感じです。
・オーケストラの分離がいいです。
・ダフニスとクロエを聞くと細かく音が分離して聞こえます。
→冒頭の全奏の部分が細かく分かれて聞こえます。Z800より上のような気がします。。
・やはりネットワーク無しの直結の威力はスゴイ。。。
・これから聞きこんで音がどう変化していくか、楽しみです。
濁りのない素直な音で、かつしっかりとした音
ヒュー・ヒュー!!!!!(指笛)
貴社HP上の試聴動画で、Z800とZ1とを何回も聴き比べました。色んなソースが聴けますが、その中の雨音が決め手になりました。最初に聞いた時に、その生々しさにゾクッとしました。後日何度聴いても、角の取れた、かと言ってボケてない、小生好みの音です。
そこで、Z1-Livornoの、チューニングされた完成品を購入しました。休日は、一日中スピーカーの前に座ってます。大山様の姿勢というか執念に感謝・感謝です!!!
今まで購入したり、自作したりした中で一番良い音を出す。
CDプレイヤーはSONY製DVP-SR20、アンプは音の工房製 真空管アンプSK-60(自作)SPは御社製Z601-OMOF101
スーパーツィータZ502の効果を実感
スーパーツイーターの記事を読んでいるうちに欲しくなり、Z501にするのか、Z502にするかで悩みました。
Z501でも十分と考えておりましたが、Z502のリボンツイーターの方が大きいので単純に聴取する範囲も広くできるだろうと勝手に考えて、Z502を選択しました。
高音が聞きづらくなっている年寄りでも違いが分かるかが一番の懸念点です。
音工房さんの開発経緯を読むと「音の変化は超高域だけではありません。」とあります。本当かいなと半信半疑です。まずは聞いてみなくてはと、音を出して確かに違うなということが分かりました。年寄りの耳でも聞き分けられてホッとしました。
Z800-FW168HRとZ505の音でも十分に気に入っていたのですが、Z502を追加することで全体がふくよかになり、表現に豊かさが増した感じになります。記憶している音に近づいてきている気がしています。
たとえて言うなれば、これまでは絹のような肌触りの音を聞いていましたが、ビロードのような肌触りの音になったのではないかと思います。上手なたとえとはいいがたいと思います。
スーパーツイーターの効果ってこんなにあるのだと実感しました。「超高域だけが改善されるだけだろう。」という認識が一掃されました。
なお、聴取領域が拡大するであろうということで、横置きで使っています。
記事の中で周波数特性が広域や低域でも変化しているというので自分でも測定してみました。高価な機器は買えませんので、iPhoneのアプリを使って測定しましたので、信頼性は低いかと思います。PCからピンクノイズを発生させ、アプリで測定したデータを見ると確かに高域に変化があります。数回測定してみても同じような結果となり、測定した波形を見るだけでZ502の有無が分かります。記事の内容はなるほどと納得させられました。2kより高域に変化が見られます。残念ながら、低域は和室だからか、測定に問題があるのか波形からは明確な変化が分かりませんでした。
音工房さんの記事はきちんとお調べになって、書かれているのが分かり、好感が持てます。
もう、Z502を切り離して聞くことはありません。
どこで歌っているかが分かる定位感
和室で聞いており、吸音がすごいのだろうと思っており、Z103を購入しました。Z103 Aを2セットとZ103 Bを2セットです。
Z103 Aをスピーカーの背面と横に、Z103 Bを聴取位置に正対するようにスピーカーの横に設置しました。もちろん大山さんのレポートを参考にしました。(写真にはスピーカーの背面に設置したパネルはわずかしか写っておりません。)
Z103を設置して一番のおおきな違いは定位感が増したことです。ヴォーカルがどこに立って歌っているのか生々しくわかります。オーケストラの楽器位置が手に取るようにわかりやすくなりました。音量も若干大きくなったのではないか感じました。気のせいかもしれません。
いままでは和室で音が吸収されていて、定位感があいまいになっていたのではないかと思います。
とにかく、音響パネルの効果を実感した次第です。
当初はパネルの有無の違いを確かめようかと思いましたが、撤去と設置が思いのほか大変で時間がかかり、あれ、こうだったかなとか記憶があいまいになり、諦めました。
組み立てはZ800の時に購入したクランプを長ナットと長ねじを追加して、締め付けられる範囲を広げて使用しました。
Z103 Aは蝶番で連結してスピーカー背面と横に設置して、Z103 Bは木枠を自作し、足をつけて自立するようにしました。
母体は硬いほうが良いか
こんばんは、色々見ていますが、この501は支えるものが堅いほうが音が出るように思います。ネジ止めですが受けるナットがあったほうが固定できます。私は社外品のセットで使っています。スピーカーは同じですが、入れ物は社外品これはブラパーツで全体シリコンですが、ボルトは前と後ろで締めており音は前に出やすいと思います。木材よりは固定がゆるく、このれは吸収少なくなると思います。
好バランスのバックロード決定版
機材:LINN SELEKT DSM-KA(プリメインアンプ内蔵),NAS(QNAP HS-210 + SSD)
ソース:ビリー・アイリッシュ『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』(FLAC 44.1kHz/24bit)
7年前からLINNのネットワークプレーヤーを中心に構成しています。その際CDプレーヤーを処分したので手持ちのCDは全てNASへリッピングしました。
スピーカーは,もともとバックロードホーンに憧れがあり,10年間Z700-DCUF122Wを愛用していたのですが,この度,限定販売でZ1000が出ると聞き,ラストチャンスだと思い即買いしました。
先日,大山さんのメルマガとブログに触発されて上記のアルバムを入手しました。
このアルバムには,押し出してくるような音圧や隠し味的に入っている重低音など多彩な音が入っていて,ヴォリュームを上げると家鳴震動しそうなほど(笑)ですが,本機は難なく再生しています。それでいて高音は刺激的にならず,ヴォーカルや演奏の輪郭も綺麗で,実にバランスがいいと感じました。
その他の音源もこれまで種々聴いてきて,ほぼ期待どおりの音が出ていると思います。
ただし,質がイマイチの音源(リマスターされる前のCDなど)は音の”悪さ”がかなり分かってしまうので,どんどん買い替えたくなるのが難点でしょうか(笑)。
音出ししてから一ヶ月半経ちますが,十分に満足しています。
ルックスもお気に入りです。
この次買うSPがない!最高のコスパ。
アンプは
①デジタル
②半導体
③真空管の3つ
切り換えられるSPは
①JBL 4312SX
②YAMAHA MS10-Pro
③Victor 安い方のウッドコーン
④BOSE AM -5 シリーズⅢ
⑤Z 700-FE 88Sol
⑥JBL Control3Pro
それぞれにスピーカーの特徴があって、ソースによって使い分けていますが、減らすとして最後まで持っているのはコレだと思います。
以前よりこのライバル器「B&W」が欲しくて、とりあえず同じブランドのMC -1を中古で買って、自分を慰めていましたが「いまいち」の感がありました。
開発秘話の中、ブラインドテストでB&Wのアレと引けをとらないと書かれてあったので、買い替え。仮組み、音出しから、他を圧倒する鳴りっぷりに感動。
やりたかった塗装をして、逆さまにセットしてしばらくこのままエージングしてみます。
本当に凄いスピーカーキットです。
いつか道内のオーディオ機器販売店のマスターに、試聴してもらって、値付けをしてもらおうと思っています。
繊細で綺麗な癖のない音
【Z601-OMOF101】
書いているうちに随分長くなってしまいました。前半がZ601-OMOF101、後半がZ800-FW168Hについてですので興味のない方は読み飛ばして下さい。尚、他の方のレビューを読んでしまうと自信がなくなって書けなくなりますので、恥を承知で感じたままを書き連ねました。おかしいだろ!とのご意見がございましても素人の感想と受け流してもらえると幸いです。
音工房Zさんを知ったのは去年の夏頃だったと思います。久しぶりにオーディオに復帰しネットで情報収集していた時、例のキャッチコピーに目が留まりました。丁度「Z701-OMMF4」の開発ブログが始まり、特別な興味はありませんでしたがコロナ下で外出も減り気分転換を兼ねて試聴会に申し込みました。MOOK本付録スピーカーの存在は以前から本屋で時々見かけましたが、所詮オマケでPCスピーカーの様なチープな音しかしないだろうと勝手に思い込んでいました。しかし、ブログの記事を読むとなんか様子が違う実際に聴いてみる価値は大であると確信するようになりました。当日のショックは大変な物でした。若いころ作ったテクニクスの10㎝自作スピーカー(メーカー推奨仕様)はナローレンジで特に低音が出ないものでしたので、現代のユニットの進歩には目を見張るものがあり、箱だけで4万円ユニットと合わせて6万円と(私には)高額でしたが我慢しきれず購入してしまいました。
前置きが長くなりましたがそんな経緯で音工房Zのファンになった私は今回懲りずに4回目の試聴会にお邪魔してきました。去年の限定モデルが最高と思っていた私は最初は行かないつもりでしたが、大山さんの誘い文句とブラインドテストの誘惑に負けて参加申し込みをしてしまいました。
今回のお題は「Z601-OMOF101(12Lダブルバスレフ)とONKYO設計者が設計したエンクロージャー(3.8Lシングルバスレフ)の聞き比べ」と、「Z800-FW168HR(V2.7)のツィーターのクロスが6dB/octの参考仕様と12dB/octの製品仕様とを10曲づつ20回聴きブラインドテストで聞き分けができるか」の2点でした。
Z601-OMOF101やOM-OF101ユニットについてはブログやネットの情報を参照頂くとして聴き比べのみについて個人的な感想を書きます。最初に感じたのはバスレフ方式の違いもさることながら、3.8Lと12Lの容量が原因と思われる音の違いです。Z601-OMOF101はしっかり低域まで出ていて音量を上げても煩くなく勿論、音の潰れなどは感じられませんでした。「繊細で綺麗な癖のない音」と云うのが私の印象で余分な音は出さないオールマイティーな性格で、どんな音楽でも過不足なく聴けると思います。一方ONKYO設計者が設計の方は中音域(ボーカル)等はZ601-OMOF101と同傾向の音ですが、低域の伸びが足らず音量を上げると音が潰れるような印象があります。因みに、前出の私の10㎝自作スピーカーは8.2LですがこれにOM-OF101を入れてみると、只ポン付けしただけですので音質云々は別としてONKYOさんのより低域は伸びてますし、音量を上げても音の潰れは感じません。また、ONTOMOの専用箱は7Lぐらいだったはずです。(但し、サイドパネルが5.5mmと薄く設計者は響きをプラスしたとのことですが私は聴いたことが無いので?と思っています。)大山さんもブログで拝見する限り16Lに良い印象を持たれたようですので、方式に依らず最低7L以上は必要と思います。(私なら選びませんが)小型のエンクロージャーはニアフィールドで小音量で使用するか、サブウーファーと組み合わせるなら有りかもしれません。
ダブルバスレフとシングルバスレフについては同容積の聞き比べをしないと判断しかねますが、大山さんのブログを拝見する限りダブルバスレフに分があると思います。ブログを見ればお分かりになると思いますが、Z601-OMOF101以上のものを個人で作るのは現実的ではなくZ601-OMOF101を素直に購入するべきです。ご自分で設計するなら大き目のシングルバスレフでしょう。限定品であと1日しかありませので興味のある方は後悔の無いように買っといたほうがいいにでは。
蛇足ですがONKYOさんについて触れさせて頂きます。このユニットの発売の少し前にONKYOの上場廃止のニュースが駆け巡りました。私はOMOF101が本屋さんに並ばないので不思議に思いネットで調べて不覚にも初めてこの情報を知りました。私は幸い定価で購入することができましたが、現在は3千円以上のプレミアがついています。大山さんには怒られそうですが、FOSTEXなどに比べて元々の設定価格が安いと思います。過去の雑誌の価格からの流れか、ONKYOが宣伝効果を狙って低い販売価格に承諾したかは分かりませんが。定価1万円以上でも十分売れそうな製品だと思います。今の価格なら買いだと思います。何故ならもしかするともう手に入らなくなるかもしれないからです。
恥ずかしながら私も某K社の元社員で債務超過に陥った会社がどの様な経緯を辿るかを経験しました。会社が傾くと儲からない部署は問答無用で切り捨てられ儲かる可能性のある部署のみが残されます。銀行からもなかなか資金を借りられなくなります。MOOK本の再発売をするのはかなりハードルが高いと思います。ONKYOはOEMで車載用スピーカーの供給は続けるようですが、市販オーディオはPioneer共々アメリカの会社に売られた模様で国内営業はONKYOがこれまでどうり担当するようですが先行きは分かりません。去年までのマークオーディオの様にカタログモデルとして販売するということは多分無理だと思います。
さて、話が暗くなりましたがもう一つのお題Z800-FW168HR(V2.7)のツィーターのクロスが6dB/octの参考仕様と12dB/octの製品仕様とを10曲づつ20回聴きブラインドテストで聞き分けができるか」ですが、正直違いを感じられなかったらどうしようというのが本音というか不安でした。結論から言うと差はほぼ分かりました。テストは勿論どちらのスピーカーが鳴っているのかは分かりませんし、6dB(1番)と12dB(2番)の鳴らす順番もランダムです。前もって聞いたりもしないぶっつけ本番的なテストです。但し、6dB(1番)と12dB(2番)を当てるのではなく、1回目のスピーカーと2回目のどちらのスピーカが「好き」か選ぶという形式です。私の結果は6dB(1番)が3回と12dB(2番)が7回で圧倒的に12dB(2番)の方が「好き」を選んでいました。更に6dB(1番)の3回の内の2回は、6dB(1番)ではなく12dB(2番)が鳴っているように思えるが音的にはこちらが「好き」と感じたため、あえて6dB(1番)を選択しました。1曲のみ全くどちらかわかりませんでした。つまり9曲は聞き分けられたことになります。これは私の耳が良いと言いたい訳ではなく、誰でもこれに近い結果になるぐらい差は分かるということを言いたかったのです。
では私の感じた違いは何かというと、ボーカル等のセンターの定位と複数楽器の等の広がり感の差です。製品仕様の12dB/octはきっちり定位しボーカルはぼやけることなく人の口から発せられたように声を感じます。広がり感は少なめですがサイドの楽器までボヤケたりせず直接音が中心に感じました。一方6dBの方は前に張り出すような感じで音の広がり感がありオーケストラなどの大箱物では迫力が増した感じでした。半面ソロボーカルや小編成の楽曲では口が大き目になり定位も少しフワッとした印象でした。音質はほぼ同じと言っていい印象ですので好みや曲で変えてもいいレベルだと思いました。自宅に2セット並べて曲ごとに切り替えるなんて贅沢ができれば最高ですね。購入された方は是非両方試すことをお勧めします。尚、今回のマイナーチェンジでバスレフポートがテーパータイプに変更され更にバスレフポートの影響を軽減する改良がされているそうです。12月からユニットの値上げでZ800-FW168HRも値上げになるとのこと、木材も値上げになるとのことですので更に値上げになると益々手が届かなくなってしまいます。CPの高いZ1-Livornoを買うことも考えていましたが、今回の試聴でZ800-FW168Hがやはりほしくなってしましました。