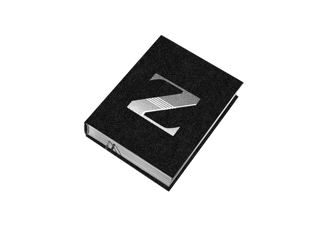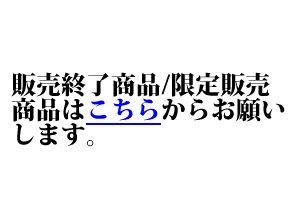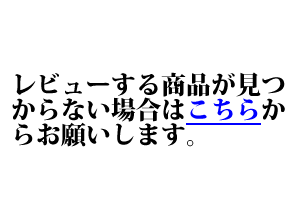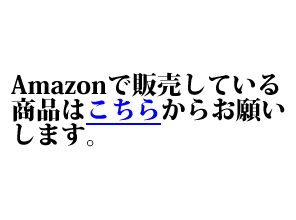レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
期待以上の良い音でした。
10年以上前に買ったシャープの1bitオーディオのミニコンポにZ702-Modenaを接続したところ、驚く様な澄み切った音が出ました。低音も十分に出ています。但し、低音の一部の周波数が少し強調されている様な印象を受けました。
スペシャルな重低音体験出来ました。
【Z508-Woofer1400】
10月21日 Z508-Woofer1400 30センチ38センチウ-ファ-試聴会
始まりの38センチでデモ音源が鳴った瞬間びっくりしました、ここでの試聴会で今まで聞いた事がない音で、重低音が素晴らしく中音域もはぎれの良い音が飛び出してきて、1曲目のパイプオルガンは地響きをも感じました。
音展 東京国際フォーラムのJBLブースで聴いた音を思い出しました。(1本100万越えのスピーカーでしたので、音工房Z様のはコストパフォーマンスは抜群ですね。)
中音域のはぎれの良いのは、ホーン型の特徴でしょうか?気持ちの良い音です。
今回のスピーカーは、ウーファー以外は同じでしたが、38センチの方が低域は当然としても、不思議と高音域の伸び中音域もよりハッキリと聞こえました。
では、38センチの方が好みかといわれると,反対で30センチの方が好みに合いました。
38センチは曲を選ぶようで、パイプオルガンやスローテンポ寄りの楽曲は良いのですが、クラッシックでもハイテンポ寄りになると低域の立ち上がりと音離れが若干遅くもたつきを感じました。
その点30センチの方が、重低音の迫力は劣りますが、音の立ち上がりと音離れが良く、どんな楽曲でもフィットするようで聴きやすかったです。
自宅では16センチのフルレンジ バックロードホーン(Z1000-FE168SSHP)を使用していますが、持ち込んだCDを聞いた時も、こんなにも重低音が含まれていたのか!!と驚きました、まさにスペシャルな体験でした。
自宅に戻り再度CD聞いてみましたが、試聴会で聴いた重低音とは違い、あっさりとしていて少し残念です。
5年間はバフル、背板セミオーダーも可能との事、とても他のメーカーではそこまで対応できません、さすがです。
今回も楽しい試聴会ありがとうございました。
ホーンドライバーの音色の再現性を感じました。
【Z508-Woofer1400】
久し振りに音工房Z様の試聴会に参加してきました。
高級なスピーカーに採用されているウッドホーンタイプのスピーカーの音を聴いたことなかったのですが結果非常に良い体験ができました。
いつものように試聴用の曲が流れた瞬間に音の情報量と自然な音色に感心しました。
その後自分の普段聴いている音源を聴き比べしましたがその曲のジャンルによって38センチのペーパーコーンのゆったりを包み込むような音色
と30センチの金属振動板のアタックの良い音色とそれぞれ得手不得手があるように感じました。
30センチウーハーのほうが能率が低かったこともあり少し低音に物足りなさも感じたのであのボックスであれば2発にしてポートも前に持って
きたらよいかもと思っているうちに視聴時間が過ぎておりました。
聴き比べる二つのスピーカーはウーハーの大きさと振動板の違い以外はネットワークやホーンドライバー、
スーパーツイーターに至るところまで全て一緒とのことでしたが低音は元より中高音から上の領域に至るまで全く別のスピーカーに感じました。
また聴いたことはありませんがJBLなどは38センチのウーハーを直結(フルレンジ)で使い
ドライバーとツィーターのみコンデンサーでローカットしボリュームでレベル調整しているものを多いようですので
そういったネットワークでも聴いてみたいです。
ベンチマークがJBLS9800とのことでしたので今回のスピーカーはまだウーハーの選定やボックスの作りなど試作の域を超えてないように感じましたが
大山様のことなので近いうちにこれが完成品というホーンドライバーユニットのスピーカーをお披露目してくれると期待します。
完成した暁にはJBLS9800とのガチンコのブラインドテストの試聴会を開催して欲しいです。
低音が無理なくでている38㎝の勝ち。(38㎝ VS 30㎝)
【Z508-Woofer1400】
今回の視聴会は収穫の多い会でした。
前回の視聴会では迷うことなく30センチに軍配を上げました。
今回は、音工房Zさんが用意していただいたソース、他の参加者方々のソースそして私のソースを全て聴いてみた結果では38㎝の方がよかったと感じることが多かったです。重低音にフォーカスすると、無理なく包み込まれるように出ているのが38㎝、30センチの方はやや無理して出しているような感じを受けました。聴きなれている私のソースでは、弦楽合奏では38㎝の圧勝、ピアノトリオ+ボーカルでは小差で38㎝の勝、J-popのアカペラ部分では30センチの圧勝と判断しました。
なぜそうなったのか私なりに考えてみますと、重低音が含まれているクラシック系ソースでは38㎝に軍配が上がり、重低音が含まれていない女性アカペラでは38㎝ウーファーのメリットよりもデメリットが出てきてしまったのかなと思いました。38㎝ウーファーには1000㎐以上を受け持たせるのは少し無理があるのかもしれません。その意味では38㎝ウーファーが本領を発揮するのは2インチドライバーとの組み合わせなのかなぁと勝手に想像しています。
さて、現在我が家には自作ボックスに入れた38㎝ウーファー(メインシステム)と以前購入した28㎝ウーファー(ユニット単体)があります。当初は28㎝用と考えていたのですが、今回の箱の出来が素晴らしいので、メインシステムの自作ボックスの代わりとするのか、28㎝用とするのか、それとも以前公開していただいた70リットルを28㎝用として自作するのか、この1週間悩みたいと思います。
自然な中低域の38cmウーファーと低域を頑張った30㎝
【Z508-Woofer1400】
まず気が付いた点は、38㎝ウーファーの自然な中低域です。ローエンドは十分伸びているもののうるさい低域ではなくグランカッサなどの歯切れはいいと感じました。
一方、30㎝ウーファーは厚みのある低温で艶っぽさがあるものの、低域の音程により音量に変化があるのが少し気になりました。その低域の歯切れは改善してほしいところです。具体的には火の鳥の冒頭のグランカッサでは細かい連打が聞き取りにくかったです。
ほかに女性ヴォーカルのリアルさにその差が大きく出ていました。
38㎝は目の前で歌っているように聞こえたものの、30㎝では数メートル離れたところで歌っているように聞こえました。
30㎝ウーファーと140Lのエンクロージャをうまく組み合わせるには、バスレフダクトを試聴時の2本から1本に減らすとか、さらには密閉箱で素直にローエンドを伸ばすなどの今後の可能性があるように思えました。
コスパ抜群
以下の構成でのレビューです。
・アンプ パイオニア A-70
・プレーヤー マランツ SACD30n
主ソースは、CD(Eagles ホテル・カリフォルニア)+HEOS音源、です。
NS1000M+【Z】パッシプサブウーファー+FOSTEX T90A の構成も並行して使っていますが、それより全体的にパワフルで繊細な音を出していると思います。
ただ、個人的な欲をいうと、もう少しメリハリのある重低音が欲しいところです。
そこで、Z505-Trentoを追加購入しようと思ったのですが、品切れ状態で購入できません。
Z505-Trentoにマッチしたサブウーファーの提供予定があれば、教えてください。
サブウーファーが不要になりました。
Z700-FE108solのエージングが進んだのでレビューします。
ダボ、ホゾ溝のおかげで以前のZ701-FE103solと比べると、かなり簡単に組み立てが出来ました。
木造12畳の洋間(床フローリング)に低音調整桟は横置きで使用。低音の量感、ローエンド共に十分出ており、最良、最高と思えるほどZ700-FE108solを気に入りました。
これまでZ701-FE103sol +サブウーファー(チャンネルデバイダー経由で超低音域だけを手持ちの20cmフルレンジで鳴らす)に満足してましたが、Z700-FE108solと聴き比べるとZ701-FE103sol +サブウーファーの低音域に不自然さを感じます。安価にサブウーファーを使いこなすのは難しいですね。
これからは主にZ700-FE108solを使うことになりますが、Z701-FE103solも良いスピーカーですので、ソースによって上手く使い分けしたいと思います。
また、
見た目重視で選びましたが満足です。
音工房Zさんのスピーカーやスタンド(全て塗装無し)と見た目を揃えるために購入しました。想定通りの仕上がりに満足です。振動の影響を気にする様な高級な機材を持っていないので、音質の改善についてはコメントできませんが、このしっかり感は多分効果があると思います。
造りを楽しんで、今は音楽を楽しんでいます
Z700-FE108Solと一緒にスピーカーユニットFE108Sol、 Z203自作式クランプを購入しました。
キットが届いて使いこなしマニュアルを確認し、タイトボンドを使うことにしてネットで発注、タイトボンドは3日で届き組み立てに着手、その後、楽しみながら造りスピーカから音を出すまでに6日かかりました。私は、過去に合板でスピーカーボックスを3回位組み立てたことがあります、その時は木工ボンドを塗って木ネジで固定しましたので、今回のようにボンドだけでの組み立ては初めてです。
タイトボンドは接着する両面に塗ったので多めに使いました。側板の接着はボンドを塗る、側板をダボに嵌めるために、当て木をしてハンマーで叩く、クランプで保持する、これらの工程に時間が掛りボンドが少し乾燥しても両面にボンドを塗っていたので接着力を確保できたようです。はみ出しも少し多くなりましたが隙間が出来ていない証拠として納得しています。クランプを持ってなかったので、オプションの自作式クランプも同時に購入しました、このクランプがなかったら組み立てられなかったと思います。手作り感が好きなので塗装はしていないです。今後塗装するとしてもニスだと思います。スピーカーの保護用にステンレスの5ミリピッチの金網を加工して取り付けています。
気楽に聞いています、聞いていくうちにエージングが進んで音が変わるのでしょうか、細かい変化には気付かないので分からないままのような気がします。メリハリのある音で広いレンジで鳴っている感じです。
アンプはデンオンのPMA-1500RとトライオードのTRK-3488にラックスキットのイコライザーLXV-OT9から真空管回路を削除したもの組み合わせ、既存のスピーカはBOSE363です。ジャンルに拘らないですがジャズ系が好きな感じです。昔かったレコードを聴いたり、CDやFMを聴いたりしています。
音は激変します クラシック中心で聴きますが、特に歌曲に効果的でした
機材 スピーカーは 音工房Zのキット FE108SS 使用のトールボーイスピーカーです 完成品もこのZ501をつけて売っていましたね 多分トゥイーターのコンデンサーの値は違うでしょう 最近大画面テレビを購入し、その横に置いてあります 歌劇をそれで観るのが楽しみになりました アンプ類はアキュフェーズのセパレート、ブルーレイの録画機から光デジタルでマランツのsacdプレーヤーのdadに繋げて再生しています ただ、昔々買ったパイオニアのリボントゥイーターほどの感激はありませんでした メインスピーカーは音工房のキット こちらはFE168SS使用のトールボーイです こちらにも接続して試してみようかと思っています
なんとなく物足りない感じの音がすっきりして聞きやすくなりました。
音源:CDをUSBメモリにコピーしてからmarantz HD-DAC1に挿しています。
クラッシク,ジャズ,最近の若い人が聞くような和製音楽~なんでも聴きます。
AMP:ロシア製の管球を挿したSV-300BE(電源/ヒータ回路にコンデンサ追加)
ウドホーン:TD-4001, トランス式ATT(GA-300/TANGO)
LCネットワーク:空芯コイル, バックロードホーン:TL-1601b
FEの音が聞きたい‥ バックロードに回帰
音工房さんのキット三作目です。
やっとフォステクスのユニットにたどり着いた‥
フォステクスの綺麗な澄んだ音が聞きたくて‥
薄い茶色のコーン紙にやっとって感じです。
40年以上前に仲間がバックロードホーンを作ってました‥
FE203だったかな‥
私はフォステクスだけどコーン紙の色が違うので組んで使ってました。
着色してない自然な音色なのかな‥
さて現在慣らし中です。
とりあえずの感想を書きます
第一印象は聞きやすい
スピード感が有る
ツイターは初めから着けた状態で聞いてます。
慣らしでどんな感じに成るかが楽しみです。
ダクト調整も楽しみですね‥
限定生産ですね‥
惜しいですな‥
Z702-Bergamoより使いやすいかも‥
(低音のボン付きとダブルバスレフの特性なのかな‥ 今は良くなってます。慣らしもあると思う)
ユニットの自然さやキットの高さが有るから。
塗装はワシンの油性ウレタンでする予定です
下地は塗らず‥
裸のオルゴールを塗装した板で鳴らすと音色が良くわかりますよ。
後は好みや趣味性で塗装は変わりますからね‥
簡単に感想書きました。
星は4で。
慣らし中ですし可能性を込めて‥
お値段もそこそこ‥(キットは安いが年々ユニットがね)
MICAはリトルジャイアントでした
だいぶ時間が経過してしまいましたが…。
当方、試聴会に参加させて頂きこの商品を購入致しました。
フロントのMlCAもリアのModenaも事前に別の7.5リッターの箱で音出しを続け馴染ませていたのですが…箱はやっと8月末作成に至りました。
更に完成したこの箱で時間をかけて馴染ませておりましたら凄い表現力を出すようになり只々驚いております。
楽器なんかもその音域を多用するとその音域になれるといいますかその音域の表現がとても良くなる感じが致します。
同様にこの箱でスピーカーを馴染ませる事で更に良くなった感じは致しました。
当方はビックバンドもののジャズをメインに聴いておりまして、各楽器の音につきましてこの音でなければならないとの基準は持っております。どちらかというとトランペットセクションよりもサックスセクションの表現が気になるタイプです。
2020年のZ701-OMMF4を所有しておりこれはビックバンド物を再現するにはかなり良いと思っておりましたが、現在はトランペットセクションに比重を置くならばOMMF4で、サックスセクションに比重を置くならは間違えなくMICAであると思います。
(どうしても音源の録音状態で優劣は変わってしまいますが…概ねそんな感じでございます)
最近はあらゆるジャンルをMICAで聴く比率が大半になって来ております。
最低音再現を重視したスピーカーはバリトンと4番テナーのあたりが影響を受けて聴こえづらくなるのですが、比較的フラットに鳴り元気のいいこのスピーカーはその問題が発生しませんのでそのへんで悩んでいる方にはおすすめのスピーカーです。
情報量が少ない音源をドッカンと低域でも驚かせるスピーカーは他のスピーカーに任せますが、きっちり情報量を聴かせることができるのはこのMICAで、リトルジャイアントと申し上げて良いのではと思っております。
音工房さんではキットの在庫がまだあるようですので、このチャンスでゲットされるのをおすすめいたします。
追伸…作成におきましてタイトボンドはすぐでも1ミリもずらす事ができない事を実感いたしました。国内の木工ボンドとタイトボンドの中間の硬さのがあれば作業しやすいのですが…。
大山様ご依頼の使いこなし記事です
135L 程度の 38cm ウーファー 用箱を試作されている様なので,小生の類似事例をお報せしたら,こちらに情報を挙げて欲しいとのことでしたので. 小生の Z503 の使いこなしを公開します.
1.ウーファー3機種と 135L 自作箱
箱の外寸は 923H x 476W x 438D ですが,補強を徹底し,ダクトも t18 MDF なので,実効内容積 135L 程度です. MDF 突板貼り 水性ステイン仕上げ で,ユニット周辺だけ39mm で,フロント下部,天板,側板 は 21mm,裏板と底板は 18mm ですが,徹底補強. 特に底板はダクト下部と底部袴(w70 ロの字型)と合わせて 36mm から 54mm の部分が大部分です. 内部補強は,測板x2 とフロントと裏板を連結する t18mm 円の字くり抜きフレームAと,側板x2 と天板とフレームAを繋ぐフレームBで強度十二分で,通常の補強桟も側板と前後を連結する様にしました, 天板中央後部はドライバーが載るので 39mm です. 吸音材は熱帯魚水槽用フィルターを,側面片側と天板と裏板に貼付け. 後述の重量増加のため,鉛板を内面下側と底面袴内部にプチル+ネジ止め.
ウーファー装着前で55キロに成りました. ダクトは 10cm x 16cm 角型で長さ 16.1cm ですから,計算上の Fd 約36Hz で,床に一番近い正面下部開口なので,実際は Fd 34Hz 位なようです.
ウーファーは,借用品と時前物で3種類. JBL 2235H (Mts 155g), 2226H (99g), Technics 38L100 (119g) です.
借用品の有名機種 JBL 2235H は一聴しただけで不採用. 悪い意味での重低音(音域で言う重低音でなく鈍い方)で,JBL 4343 の様な 4 Way 向けには良いかもですが,¹” ドライバーに繋ぐには音色が繋がりません. 同傾向な設計の 2231A が音工房Zさんでの試聴会で評価が高かったのは不思議です.
Technics 38L100 は知名度低いですが,現役当時に聽いて印象よかったので,ヤフオク調達. 3 Way で 中音部 (Yamaha NS-1000M 中音 JA-0801) とリボン Pioneer PR-T7Ⅲ のベリリウムコンビとの組み合せなら,これを採用かと想った程,25Hz-40Hz も筋肉質で良い感じでした, ですが,コンプレッションドライバーの速度感には今ひとつ追い切れず,今回用途には次点でした.
JBL 2226H は強靭ながら軽量な振動板の,どちらかと言うとPA用途ですが,ドライバー中音の速度感を超えるのは無理でも,良く追随, 40Hz 以下が 38L100 比で見劣りしますが,ベースやドラムの基音は 50Hz 位までなので,ウーファー は 2226H 確定.
ドライバーは,JBL 2420, ブラジル新興系 PRV Audio D290Py-B, Technics 45D100 を比較. 45D100 は,数カ所耳障りな音を出す箇所があり,却下. D290Py-B は意外なくらいに良かったです. 但し,如何にもコンプレッションドライバーと言う鳴り方とは方向性が異なり,ソフトドームミッドみたいな印象. 「62歳で耳が老化し始めており,耳が完全に駄目になる前に一度は本格的なホーンシステムを書斎に入れたい」と言う小生の動機では,特典低いです. プラ系振動板なのでエージングが進めば,ますます求めていた音から遠ざかりそうなので,次点にします. 但し,20代半ばの子供達や52歳の家内の耳では,D290Py-B がベストだった様です.
JBL 2420 は,十二分にエージング終えてるが老化は未だの程良い所なためか,悪い意味でのホーン中域の音でなく,耳障りな音を出す帯域は皆無. それで居て,切れ味はホーン中域に期待するそれで,気に入りました. 但し,NW コンデンサーの質には驚くほど神経質です. 幸い,16Ωで,通常の8Ωユニットの半分の値のコンデンサーで済むので,全て箔コンと言う贅沢をしてます. それと,超高域は明らかに頭打ちですが,これはスーパーツイーター追加すれば良いです.
スーパーツイーターは,暫定で手持ち遊休品の Yamaha JA0506 使用中. 音質は絶品なのですが,ハイエンドが頭打ちなのは残念. 現行品で言うと,Fostex T925A 辺りに換装するかと悩み中です.
上記構成用ネットワークは下記の通りで確定です.
2226H LPF ; 833Hz -12dB/Oct (コア入りコイル 2.4mH & フィルム 15μF)
2420 HPF : 1441Hz -12dB/Oct (箔コン 4.46‐3.9 + 0.56-μF & 空芯 2.7mH)
ATT : -9.1dB 固定抵抗ラダー型 R1=10Ω & R2=8.2Ω
LPF : なし
0506 HPF : 0.33μF or 0.47μF で低域カット兼アッテネーション
音工房Zさん推奨 2231A & 2420 用とは似ても似つかないですし,教科書通りの定数からもかけ離れてまが,小生の測定とヒアリングで決めた値で,これで実効 1200Hz クロス位になります.
2226H と 2420 どちらも,希望するクロス 800-1500Hz 近辺が盛り上がり気味なので,教科書通りのNWにするとこの辺りが凄く耳障りになり,世間で言う「ホーン臭い音」に成るのは,試してみて痛感. ウーファー LPF を 3.6mH & 12μF にするのが測定上は一番平坦になりますが,音楽再生的にはクロス周辺が少し薄いかと感じました. 良質なコイルを用いた 2.7mH & 13.3μF 辺りがベストかもですが,手持ち 2.7mH コイルが直列部署に用いるには安物で,聴感上は良質 2.4mH での確定NWに負けてます.
上記の例に限らず,ウーファー LPF のコイルと,ミッド HPF のコンデンサーは予算の許す限り良いものを投入しましょう.
コイルはウーファー LPF 用クラスの値になると,測定上は歪率などは空芯が良いですが,試聴すると,速度感の差で,コアコイル一択です. 今回のウーファー+ホーンミッドの例では,少しでもウーファーを軽快に動作させたいのでなおさら.
直列で入るコンデンサーは,どんなNWでも良質な物が良いですが,コンプレッションドライバーが超高能率な為か,これ迄経験したことがない位に音質に差が出ます. 手持ち錫箔コンの関係で 4.46μF と言う半端な値ですが,友人から借りた 4.7μF アルミ箔コンも良かったです. 音楽ジャンル万能ならアルミ箔で,フージョン中心なら錫箔な感じかな? 小生は,BエバンスさんとADメオラさんが錫箔が好きと言うので,錫にしました.
反面,ウーファー用コンデンサーやホーン用コイルのユニット並列に入る素子は,少なくとも小生の鈍い耳では差が殆んど感じられず,予算を注ぎ込むのは勿体ないです. 但し,ウーファーのコンデンサーをオール電解にすると音速感が落ちますので,少しでもフィルムを混ぜると良いです.
60年代まで位のジャズ限定なら,2226H & 2420 w/ Z502 の2 Way が良いのですが,もう少し幅広いジャンルを聴くにはハイエンドが明らかに寂しいです. 100dB 以上でないと繋がりませんので,手持ちホーンTWでルックスの良い Yamaha JA0506 を載せたら音の繋がりも良いので,暫くコレで行きます. アッテネーター入れずにコンデンサーだけで調整すると,測定値と小生の耳は 0.47μF 一択でした. ですが20代の子供2名は 0.33μF が良いと行ってますので,この用途のコンデンサーは値が小さく比較的安価ですから,数種類用意して比較試聴すると良いです. ホーンミッドにホーンTWを追加する場合,ミッドには HPF 入れぬ方が良いと感じました. 2420 の高域を切ると,良く言えば端正な音でTWと繋がりますが,「これならドームミッドとリボンTWの方が良いかな?」になっちゃいます.
中域をホーンにするとアッテネーションの値が大きくなりがちなので,ここも要注意です. ボリューム可変式アッテネーターは,小生は音質的に許容できるのは -6dB 位までなので,この用途には不適です. それ以上絞ると音質劣化だけでなく左右の音量を揃える調整も実質不可ですしね. 固定抵抗2本でのラダー型がお薦めです. これも,特に直列で入る R1 は音質にモロに効きますから,一般に持ちられるセメント抵抗は,減衰値を決めるまでの暫定用にした方が良いと想います. 測定と試聴で値が決まったら,無誘導巻き巻線抵抗を調達することを推奨します. セメント抵抗の5倍と言うと高そうに想われますが,100円と500円です(笑).
■追記「ウーファー振動板実効質量とSPシステム重量の関係」
SPシステム全体の重量と,ウーファー振動板実効質量(Mts とか Mo としてグラム表記されてる諸元)の関係も重量です. 一般的に,SP重量が Mts の500倍以内(市販品SPでは珍しくない)な軽量級SPの低域は締まりがなく,小生は聴く気に成らないです. 500倍を超えると音が纏まり初め,小生的には 1000倍が最低線で,5000倍迄は重量付加効果が明確と想います. 5000 倍を超えると音質改善度が鈍り,10000倍位で頭打ちな感じです.
例えば,Fostex 巨大マグネットフルレンジ(と言うよりもバックロードホーンドライバー)なら,10cm 級なら Mts 3g 超えはないと想いますので,3g とすると,1000倍で3キロ,5000倍で15キロ,10000倍で30キロですから,BLHで箱が大型化する上にデットスペースに重量付加したら,1万倍も楽勝. 20cm級で1万倍は,床の強度と要相談ですが,5000倍くらいなら大丈夫でしょう.
これが 38cm ウーファーだと,例えば JBL 2235H Mts 155g の 1000倍は155キロで,小生が音になる最低限と想う 500倍でも78キロ. 「38cm ウーファーは必ずしも良質な低音再生に向かない」と言う向きが多いのは,ユニットが悪いのでなく,重量級 Mts に対して,十分なSPシステム全体の重量が確保できていない故と,小生は考えてます.
とは言え,38cm ウーファーで質量比 5000倍 (2235H なら 775キロ)を目指すのは,箱の強度確保も大問題ですし,それを2本置いて床が抜けない一般家庭の居室が有るか,疑問大です. 設置する際に成人男性6人がかりとかでも足りなさそうです. 38cm ウーファーの場合は,比較的 Mts が小さいウーファーを選び,1000倍確保できたら良しとするのが現実的でしょう
今回自作した,実効内容積 135L ウーファーボックスは,木質材料重量27キロに,鉛を仕込んで約55キロ. ウーファーを装着し,Z503 ホーンに 2420 ドライバーを装着して乗せると約73キロです. JBL 2235H だと,500倍未達で低域ブヨブヨでしたが,JBL 2226H なら約 740倍で,ウーファー3機種比較で2226H が図抜けて良かったのは,これが奏功していると想います. 現在,外部にも鉛を載せて 100キロ少々 x2 で聽いており,質量比 1000倍達成の音に満足ですが,家内からは,凄く評判が悪いです(^^;).
滑らかでありながらもくっきりとエッジが立ったクリアーな音
【Z503-Woodhorn1/30センチウーファー】
8月19日の試聴会に参加させていただきありがとうございました。
今回の試聴会は音工房Zの1インチ木製Woodhorn1によるJBL4320系と音工房のローコスト
組合せの聴き比べでした。
まず音工房セットは、音出しした瞬間から、滑らかでありながらもくっきりとエッジが
立ったクリアーな音が印象的でした。ウーハーとコンプレッションドライバーとの繋が
りも自然です。いつもの音工房試聴ソースを通しで聴きくと、Z800-FW168HRの延長線上
で強度とスケールをUPしていた様な音に聴こえます。全帯域に亘って余裕、安心感が
感じられました。微小音での繊細感や静寂性も引け目を取りません。大型SPでまま感
じられる重さや鈍さは感じられず、軽快な低音がコンプレッションドライバーをしっか
りと下支えしていました。
一方のJBL4320系は、重低音の延びとスケール感、コンプレッションドライバーの質感で
音工房セットを上回っていましたが、低域の重さと鈍さに時代を感じました。更に中低
域が薄く弱くいのですが、それでコンプレッションドライバーとの繋がりで破綻する事は
無く、むしろ中低域の存在感を敢えて薄め、コンプレッションドライバーに全ての音楽表
現を託してしまったかの様です。嫌な音は一切聴こえませんが出ない音も多々ありデフォ
ルメして聴かせているのかもしれません。音場も後に引っこんでいました。瞬時切り換え
ブラインドテストでは音工房セットに負けてしまうかもしれませんが、自宅で寛いでノス
タルジーに浸って聴く分には、このJBL4320系も悪くないです。
小生にはコンプレッションドライバーを使うつもりは全く無くて、音工房がJBLビンテージ
をどの様にまとめ上げたか?に興味あり参加しました。
しかし、いざ試聴会に参加してみると、1インチ木製Woodhorn1のおかげなのか、ホーン臭さ
は全く感じられず、改めてコンプレッションドライバーの威力に魅了されてしまいました。
フルレンジコーンやドームスコーカーを一般車でハイウェイを走る様に例えるなら、コンプ
レッションライバーは、レーシングカーでサーキットを飛ばす様なものに感じます。まるで
別世界です。
こうなると、JBL375/2440に憧れた2インチでの音が楽しみです。今ならデジタルチャンネル
デバイダーとデジタルアンプで低価格で楽しめるので、心を動かされつつあります。
Woodhorn1と30cmウーファーがベストマッチ
【Z503-Woodhorn1/30センチウーファー】
2023年8月21日視聴会
お忙しいなか貴重な時間を有難うございました。音工房Z様のことを知りZ1000 Bergamoを作成して素晴らしいスピーカーだと実感しました。大山様が実験を何度も繰り返しながらスピーカー設計されているからこその製品だと思いました。普段はジャズとクラシックをよく聞いていますが、交響曲の楽曲にはやや物足りなさを感じていました。今回はWoodhorn1と30(38)cmウーファーの組み合わせにより視聴ができるとのことで申し込みさせていただきました。
Z1000は張りのある華やかな中高音域と低音域ともに素晴らしいですが、箱が鳴る低音と30cmクラスのユニットから直接出てくる低音の違いは歴然で耳で感じるというよりも体で感じる音と言った方がよい違いがありました。
Woodhornは、中・高音域の伸びと張りが素晴らしいです。コンプレッションドライバーの違いによる音の違いはそれほど感じられませんでした。どちらも素晴らしいです。
30cm・38cmウーファーは共に、低音域がよく伸びて余裕が感じられる出方です。しかし、スピーカーユニットによる音色の違いが歴然でした。
音色については好みが分かれるところだと思います。
30cmは切れのある華やかなレスポンスがよい低音に聞こえました。
38cmは深みのあるしっとりとした低音ですがややレスポンスが遅く感じられました。この違いはスピーカーユニットが金属かコーン紙か、新品か中古品かによる違いと思います。できることならば同じ素材のユニットで30cmと38cmの違いを比較してみたかったです。
1インチWoodhornとの組み合わせとしては、私の好みは30cmウーファーだと思いました。
低音域とスケール感は大型ユニットスピーカーが一番だと思っていますが、リスニングルームの広さやご近所への音漏れ、コストパフォーマンスを顧慮すれば今回の30cm70Lがベストな組み合わせだと思いました。
貴重な聞き比べの機会を頂き有難うございました。
音楽のジャンルによって違ったように聞こえました
【Z503-Woodhorn1/30センチウーファー】
30cmのウーフアーと38cmのウーフアーの聞き比べに伺いました。
私のいつも聴くジャンルはクロスオーバーが主体で、30cmの方が音圧、バランスが良く感じました。それに比べて38cmは容量も大きいし、口径も大きいので期待をしていましたが、低音の響きがいまいちでした。
同席していた方がお持ちしたコルトレーンのCDを聴いているとその逆で、38cmの方がバランス、低域が出ているように思え、30cmは低域不足感、音がこもった感じに聞えました。
30cmのウーファーのメーカーを教えて頂けたら嬉しいです。
贅沢な一品
【Z503-Woodhorn1/30センチウーファー】
Z工房さんの最新作ウッドホーン+大口径ウーファー
このタイプのスピーカーを作っている有名メーカーはJBLぐらいでしょうか? JBLはこのタイプの老舗ですから やめるわけにはいかないでしょう。ポルシェの911シリーズみたいなものですから。今のJBLは一般的には高性能な?Bluetoothスピーカーメーカーのイメージですが、
1900年代の後半は高級スピーカーの王様ブランドでした。私がオーディオの虜になったのも45年前にヤマギワ電機のオーディオルームで聞いたJBLです。
今回2種類のスピーカーが用意されていて38㎝のJBLウーファー+JBLホーンドライバーとデエトンオーディオの30㎝ウーファー+SBオーディエンスのホーンドライバーです。両方のスピーカーを聞いた第一印象は今まで聞いたZ工房のスピーカーには無い、ゆったりとした音と深い余韻、これはなんだ? 多分部屋かも?正面の壁に取付けてある音響パネルBやスピーカーを取り巻く音響パネルAのの効果が聞いているのでしょうか、この位の大きいサイズのスピーカーになるとやはり部屋の影響が大きいのでしょう。部屋を選ぶタイプのスピーかもしれません、このスピーカーが良さを発揮するのは8畳以上の部屋でルームチューニングが行き届いた部屋が条件だと思いました。そんなところも中級向きなスピーカーかもしれません。2機種の違いは明白で38㎝JBLコンビはゆったりとした大きな音でホーンドライバーは切れのある音です。でも全体的には中低音の明瞭感が乏しくぼやけた感じで、他の方が聞きやすいので喫茶店で聞くには最高だとおしゃっていました。30㎝デイトンとSBオーディエンスのコンビはよく締まった大きい明瞭な低音、解像力が高いけれど聞き疲れしない高音の現代的な音で幅広いジャンルの曲をカバーできるスピーカーでしょう。次にZ800ーFW168HRと聴き比べてみました。いつもバランスの良い高音質なZ800ですが今回はハイ上がりな音に感じました。たぶん他の2機種が低音よりな音だからハイ上がりに聞こえたのかな?やっぱりスーパーツイーターがあった方がバランスが取れた音になると感じました。このような大きいラグジュアリーなスピーカーをキットで販売するとは感動です。
憧れのウッドホーン!
【Z503-Woodhorn1/30センチウーファー】
今回の試聴は30cmキット製品版 70L と 38cm試作品150Lの聴き比べで、音工房zでも初チャレンジのウッドホーンの2WAYシステムとのこと、期待いっぱいで試聴に伺いました。60代から上の方なら昔、ウッドホーンのブーム?があり憧れたことがあると思います。私もMJを読みながら夢想した覚えがあります。ただ、コストやノウハウなどハードルは高く、一般人がおいそれと立ち入ることはできない超ハイエンドな世界と思っていました。
突然、現実的な価格でウッドホーンのキット販売が告知されビックリしました。そしてやっと試聴会の案内、暑い中頑張って聴いて来ました。何時ものレビューは普通のレビューですが、今回は書きたいことが多いため、ブログの抜粋&私の試聴感想という形式で箇条書き風に纏めました。抜粋部分は基本的に原文のままで、開発経緯と使いこなしの中からあらすじ的にまとめたつもりです。12コマのブログを読むのは大変ですので(書くのはもっと大変ですね)、以下をお読みいただければ大体の概要が分かると思います。なお、スピーカーの写真がメルマガより見れますので先にご覧になってください。
スピーカー以外の試聴機器はいつもと同じです。
試聴曲は
マイルスデイビス Walkin (JAZZ トランペット)、
STEVIE B Because I Love You (男性ボーカル)、
パイレーツ・オブ・カリビアン(サントラ)、
image2(オーケストラ、バイオリン物など弦楽曲)
など11分堪能しました。
試聴の後、大山さんからどちらが良いか尋ねられました。大人の返事としてはどちらも良いが30cmの製品版が素晴らしいと答えるべきなのでしょうが、嘘をつくことはできないので「38cmの方が好きな音です」とお答えしました。どちらが良い音かは判断しずらいレベルでしたが、好きな音は38cmの方でした。その理由は以下をお読みいただければ納得いただけると思います。なお、製品版の試作品の図面や仕様がメルマガからダウンロードできますので参考にして下さい。
・オーディオ初心者の方にとって38センチの大型ウーファーはさぞかし凄い低域がでるのだろうと期待するかもしれません。しかし、ローエンドの伸びだけでいったら、20センチ2発のパッシブサブウーファーをデジタルデバイダーで上をカットして下だけアンプで持ち上げてやったほうがよほどローエンドを伸ばすことができます。
10センチのフルレンジでもBHBS箱で40Hzまではでますので、40Hz以下を含まない音源でブラインド比較をしたらどちらが鳴っているかわからない人が多いでしょう。
(私の試聴した感想)
Z1-Livorno + Z506-Livornosub の試聴時の方がはるかに低音は下の方まで量的にも出ていました。10cmフルレンジBHBSのBergamoなどの方が低音の迫力は遥かに上に感じます。38センチの大型ウーファー(JBL 2231A)は意外とソフトで優しい低音で包み込んでくれるような鳴り方で、大きな空気の塊に包まれたような心地よい感じがしました。半面、ボーカルなどの定位は音場型とまでではないですがぼやけ気味で、ピンポイントの定位が求められるようなソースには向かないと感じました。中古でアルニコの減磁があるかもとのことで本来の音とは違っている可能性はあるかもしれませんが、このおおらかさが38センチの大型ウーファーの美点かと思いました。
・大型ウーファーは、振動板が重いために切れの良い低域というよりかは少し「とろ~ん」とした低域になりがちというデメリットもあります。昔、10センチのバックロードホーンから20センチのバックロードホーンにいったときにさぞかしローエンドが伸びるだろうと思ったのがそれほどでもなかった経験があります。
(私の試聴した感想)
「とろ~ん」とした低域は私も感じました。意外と38センチのJBLの方が 「とろ~ん」は少なめで、メーカーによる音の違いなのか、明るめのアメリカンサウンドのJBLのキャラなのかもしれません。シングルバスレフと重い振動系のため、BHBSの様な締まった低域とは違う低音ですが、今でもPAなどではホーンとの組み合わせが主流なのはこういう音も支持されているからではないでしょうか。昔からALTECのA7などを家庭で使われている方もけっこういらっしゃいますし。
・JBL 2231A
中古品をオークションで購入しました。エッジの張替えをされているので、オリジナルとはだいぶ違うと思います。ローエンドが過剰にでている反面、ミッドバスは少なめ。少しダブルバスレフのような低域の出方をしています。全体のバランス的にはもう少しミッドの力感があるほうが良い印象がありました。高域とのつながりは良好でした。
JBL 2231A は前オーナーがエッジを貼り変えているからか、アルニコの減磁かわかりませんがローエンドだけは良くでますがミッドバス少なく切れが弱く感じました。年代ものになるとどうしても個体差の影響が大きくて正しい評価が難しくなってきますので、ここで書いた評価がJBL2420の新品評価とは違うことを繰り返し書いておきたいと思います。アルニコマグネットを再着磁等すれば変わるかもしれませんが、ローエンドはよくでるのですが制動感が弱めな感じです。3つのユニットの中では最も下まで伸びていますが若干尾を引くようなローエンドです。ただ、高域はさほどうるさくなくホーンとつながってくれます。
(私の試聴した感想)
オリジナル(新品)とは違うかもしれませんが私はこの音は好きです。大山さんの評価とは逆の感想ですが、ヘタった性かミッドバスが少な目がかえってホーンとの繋がりが良くなり、自然な音に感じました。先にも書きましたがスケールが大きな音像で、30cmから切り替えると2~3割違うと感じます。低音の量的にはどちらも差は感じませんでしたが、音質はかなり違うと感じました。なお、左右の特定の音域が右の方が強く(多く)聞こえました。最初、私の耳の性か、録音がそのようになっているのかと思いましたが、30cmに切り替えると左右均等に鳴っているし、曲を替えてもアンバランスは感じられましたので、やはり古いスピーカはヘタレを覚悟する必要があるようです。
・低域の出方(キレ、スピード感、しまり)
概していえば口径が小さい30センチのほうが良いです。締まり感や切れ感はどうしても口径が大きい38センチは、すこし制動感が弱くワンテンポ遅れた感じになりがちです。しかし、ここはスピーカーユニットの価格やクオリティーによっても左右される部分もあります。
(私の試聴した感想)
38センチは、すこし制動感が弱くワンテンポ遅れた感じは私も感じましたが、ウッドホーンは意外とやさしいソフトな鳴り方で、金属ホーンや長岡式バックロードホーンの様な突き刺さる感じはないのでスピード感&生音感命の方でなければ許容範囲と思いました。
・音像のサイズ
1インチホーンの2wayはクロスが1KHz近辺より下げにくいため、結構高域がウーファーから聞こえてきます。そのために、ウーファー口径が如実に音像のサイズに影響してきます。
38センチの口径のほうが大きな音像、30センチ口径のほうが小さな音像になりますが、どちらも大口径なのでそこまで大きく変わるわけではありません。
女性ボーカルなどを聞くと38センチは巨大な口になってしまいがちですが、ピアノやパイプオルガンのように躯体が大きな楽器の音像表現や音が面で迫ってくる感じは38センチ凄いです。
(私の試聴した感想)
ここも大山さんとは意見が分かれますが、38センチと30センチの音像の差はかなりあると感じました。好みの差かもしれませんが、私は広く包み込まれるような音像が好きなのでこの差が気になりました。スピーカーは個々に得手不得手がありますので、長所を生かしたソースを選べばよい訳で、ボーカルは小型のフルレンジで聴けばノープロブレム!
ただ、音像のサイズより私が気になったのは「結構高域がウーファーから聞こえてきます。」の部分で、30cmの方は38cmより高域が多く(高くまで)出ているのではと思えました。そうするとホーンの音域と重なり2つのユニットから音が出ている感じがして繋がりが悪く感じられます。重なった帯域が持ち上げられた感じで煩く感じてしまいます。昔、カーオーディオでサブウーファーが流行ったとき、スペースの関係でBOXは小さめのバスレフにせざる負えず無理やり25cmを2発押し込んだ時の音とちょっと似ているなと感じました。
(追伸)
持ち時間の後スーパーツイーターを付けて試聴させて頂きました。30cmのシステムは見違えるように良くなりました。煩さは無くなり全域がフラットで癖なく伸び延びと鳴りました。こちらは初めから3WAYで組んだ方が近道かもしれません。問題はスーパーツイーターのお値段ですね。ウファ―とドライバーで5,6万なのにスーパーツイーターが10万はきついですね。せめて5万ぐらいでお勧めがあればいいのですが。なお、38cmは2WAYのままでもOKですが、スーパーツイーターがあるとなおいいです。ハイレゾ音源をお聴きの方は一考の余地ありです。
・40Hz以下のローエンド
これは38センチ&150Lの箱の圧勝です。40Hz以下の音圧がかなり違います。ローエンドまで伸びているのはユニットの口径が大きいのもありますが、やはり箱の容積が大きいのが効いているようです。
一方の30センチウーファーですが40Hzあたりまでは十分にでます。実用的な部分の低域に関してはどちらも問題ないけど20~40Hzというマニアが求める超低域だけは38センチ&150Lの箱が勝っているということになります。
(私の試聴した感想)
今回の試聴は30cmキット製品版 70L と 38cm試作品150Lの聴き比べでしたが、ウッドホーン以外はユニット、エンクロージャーなど違う箇所が多く何が音の違いを生んでいるのかを特定するのは困難に思いました。販売予定品と老舗JBLの比較を聴いてもらうという主旨は理解できますが、あまりにも変数が多く純粋な聴き比べてしては無理があると思います。ドライバーだけ入れ替えて試聴すればよかったと今思えば残念に思われます。そうすれば 70L と 150Lの違いやドライバーによる音の違いも感じられたかなと。
・ウーファーというと普通は低域の良し悪しかと思われるかもしれませんが、1KHzあたりでクロスをとる2WAYのウーファーは「高域」が全体の音を判断するうえで大変重要になってきます。あるウーファーだと高域が綺麗にホーンとつながってくれるのに、別のウーファーだと刺々しいということが普通におこります。低域の切れ感と伸び、高域のつながりを元に評価しています。
1インチホーンの2wayはクロスが高いのでウーファーから高域が多くでてしまう問題はネットワークを急スロープにしたり、デジタルデバイダーを使うことで改善する可能性は大きいです。ネットワーク部分でウーファーの高域部分の評価はひっくり返ることもあると思います。
(私の試聴した感想)
この件は今後の課題として研究頂けると嬉しいです。
・スペック表をみてわかったのですが、DSA315-8は1~2KHzは落ち込んでいて、4KHzにピークがある感じです。他の2つのユニットは逆に1~2KHzが盛り上がっています。ご自身でウーファーを選択される場合は1~2KHzに山が大きくなく可能なら凹んでる周波数特性のウーファーが使いやすくなるかと思います。
1インチウッドホーンはどのホーンを使ってもここの1~2KHz帯域がもりあがるので、ホーン設計時に盛り上がりを大きくならないように工夫したのがZ503-woodhorn1になります。
しかし、ここはウーファーユニット、コンプレッションドライバー、ネットワーク、吸音材などすべて良質なものをチョイスして組み合わせでバランスをとる必要があると思いました。
(私の試聴した感想)
「DSA315-8は1~2KHzは落ち込んでいて、4KHzにピークがある感じです。」とのことですが、1~2KHzは落ち込んでいるユニットでウーファークロスが 1000Hz 12dB/oct でも高域が出てしまうとすると、もう少し高域が出ない工夫が必要に感じます。「すべて良質なものをチョイスして組み合わせでバランスをとる必要があると思いました。」には私も同感です。大山さんなら更に高みを目指して解決策を見つけてくれるとことと期待しています。
・JBL 2420 は音的にはフラット系で超高域まで良く伸びていて、高域は解像度が高く、長く聞いていても疲れません。耳につく高域帯域が全くないわけではないですが、他のドライバーと相対比較したときに癖が最も少ないドライバーに思いました。
ホーンでありながら透明感の高い音で、かつ癖が少なく聞きやすいという絶妙なバランス感の上に成り立っている感じがします。ヌケのよい晴れやかな音です。
(私の試聴した感想)
JBL 2420 の音は明るく大変聴きやすい音と私も思います。と言っても私もウッドホーンどころかホーンスピーカーの経験はあまりありません。今回のドライバー2点が実質初ドライバーです。偉そうにいえる立場ではありませんが、音工房zに通い始めて4年目です。専門的な評価などは到底無理ですが、好きか嫌いかという分かり易い基準なら誰でも自分への評価は可能だと思います。食べ物と同じで音(音楽)の好き嫌いは個人基準の評価で、他人の評価は関係ありません。迷える子羊を導いてくれるパイロットして大山さんにはずっと先を歩いてほしいと思います。
・ブラインドテスト2 SB-AUDIENCE BIANCO-44CD-PK VS PRV AUDIO D290Py-B
こちらは前回紹介した新しい安価な新興ブランドの上位2機種の対決です。JBLやTADのような金属系の振動板ではなくどちらも樹脂系の振動板をドライバーに利用しています。先程のJBLやTAD等の金属系に比べるとトゲがなく聞き疲れしない音です。
(私の試聴した感想)
残念ながら私の好みは、30cmキット製品版 70L ではなく 38cm試作品150L と大山さんには答えました。好き嫌いは頭で考えたのではなく感じたままです。忖度して「30cmキット製品版 70L ブラボー」と言ってみても意味がないと思い正直にお伝えしました。青木さんも2420に似た特性のSB-AUDIENCE BIANCO-44CD-PK はかなり自信があったようでした。試聴時は今回のブログは飛ばし読みした程度でぶっつけ本番の試聴でしたので、開発の苦労や経緯は知らずに思ったままを申し上げてしまい恥じ入ります。ただ、ここまで書いてきて私の感じた多くのことは音工房zでも承知していることがよく分かりました。ウッドホーンは自作派の憧れ是非更なる展開を期待しています。