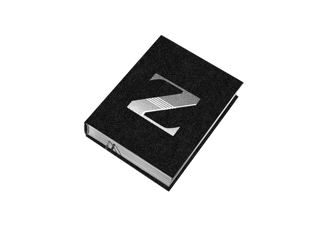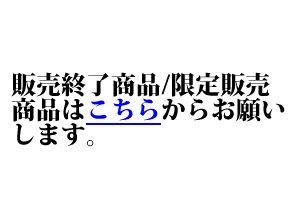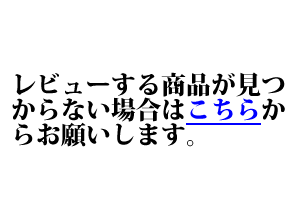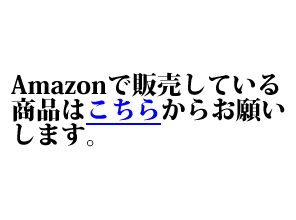レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
オーディオを中心とした趣味をトコトン楽しむ (音楽三昧の道連れとして)
音工房Zキット Z800-FW168HR(V2.6)
1.発 端)) 誰かの為に日々の生活にあくせくした現役時代は突然終わり、シニア時代に突入。すると、 収入は無いのに、暇をもてあます羽目に陥りました。しかし、これは自分の為に生きる素晴らしい人生の 幕開けでした。
今般のコロナ禍に対し、一つの解答として、 ① 手を動かす ② 好きな音楽の興味を追求 友人と相談して、えいっとばかりに「最後の贅沢」として今回のキットに手に伸ばした次第。 完成品を単純に購入するよりもそのプロセスを楽しむこと=手間を掛け、更に何より友人と過程を話題を シェアする事にしました。友達と楽しむ大切な時を買い求めた事になります。
2.キット到着)) 届きました。まるで高級プラモデルを開梱した小学生になっての興奮状態です。素晴らしいのは滅多に 無い価格もそうですが、目の前に素晴らしいパーツが当りまえのように並んでいます。何と言う幸せ。
① パーツ (スピーカーユニット、本体素材、ネットワーク、配線) スピーカーユニットは名にし負うFOSTEX/箱部材が正確に加工済み/組立に迷う事無し/ ネットワーク部品も細かい部品も含め良いモノの組合せ。上手く行く予感。
② 高品質の電子部品・配線 通常使用される部品より更に品質が高く/信頼性が向上しており/+部品メーカー素性が明確/ 配線部材も問題無し。
③ 頼もしいマニュアルの存在 本体のマニュアルはP 63にも及び、更にオプションの塗装マニュアルもノウハウてんこ盛り。 大山さんの長年の智惠が詰まっているようです。
④ オーディオの向こうに木工組立とその後の塗装の楽しみ 本体組立はシステマティックに構想・展開されており、単なるキットの枠を超え、木工趣味の一部である 塗装までに楽しみがある事に気が付きます。
音を楽しむという行為は音が出る以前からも、そして音が消えた後も続きます。単純な動機からのプロセス 開始ではありましたが、これは当初全く予想しなかった深化した展開です。
塗装は手間が掛かりますが、水性・油性?何色にするのか?タッチは? これでは全ての購入者に全く同じモノを 作れと言われても全員が異なる嗜好がありますから却って出来ませんよね。 これが完成し、音を楽しんで、そこに頼もしく存在する愛器となって行く訳で、全てのスピーカー製作者の 個性が表現される器が完成するのです。
3.製 作)) 製作には各人の技量や時間配分があると思いますが、小生の場合はゆっくりと楽しんで塗装を除いて大凡12時間ぐらい。
Step1 箱造り マニュアルを見ながら、縦/横それに上/下の区別が明確な手順に従い組み立てます。箱底面には耐震用の鬼目ナットを 取り付けます。 板には既にダボ穴があり、サイズの異なる二種類のダボを使用して組立を進めます。仮組みして、その後組立。
Step2 ネットワークと配線/組み付け 部品の一覧から始まり、基盤の図解を確認して仕上げます。文系の小生にはコイルとコンデンサーの役割が初めて 判りました。ハンダ付けがありますが、それを乗り越えるとほぼ問題無し。
配線には+が銅色、ーは銀色と分けてあり、これに端子を付ける事になります。説明通りに組み込めます。 アッテネーターを取り付けたら箱としてほぼ完成です。
Step3 ポート取付と吸音材 ポートは特に何の問題も無くあっさりとセット出来ました。又、吸音材もすっきり貼り付け。
Step4 スピーカーユニット取付 FOSTEXの箱に入ったウーファーとツイーター取り出して、ネットワークと結線し、完成した箱に組み込み、 はい、完成です。形としては出来ていますが、これから何を聴くのか?が購入者一人一人によって異なります。
Step5 設置とエージング 設置場所は最初から決める必要はありません。台はどうする?等々試行錯誤を繰り返してベストな場所、 高さに設置下さい。購入者の愛器となったセットを時間を掛けて慣らし運転を行い、仕上げて下さい。 注)塗装のタイミング 塗装は後日でも良いのかも知れませんが、後戻りをする手順は怠惰な小生には難しく思えた為Step3の前に 挑戦しました。 今回はスプレータイプの油性ペイント(マホガニー)で二回塗りを行い一旦完成としました。今後はBRIWAXで 上塗りを挑戦する予定です。 4.AUDIOの楽しみ)) 動機は良い音を聴きたい一心。
実は過日最近評判の良いスピーカーセットを試聴すべく態々東京の都心まで出向きましたが、あれ、高級?を
謳ってもこんなもんかい?流石にシニアになり耳鳴りもするようになって聴覚が衰えたかと一瞬思ったのです。 本来の音痴で音の善し悪しは美味く表現出来ませんが、何となく自分の感じる良い音とは異なる違和感を
覚えて帰宅しました。
不断はAVアンプでBLディスクに記録したメトロポリタンのオペラを楽しむ位でしたが、上記の経緯から 久し振りにデジタルソースの広がりを感じるべく新らしいオーディオに好奇心が芽生えました。
で、Z800-FW168HRの登場です。一体どれほどの音が愉しめるか? 素直な疑問と期待で、迷った挙げ句ですね。
5.Z-800をデスクトップミュージックの出口として)) Z-800という立派なシステムをデスクトップオーディオに使用して申し訳ありません。が、邪道ではありますが、 自宅とは言えども自分の好きな分野を思う存分堪能出来る場所は限られています。
尚、単純に作業を行う机に張り付いた姿勢ではそもそも無理があります。スピーカーセットとの間は真っ当な音楽 鑑賞の距離が必要ですね。ですので、鑑賞時は当然距離をとります。
6.機器構成)) 1)メイン (PCベース) デジタルソースの再生を想定している為、現状下記の構成です。近々SACDプレーヤーの購入を予定しております。 基本的には小音量での再生を楽しむ構成で、皆さんの本格的なオーディオとは異なります。
Case A) Audirvana ベース Mac Mini (> iTunes Library > AIFFファイル (FLACファイル) > Audirvana* ) > 光接続 > YAMAHA ワイヤレスストリーミングアンプWXA-50 > Z800-FW168HR
*アプリであるAudirvanaにはiTunes統合モードがあり、データを流せます。
Case B) Web ベース ストリーミングとして deezer を使用。この場合、Audirvanaが使えないのでそのままながしています。
2)iPhone系 (所謂スマホベース) ご参考までに記述します。 流石にオープンエアが懐かしくなりましたが、つい最近まで15年ほどイヤフォンに凝っていました。 今は懐かしいWalkmanからの転進組です。スマホ利用は場所を選ばず便利ですが、イヤフォンはピンキリで 要注意ですね。
イヤフォンは個人空間を音楽空間に転化させる謂わば仮想現実を展開する便利な道具ですが、Z800は更に 実際の部屋を広大な音楽空間に展開し、居ながらにして実演奏が繰り広げられるイメージです。 iPhone > アプリ ① iTunes > アプリ ② FLAC Player >
イヤフォン> a. Apple / AirPods Pro インナーイヤフォン(アクティブノイズキャンセリング 機能付きワイヤレス) b. SONY / MDR-1RBT (ワイヤレスヘッドフォン) c. SHURE / #535 (有線インナーイヤフォン)
試聴感想)) 完成後30時間程のエージング。以下その後慣れた曲での感想を書かせて頂きます。 音源はCDからiTunesに取り込んだAIFFファイル及びFLACファイル等です。
オーディオは種々の要素が絡む領域なので、皆さんそれぞれのご意見として感想の受取方はお任せ します。ただ、申し上げたい事は感じられる物理的空間としての音の場がとても広くなった気がします。
軽便なスピーカーセットでの籠もった乃至は高音ばかりが強調される癖が無く、伸びやかな音場が展開します。 普通のスピーカーユニットでは歌手があたかも本人が苦しそうに歌っていると聞こえるのにZ800では伸びやかで 楽しそうに歌っています。何のストレスも感じられず、音源が3Dとして目の前に存在し、無理が無いのです。 Classics ピアノ 音源にも依るのかと思いますが、グレン・グールドのゴールドベルグ変奏曲(録音1981年)は想像以上に 素晴らしい音で聴くことが出来ました。音の粒立ちが良い。グールド本人の鼻歌?も楽しい。
室内楽 モーツァルトのグランパルティータ(13管楽器の為のセレナード)を聴くと、合奏する事が喜びであることが いまさながら判りますね。昔はベームのゆったりとしたテンポのアナログディスクを楽しんでいましたが、 最近はテンポが上がっていて軽快な曲として楽しめます。音の重なりがタピストリーを鑑賞する如く 楽器の音色で重なり合う光景が展開されるのは本当に有り難いです。
交響曲 分厚いハーモニーが、独奏楽器の響きが押し寄せてきます。又、ベートーベンの第九「歓喜の歌」を聴くと 平板に聞こえていたものが音の集合体としてより立体的に盛り上がって感じることが可能です。 ホールでの音場感がありありありです。
オペラ deezer でモーツアルトの魔笛を聴いて見ました。オペラハウスでの臨場感がありあり。中央席に着席し、 目の前に歌い手の独唱・二重唱から合唱までが展開されます。想像が膨らみ、音楽の陶酔に浸れますよ。 Z800では、喜劇から重厚な悲劇まで低音の伸びと高音の響きが癖の無い音質で鑑賞出来ます。
Jazz Instrumental Dave Brubeckの名曲Take Five を試してみる。ハイハットが心地良いリズムを刻み、スネアドラムが快調に 運ぶ、そしてバスドラが響く。勿論、Alto Saxも良いメロディーを奏でている。良いではないですか。
Vocal Sarah VaughanでBe Witchedはどうだろうか?しっとりとした高音が弦との絡みも良く伸びやかに発せられる。 ああ、名演だね。スピーカーユニットが良いモノになるとサラ・ボーンの印象が平板なものから良くなりました。
Popular Vocal Engelbert Humperdinckを懐かしく思い、試しに聴いてみましたが、Last Waltz の彼のハイトーンの伸びは 素晴らしい。 「君!美味いね、更に上手になったねと今更ながらに再認識した次第。」
bastian923
Z800-FW168HRは、非常に難しいですね。
私のシステムは、アンプはラックスのL505uxⅡ、SACDは
ヤマハのSD2100を使用スピーカーはJBL4425、ヤマハNS10mです。ハイスピードな高音のZは昔のjazz喫茶のようです。
TIGLON製のMGT-DS7060のスピーカースタンドに変えたら
ずいぶん落ち着いてきました。暫くはこれを調整しながら追い詰めたいとおもいます。
明らかに違います
音工房Zさんのスーパーツイーターキットからグレードアップしました。効果音、高域の鳴り方がめちゃくちゃ良くなりました。スーパーツイーターキットとZ501の差は4倍近くの値段の差だけではありません!思い切ってグレードアップしてよかったです。
本領発揮!
メインシステムを更新し2回目の投稿です。プリメインアンプDENON PMA-A110 CDプレーヤー マランツSACD-30n レコードプレーヤー テクニクスSL-1200GR DENON MC型カートリッジDL-103R の構成での試聴です。ジャズは低音の締まりと力強さが増し定位がビシッと決まった感じです。クラッシクはオーケストラの各楽器の音が判別できるようになり特に弦楽器の音が鮮明に美しく響きます。全般にダイナミックレンジが広がりこのスピーカーの解像度の素晴らしさを実感でき、非常に気持ちよく各ジャンルの音楽が楽しめるようになりました。スピーカーが持っているポテンシャルが発揮された感があります!
ピアノの音が綺麗、全体にバランス良く音が出ている
クラッシク、ジャズを主に聞いています。以前はタンノイの3LZを40数年聞いていました。中高域がとてもきれいです。メンテナンスのため片側の側面は接着せずにはめ込みにしています。音に影響あるでしょうか
音像の立体感が素晴らしい。
プレイヤー IO DATA SOUNDGENIC
DAC OPPO SONICA
アンプ PIONEER A70A での再生です。
音工房さんは以前よりスーパーツイーターやスピーカーグリルなどを利用させて頂き
商品の取り扱い説明の丁寧さに感心していましたので、キットとしては高額な部類
でしたが不安はありませんでした。
再生音は非常にソフトな印象ですが、細かい音がよく聞こえ立体感が素晴らしいです。
部屋がかなりライブな環境でそのせいもあるのでしょうが、離れて聞くとそこに人がいるように聞こえます。これは結構癖になりますね。
試しにスーパーツイーターを加えてみましたが高音はのびますが立体感は減退するようです。
鳴らし始めてまだ2か月なので色々調整は必要かとは思いますが、このあたりは完成品にはない楽しみかと、
同じ環境で鳴らしているFE108SOLのBHとは対照的な音ですが、オールマイティーに音楽を聴くものとしてはこちらのほうが安心感があります。
いずれにせよ、個人で揃えればユニットとネットワーク部材だけで15万円近くになるものを
キャビネット含めてこの値段で販売している音工房さんに感謝します。
使えるアクセサリー
【スピーカー能率補正機能付スピーカー切替器】
スピーカー切り替えは、極力ケーブル接点を増やしたくないので切り替え機を使用せず、SPシステムごとにパワーアンプを接続していたが、SPが3セットになったので音工房のブラインドテストで便利だった切り替え機を使ってみることとした。
導入した一番の収穫はお恥ずかしいことだが、長岡式共鳴管タイプのリファレンスの左右バランスが悪いことに15年目にして初めて気付いたこと。従来はセンターが甘いという程度の認識だった。
これが音工房のZ800-FW168の4Wayとの瞬時切り替えで、一聴にして悪さが判明した。
原因はフォステクス限定ユニットの特徴である巨大マグネットのため、バッフル開口とのクリアランスが不十分でSPコーン後方に音が抜けきらないことであった。特に黄銅のサブバッフルを介しているため、バッフル厚は30㎜を超えて、SPの取り外しがするりとは行かないほどきっちり埋め込むような感じSPマグネットが収まるため、クリアランスがほとんど取れていない。
このクリアランスの幅が左右CHでわずかにずれるため、位相差や音量差が生じて聴感上センターが安定していなかったのだ。早速バッフル開口部の淵をRound処理して問題解決。
ここでわかったことは、自作のメインSPは背圧が一切かからず、ネットワークにコイルが入らないため、あっけらかんと軽々と透明度の高い音を出すこと。ダイナミックレンジもすごく広く、ボーカルや撥弦系の楽器には特に相性が良い。長岡式バックロードより低音域のレンジも広く重低音も出てオケにも強い。これに対してZ800-FW168の4Wayはバランスが良くレンジも広大でサブウーファー追加で迫力も出て持続音に強い。高価なリファレンスモニター調だが少しおとなしくよく言えば品が良い優等生。このような違いが瞬時切り替えですぐわかるということが凄まじい。
ただ聴感の不思議なところは、しばらくすると違いが耳になじんで多少の違いなら特に気にならなくなることだ。こんな体験もこの製品の魅力だろう。そんなこんなでZ800-FW168のネットワークをいじってZ1-Livornoの製作記事にあるようにユニットをもっとフリーにしてみたい欲求が湧いてきた。この場合も瞬時切り替えは変更の違いを左右で確認すれば一聴で判断してくれることが期待できる。(音工房でZ800-FW168の4Way完成型ネットワークを再提案してほしい!!!)マルチCHは泥沼にはまるというがこれは一つ一つの変更の違いが一聴では判断できず、そのうち頭が混乱することだと思う。
所で本製品の使い勝手だが、これは個人的にはかなり問題であった。その結果、設置後のルックスは写真にもあるように最低。(実際にはこの上にレンガを置いてケーブルの捩れで動かないよう固定している)
①SP端子が小さく、間隔も狭いため配線作業は容易ではない。
②バイワイヤリング対応もできず、端子を加工して何とか接続したが接点の安定性はよいとは言えない。盤裏にSP端子を集めるというより盤上にSP端子を配してもよいかもしれない。
③ピンケーブル端子間隔も狭く接続しにくい。
④取説はわかりにくい。シンプルに手順ごとに操作を記載する配慮も必要と感じた。ぼけ老人のせいかボタンの個々の機能説明を読んでも実際の試聴手順につながらず、リモコンを色々いじって試行錯誤を繰り返し、音出しするまでに丸1日かかってしまった。
アンプのブラインドテストでアンプの違いを聞き分けることは音工房でも至難の業という。この切り替え機はプリの機能があるため、PC音源では直接DAC出力を入力できるが、メインのプリを介した音と区別はできない。というか違いを感じようとする気力はわかない。ADがリバイバルする中、既存のプリは手放せないが、従来のオーディオのコスト概念は大きく変貌を遂げつつあるようだ。音工房の主張するようにSPにコストをかけ、そのコストを自作で軽減することでソースにリソースを集中させてその充実を図ることが今後のオーディオの姿かもしれない。ひょっとすると大蛇のようなケーブルの違いも基本ないも同然か?であるならば本製品は一つの方向性を象徴するものになるし、今後のトレンドをリードするうえで大きな武器になるものと考えられる。
自分なりに工夫しながらオーディオを楽しんでいきたいと考えています。
これまで断片的に読ませていただいておりましたが、纏まるとすごい分量ですね。貴重な研究成果や制作ノウハウをご提供いただき、感謝いたします。自作ハイエンドはなかなか目指せませんが、百科事典を参考にしてゆっくりですが自分なりに工夫しながらオーディオを楽しんでいきたいと考えています。
ご自身のノウハウを惜しみなく公開されている姿勢には感嘆しています。
私は自作はしませんが、自分のオーディオを可能な限り良い音で聴きたいと思っています。
ご自身のノウハウを惜しみなく公開されている姿勢には感嘆しています。
参考にさせていただければとてもありがたいことだと思っています。
機会があれば製品も一度使わせていただきたいと思っています。ありがとうございます。
オーディオ熱が冷めつつある今日貴重な存在です。
いつもホットで貴重な情報をありがとうございます。オーディオ熱が冷めつつある今日貴重な存在です。非現実的な価格の製品のみが一流である様な錯覚に陥っているオーディオ評論家たち自身がオーディオ熱に水を注いでいることを知らしめてあげて欲しいと熱望します。
今後も楽しみです。
長岡スピーカーを何個も作りましたが、水害で設計書もスピーカーも流出、このレポートは非常に参考になります。少しずついい好みの音になるよう追い込んでいきたいものです。今後も楽しみです。よろしくお願いします。
独特の音世界を展開(追記)
聴き込み1か月後の感想。当初気になっていた定位感については、ソースによっては気にならなくなりました。また、ダクトの長さを90mmから60mmに変更することで超低域の強調が和らぎ、中低域との繋がりがスムーズになって聴きやすくなりました。このスピーカーは管球アンプとの相性が良いようで、人の声の再生が秀逸です(使用アンプは、プリがマッキントッシュC28タイプ自作、メインがラックスMQ80)。特に中高域に独特の艶があり、原音再生とは違う方向で極めて魅力的な音を奏でてくれます。
同価格帯の既製品を凌駕する個性
支払いから品物の到着まで結構 (2カ月ほど) 待った。
おかげで期待だとか要求のようなモノも相応に増した訳だが、組み立て直後の音出し一発目で期待通りの手応えがありました。
端的に言えば小径&複数ユニットのメリットの具現化ですね。
極小音でも非常にメリハリがあるし、音像に高さがあるので大画面モニターとの相性がとても良い。
エンクロージャーのサイズがそれなりに大きい訳だから、生み出す低音に関しては普通に想定の範囲内だったけれど、ある程度限られた音場の枠内での粒立ちやボーカルのライブ感は価格考慮で十分高評価に値すると感じました。
見た目は…お世辞にも美しいとは言えず、ちょっと滑稽な印象のスピーカーですが、音が気に入ったので目を瞑ります。
大変参考になります。
大変参考になります。毎回プリント・アウトして、分厚いファイルに綴じています。
まとまりがあって、素晴らしい!(追記)
1か月経過後(エージングが進み?)、低音の響きと閉まりが格段に、良くなってきています。特に、低音は、芯が入ってきたというような感じで、19年度のOM-MF519で作成したバックロードホーンを凌駕しているように感じたことから、評価を上げました。
ここからは、評価についてですが、個人の感想として、総合評価を単純に5段階というのは、簡単であるものの、かなり主観が入り、難しいものです。今後、検討してもらえるのであれば、高音、中温、低音と分けた評価とリスニングの部屋(洋室、和室、デッド、ライブ等)の分類を記述し、総合評価のポイントを5段階にすると、かなりわかりやすくなると思います?(測定器を所有していないので、単なる主観での評価ではありますが。)
低音の厚みだけでなく定位がよくなり臨場感が向上しました。
以前音響パネルAのみを購入して低音反射のためコンパネを裏打ちして低音の量感を増やして改善ました。
ここでスピーカ(DS-5000)の外側に置いて広がる音場感を取るか、内側に置いて安定した定位感を取るのか悩みどころでした。
今回音響パネルBをコンパネで裏打ちして長手方向に延長してスピーカの内側に置いてみました。
この結果、狙い通りに臨場感と定位の安定が得られとても満足しています。
本当は内側も幅をより広くしたかったのですが、中央の引き戸に行く都合上止むを得ませんでした。
臨場感と低音の厚みはフルオーケストラ(春の祭典)で確かめて,定位感はボーカルと室内楽で感じることができました。
小さな箱で驚きの低音の響き
15年以上前にAVアンプと共にそこそこの値段で購入したメインスピーカが、高音はいいものの低音域が期待したように出ないままで、うまく使いこなせないうちに片方が壊れてしまい、ずっとそのままでした。
最近になって、高音から低音域までよく鳴ってくれるスピーカーが手頃な価格でないものかと思い、
オーディオに関しては素人同然なので、インターネットで探していたら、偶然御社のサイトに辿り着き、自作する自信はないので完成品を購入しました。
ブラインドテストの結果やいろんなレビューを読んで期待はしていたものの、小さな躯体では限界があるのではないかという不安もありましたが、よく聞いていたクラシックをかけてみると、ピアノピアノソナタや協奏曲も低音域までバランスよく、クリアに聞こえて、おおっ、やったーという感じ。息子が持っていたJ-POPをかけてみるとベースの重低音感までバッチリあって更にびっくり。
フルオーケストラの交響曲では、多数の楽器が鳴る部分では、流石に少しアップアップして余裕がない感じがしますが、これまではそもそもか細い貧弱な音でしか聴けなかったし、この値段でここまで聴けるようになって、大変満足しています。
以前に購入していたYAMAHAのサブウーファーを繋いで、ハイカット周波数55Hzくらいでボリュームもかなり絞ることで、メインのバランスを崩さずに低音域の深みを出せないか、試したりして楽しんでいます。
私は長い間ソフトウエア技術者として品質・性能が最高のものを作ることにこだわってきましたが、
この価格でこのパフォーマンス、御社の音と技術へのこだわりが伝わってきます。
良いものをありがとうございます。
次の機会があれば、Z800-FW168HRとZ505-Trentoまで揃えたい、と思ったりしていますが、
肝心の手元のものが思い通りにはいかないもので、どうなることか。。。
素晴らしい。天国の長岡先生に届けたいですね。
素晴らしい。天国の長岡先生に届けたいですね。そしてわざと悪びれたつっこみコメントはどんなものなのか聞きたいです。
やりたいことはたくさんありますが、少しづつ試してゆきたいと思います。
昨年の試聴会以降、音工房Zさんのファンです。中古でV601+Markaudio OMMF-5を手に入たた昨年秋に私の音工房Z体験が始まりました。先週Z-Modena mkIIを購入し、V601に組み込もうと思っています。さて、今回のメルマガ記事も堪能いたしました。DIYが苦手で本格的な組み立てへの勇気が足りないのですが、小学生以来45年間のオーディファンとして、今回の記事のような内容をじっくり追体験しながら余生のオーディオ人生を過ごしていきたいとの思いを強くしました。やりたいことはたくさんありますが、少しづつ試してゆきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。