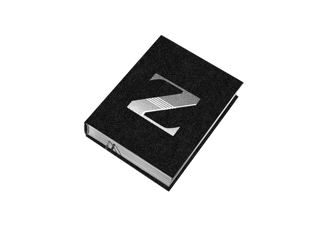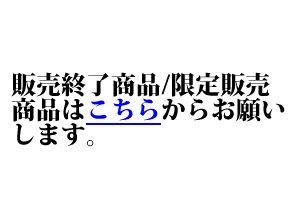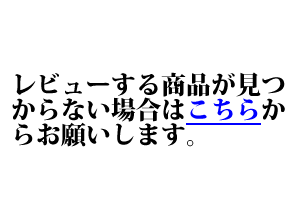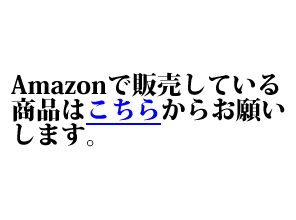レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
3日間に渡るmailのリンクより拝読させていただき、ありがとうございます。自作派にとって貴重な指針を得ました。
MJ誌2020/11で御社の記事を拝見して以来、市販の1/10のコストで製作というコンセプト(元は故長岡氏の?)に賛同しております。私の現用SPは10″ウーハー&72リットル密閉箱の上に1″ソフトドームを乗せた自作2wayです。これに対してサブウーハーで50Hz以下を補強したいと考えておりましたところ、御社の知見から、無理に大口径を使用しなくてもこの帯域を扱うことができる見通しを得ました。今後、追加のパワーアンプ、チャンネルディバイダ、そしてサブウーハーと、製作すべきものがたくさん見えてきましたので、会社をリタイアした今からボケ老人にならずに済むと安心した次第です。
なお、弊システムの写真につきましては、雑な工作が露呈してしまいますのでご容赦ください。
音場、音域の広がりが数段アップしました。最高です。
最近は、手のひらにのるデジタルアンプとラズパイのネットワークプレイヤー(NAS)で色々なジャンルを楽しんでいます。
今日はサブスクで【Z・CD紹介29】50 Ways to Leave Your Loverなども
効果抜群です
クラシック好きです、部屋がコンサートホールのようです、奥行き 広がりが出ます、スピーカー レクタングラーヨーク、アンプ ラックスマン38FD ターンテーブル プロジェクトX2 カートリッジ ゴールドリングエトス。
音のバランスが自然で素晴らしい。
アンプ(マランツ30n)NetworkSACD Player(SACD30n)で視聴しました。まだエージングが終了していませんが、音のバランスが自然で雑音がなく透明感があります。SPはヤマハ1000M、JBL4312G、DALI OBERON3、AIRPULSE A100 BT5.0を所有しています。SWで切り替えて聞いています。所有しているSPの中でも一番いいのではと思わせる素質の良さがあります。
Z-Bergamo これは買い!
本日納品でした。まず綺麗な外観。見た目も重要!とりあえず繋いで音を出したところベースがいい感じに、暫く聴いていると楽しくなってきました。最初からこれだけ鳴るのは初めてです。機材はカラオケ用のミキサーにクラウンD-150、何それと言うシステムです。ソースはウオークマンでスティーリーダン。しかしながら、あまりパワーは入らないようです。アベレージで1Wぐらいが無難かな?あっ部屋は約50畳でエアーボリュームがあるから、これは買いかも?に変更します。
Bタイプ1セットでも効果あり
Z1-Livornoを購入、音質は充分満足ですが、交響曲の音場感の向上と低音の締まりを目的に、Z103Bタイプを1セット買ってみました。部屋に余裕がないので最小限のセットで効果があればラッキーと思いながら試してみました。
・2枚を貼り付け左右に使う。
・スピーカー背面ではほとんど変化無し。
・スピーカー側面、斜めにセットしたら音場、量感が向上しました。(写真添付)
自分としては目的達成です。
ところが、スピーカー周りが良くなったせいか、Sony HAP S1 HD Playerの非力さが気になり始め、入口の改善を図ることにしました。
DENONのDACアンプは問題ないので、CDトランスポートCambridge CXCを購入しCDを視聴したところ、CDの音はこんなにも良かったのだとうれしくなりました。
Z1-Livornoの購入がきっかけで音楽の再生環境を大幅に改善できたことに改めて感謝、ありがとうございました。
自作ハイエンドスピーカー大百科事典
お世話様になります。製作記録を残す事は、今後の前進につながるので大切と思います。今後更なる発展する事を願っています。
追伸:12cmフルレンジを貴社のダブルバスレフ設計を応用して作成しました。ポート調整を念入りに行った結果最高の音質となりました。
一言でいえば「まあ良かった」でしょうか。
CDプレーヤー:マランツ SA8005 アンプ:PM8005
組み立て直後の音出し時は「普通」でした。補足をさせていただきます。
4月上旬に完成し先ず音出し初日の印象は5段階評価の3で、3日後には3から4の3寄り、3週間後には3から4の丁度中間、そして5月中旬には5段階の4になりました。
かなり真剣に評価したつもりです。ただ言えることはこのスピーカーのエージングは音出し直後と1ヵ月後では全く違う音でした。
そして更に言えることは、レビューを書かれている先輩諸氏の評価は5評価の方々のご意見だろうとお察しします。4評価の32%の方々の評価の根拠が知りたかったですねえ。私の耳が客観的にどんなものか気になっています。
以前から申し上げておりましたが、私は低音大好き人間です。自分の気に入る音は低音が豊かに出ているかどうかが決め手になります。中音、高音がよく出ていても低音が出ていなければその音は私にとって気に入らない音になります。
このModenaというスピーカーは低音を別にすればよい音を出しますね。幾分高音がキンキンしますが、多分このキンキンは好き嫌いが分かれるところでしょう。初めての音出しから丸3日ほどは嫌なキンキン音でしたが、その後次第にいい意味での、つまり聴けば聴くほど嫌味なキンキンではなく心地よいキンキンに変化してきました。4月上旬以降毎日このスピーカーでCDを聴いています。
低音も初期に比べれば比較的鳴るようになってきました。比較的低音 が出るようになったことと高音の嫌なキンキンが心地よいキンキンに変わったことで評価が3から4になったという次第です。かなり真面目に聴き込んでいます。
完成直後の初めての音出しで「ん?なんだこりゃ!」が第一印象で、何か大きな間違いをしでかしたのではないかと思い、慌てて大山様にメールで確認させていただきました。ターミナルの+と-をつけ間違ったのではないか?とのご指摘でした。そして大山様のご判断では+と-を正常につなげば低音の出方が明らかに違うので直ぐわかるとのお話でした。私は自分の耳を疑いました。+と-を付け替えても差は感じられず、再度+-を付け替え、結局元のままで聴いています。このターミナルの端子の+-が正常でないかどうかは低音ではほとんど感じられず、正常でない場合は何か不自然な、気分が悪くなるような音でなじめない音でした。
初めての音出しで、豊かな低音が出る?先輩諸氏のレビューにも書かれてましたが、初めての音出しでびっくりするほどの低音が出るって、どんな耳をされているのか?ダンボみたいな耳の持ち主かな?皮肉っぽく言うつもりはありませんが。
また他のレビューでは、重低音がよく出るとのご評価もありました。
私には信じられません。ヤマハスピーカーのNS-1000よりこの8センチModenaの方がよく低音が出る?この言葉も信じられません。
念のために大山様にお尋ねします。
エンクロージャー制作で大事な点の一つに気密性があります。どこか空気の漏れがあるとして、その場合「スカスカの音になる」とのお話でした。このスカスカの音とはどんな音でしょうか?もう少し具体的な表現で教えてください。
私の場合、スピーカー自作は初めての経験で、慣れない手つきで何とか仕上げたものの最初の1本目は接着でちょっと失敗し、隙間ができたため隙間はボンドで充填し、出っ張った部分は荒いペーパーで段差をなくした、という経緯があります。このトラブルで、ごく僅かの隙間が残っていたなら低音再生に影響があるはず、と当時は考えていましたが、2本目は慣れも手伝いましてスムーズに制作できましたので、結果として2本のスピーカーでの低音の出方による差は感じられないので共に漏れはないのではないか、と思っているのが現状です。
更にお尋ねしたいのは吸音材の件です。
吸音材をどれだけ詰め込めばいいのか自分では判断できません。かれこれ10回くらい試しています。完成直後の音出しから1週間ほどは組み立て時にご指定箇所に同梱の吸音材をボンドで半分ずつ貼った状態で聴いていました。
1週間ほど経ってから吸音材を多くしたり少なくしたりを繰り返して試していますが音の違いは余りはっきりとは判らず、今は多めの状態です。基本的に吸音材をどの程度詰めればいいのか?が判っておりません。大山様は確かメールで、多めにかなり目いっぱい入れている、と言われていたと記憶しています。その言葉を信じて私も多めに入れています。
つまり吸音材を沢山入れることで音がまろやかになる?という方向にしたいのです。
大山様のお言葉では、入れ過ぎると低音の減衰が生じる、とのことでしたので低音大好き人間としましては低音には影響がない範囲でまろやかさがMAXになるときの吸音材投入量が知りたい、というご質問です。
大型のエンクロージャーではありませんのでぎゅうぎゅう詰めと言ってもたかが知れてますが、押し込めばまだまだ入りそうですが、どの辺で止めればいいのか加減が判りません。改めてまろやかさを求める場合の吸音材投入量をご指示お願いします。
書きたいことがいろいろあって、メールが長くなりすみません。
このZ701-Modenaのフルレンジ1発の最大の良さはヴォーカルの生々しさでしょうか。確かに中央にくっきり声が集まります。セパレーション、楽器のクッキリ感なども文句なしです。また、ボーカル以外の左右の楽器やギター、ドラム、拍子木などのコーンという特徴的な音などもクッキリです。低音も徐々に出るようになりましたが残念ながら私にとってはまだまだ不十分で、今後このZ701にサブウーファをプラスする方法などのご教示を得ようと心に決めておりました。
しかし低音が不十分でもですが、例えばマンション生活などで夜中に音量を控えめに音楽を楽しむ時などは申し分のないスピーカーと言えるでしょう。
フルレンジ8センチの割にはよく低音が出る!というのも過去経験したことがありませんのでうまく適切な表現ができません。例えば、携帯型のちょっと大きめのラジオや昔からあるラジカセなどの機器に使用されているスピーカーって数センチ程度のスピーカーでしょうか?そういった携帯の機器に比べればこのModenaはよく低音が出ます。
丁度、完成から1ヵ月程度過ぎたころに発見しましたが、このスピーカーはCDを選ぶなあ!ということです。簡単に言いますと低音の出ないCDは全然聴く気になれず、しかしCDによっては大型スピーカーとの比ではないものの聴いていてストレスを感じないCDも結構あるなあ!と実感できるようになりました。
爆音で楽しむのではなく少し抑え気味でさらっと気分よく聴くには持って来いのスピーカーシステムです。
もう少し私なりの感想ですが、この1ヵ月半くらいの間で聴いたジャンルで申し上げれば歌謡曲は五分五分で何とも言えませんが例えばタンゴはコンチネンタルよりアルゼンチンタンゴがよく鳴ります。ラテン音楽もいいですね。70年代~80年代のJ-POPも大体鳴ってくれます。
1曲だけ具体的に申し上げます。昔の歌ですがダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコス」なんかはハッとするくらいのエレキの低音で、おやっ、スピーカーを間違えたかな?と思わせるような鳴り方です。騙されたと思って一度だけこの曲をZ701で鳴らしてみてください。強引ではありますが大山様の耳で確認して欲しいのです。どうぞよろしくお願いいたします。
イージーリスニングでは大編成になるほど相性がよくなく小編成ほど聴きごたえがあると思っています。レーモンルフェーブル楽団よりポールモーリアの方がウキウキ感がありますがマントヴァーニも様になりません。リチャード・クレイダーマンもなかなか乙なものです。
小編成と言えばジャズもトリオ~クインテット辺りはじっくり聴くことが可能です。8センチにしては思っていた以上の音量で楽しめますが、私の使用しているアンプでは時計の位置で10時か10時半くらいがギリギリ聴ける音で、あえて9時くらいなら親しい友と話をしながらでも楽しめるのがジャズです。このことは大型スピーカーのボリュームを極力下げてBGMとして聴くのとはちょっと違う音の出方で、小音量であってもハキハキしていますので、それが心地良い音で聴けます。
私のレコードやCDの約70%くらいはクラシックですがZ701でのクラシックもこれで良し、っていう場合とやはり大型にはかなわないなあ、とついついつぶやいてしまうのと両方あります。オーケストラの交響曲や協奏曲では大型スピーカーに軍配が上がりますがちょっと控えめボリュームでは互角に戦える素質があるように思えます。
最後に、低音大好き人間としての願望ですが、比較的最近に大山様へメールで確認させていただいたその返信で、Z505-Trentoは販売と中止、との報を受け、目の前が真っ暗になりました。実は、低音の不足はこのサブウーファと組み合わせれば自分として納得のいく低音が得られるのではないか、とひそかに期待していたのです。現在、次期モデルを開発中とのことですがZ505-Trentoに比べてどんな音を目指されるのか、また大体いつごろの完成でいつ頃の販売を予定されているのかもものすごく気になります。一日も早く完成され販売されるよう祈るばかりです。かなり高価なサブウーファでしたので開発後の新商品もできる限り値上げなさらないよう今のうちからお願いしておきます。
さて長くなってしまいましたが、Z701-Modenaの私の評価は「まあ良かった」ですが、期待していたほどの低音は8センチを考えれば止む無しですがそれ以上にCDによりけりではあるものの優れた求心力を持つスピーカーであることは先輩諸氏が口を揃えて認めているとおり素晴らしさに満ちています。ちょっとした効果音的な音がクッキリ聞こえたり今まで気づかなかった楽器の音が鮮明に鳴ったり、またそれが力まずに素直に出てくるんですね。参りましたよ!
でも私は低音が好き。9時のBGMより10時か10時半の爆音で将来は聴きたいのです。そのためにも一日も早い次のサブウーファを待っています。
この私の気持ち、お忘れにならないようお願いしておきます。
最後の最後にもう一点だけお尋ねします。
大山様にとっては昔憧れていたというJBLのS9800とご自分でお創りになった最高級ユニットのZ800-FW168HR+Z505-Trentoと比べるとどちらがより良い音でしょうか?音には好みがありますのでずばりの答えは出しにくいでしょうが、S9800は私も憧れていました。しかし余りにも高価なため所詮は高嶺の花で、私は追っかける勇気もなくS4700で我慢する選択肢を選びました。最近ネットでS9800を検索したところ大山様の記事を見つけてしまいました。私以上のベタ惚れ記事でした。今ならどちらの音が大山様の望まれる音でしょうか?低音だけ取れば両者で大きな違いは感じられませんでしょうか?低音の差が感じられるなら是非教えてください。将来の参考にさせていただきたいものですから。
酷な質問で失礼しました。
今後とも音に関する様々な悩みに対し、ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。
大変参考になりました。
部屋とSPのセッティングと聴取位置に関する解説は大変参考になり有難うございました。音源をCDに変えてからず~っと試行錯誤を繰り返していましたが、漠然とした実感と一致する部分が多く有りセッテイングが非常に重要だという事を改めて認識しました。この大百科事典をもう少し早く見たかったと思うほどです。今回のレポートを参考にして、さらに気に入った音を手に入れる事が出来るように試行錯誤をして行きたいと思っています。
終の棲家の終のスピーカー
下の娘が入籍して出ていき、1年前に妻と二人きりの「終の棲家」を普請することを決め、3月に入居しました。4畳半ですが念願の書斎兼リスニングルームを確保できました。STEREO誌を見ながら38年前に組んだ長岡さんの20㎝一発BLHは、引っ越しを繰返したため満身創痍のうえ最近は油が抜けたのか合板の剥離が進み、しかも38年物のFOSTEXが劣化したのかキレがなくなっていたため、この際「終のスピーカー」の物色を始めました。ネットで見かけた音工房・大山さんのコンセプトに共感、去年に先ずはZ800-FW168HRを購入して組みました。軽度の難聴のうえ加齢で高音が聞こえなくなってきたので20万円の価値があるほどの違いが判るか不安でしたが、BLHでは聞こえなかったホールの残響がきれいに聞こえて感激!低音もコントラバスの締まった余韻が美しい!バッハの部伴奏チェロ組曲、バイオリン組曲やビヴァルディの調和の霊感は、在宅勤務で仕事しながらでも邪魔にならず小音量でよくかけますが、夜はウイスキー片手にダイアナクラールや中溝ひろみのジャズボーカルで癒され、酒が進むと何でもござれ、シベリウスやバルトークからジェフ・ベックやピンクフロイド、メンアットワークまで。システムは、YAMAHAの質量15.5㎏のAVアンプとCDデッキ、そして38年物のDENON DP57M + Audio-Technica AT7Vという、アンティークなるもハイCPな構成。(「ハイCP」という言葉は、長岡さんの発明かも知りません。)ソースはCDとLPだが、一応音質重視の録音。
昨年秋に「Z505これが最後」というメールをもらい、衝動買いしてしまいました。Z800-FW168HRは小型で完成度が高いと思っていましたが、9年の歳月をかけた(ほぼ)専用のウーハーとのこと、Z800に合わせて悪いわけないじゃん!ちょうど、地震でZ800ごと転倒しにくいスピーカー架台を探していたことでもあるし、ちょっと贅沢なアドオンをすることにしました。アンプに2出力あるので、チャンネルAにZ800、チャンネルBにZ505 を繋いで、ソースとその時の耳の聞こえによってA+BかAのみで聞いています。Z800だけでも低音は十分な気がしていましたが、これにZ505を加えると、低音の量もですがスピード感が良くなるようです。逆相接続+Z800密閉化で聞いています。Z505は組み終わってまだ1週間ですので、今のところのインプレッションはこの位です。なお、Z800もZ505も今のところ時間がなくて仕上げてないので積層合板むき出しです。バッフルの面取りは意匠的にも良いと思うのですが、断面の積層合板感は私の趣味には合いません。潰し塗装ができればよいのですが自信がなく、ウォルナットの突板を仕入れたので、夏休みにでも突板で仕上げる予定です。
組んでみての感想は、
① クランピングは手早く慎重に根気よく:ダボの加工精度も高く組みやすいが、接着後の圧着には気を遣う。ハンマーで圧入しても隙間が残ることが多く、特に作業した日は室温が20℃あったためか、タイトボンドが短時間で粘度増加して硬化し始めるようで、もたもたしていると隙間が空いたまま固まる。根気よく全部のクランプを締め上げた結果、最終的には目立つ隙間は無く仕上がったが。特に前面の天と地の稜の部分は、面取りしてあるのでクランプ力が旨く伝わらないので要注意。Z800のように、楔を使ってクランプした方が良いかも知れない。また有りったけのクランプを全部動員しても隙間がどうしても埋まらないことがあり、この時は焦った。クランプを斜めにかけて、より長い部分にクランプ力がかかるように工夫したら何とかなった。
② バッフルの大きさ:バッフルが音道より0.2㎜ほど大きくカットされているのは良いアイデアだと考える。組んだ後にバッフルの面取り部分をsしサンドで落として、音道と段差なしのきれいな面取り面に仕上げられると思う。実は去年組んだZ800ではサブバッフルがバッフルより若干小さく、バッフルとサブバッフルの間に最大で0.2㎜程の段差が生じてしまっていた。仕上げの前に0.2㎜厚の木口テープを貼ってツライチにするか、パテを薄く盛ってツライチにするしかないと考えている。Z800のサブバッフルもバッフルより大きめにカットしてあれば、作業は簡単だったと思う。音工房様、ご検討ください。
最後まで読んでくださって有難うございます。
納得できる響きが気に入っています
いつも興味ある記事を配信していただき、楽しみにしています。
小口径SPの良さが気に入り、8cmSPでは御社のキット3台と自作2台を作成しました。
最もお気に入りは初代のZ701-Modena(組立誤差2mm以下で作成)ですが、200Hz前後の響きが気になり、9素子イコライザーで好みに合わせて使用しています。
今回10cmモデルの記事を見て、低域の厚みに期待し購入に至りました。
公称口径面積比で1.5倍は納得できる結果でしたが、聴感上の高域特性が老人の耳に届かなくなり、御社のツイーターキットを1μFに変更し追加しました。
現在はバランスのとれたModenaと、バランスに加え低域の厚みを増した今回キットを併用して楽しんでいます。
私は物作りと音楽が趣味なので、オーディオ的にはつまらないレビューですが、日頃の御礼を兼ねて投稿させていただきます。
脅威のコストパフォーマンス❗️
音に関してはど素人ですが、過去に見よう見まねで3台ほどスピーカーを製作しました。B&Wの低音を聴いて今まで聞いていたのは濁った低音だったことに衝撃を受けました。それ以来、いつかはB&Wを買おうと考えていたところ音工房の図面に出逢い、1万円でしかも8センチフルレンジが300万円のスピーカーに勝つとは言い過ぎじゃないかと思いながらも作ってみようと思い立ちました。
出来てびっくり、その音の凄さに衝撃です。8センチの小型スピーカーからこんな音が出せるとは。期待していなかった低音もかなりスッキリしていてB&Wと並べて聴き比べしたわけではないですが、記憶と比べてもそれほど劣っていないような気がします。私のポンコツの耳では充分なレベルの音になりました。
音質がすばらしいです。
今まで音工房様のスピーカー購入はZ1-Livornoを含めて4種類になります。最初の機種はバックロードホーンでこれは私の作り方が悪かったせいもあって低温がこもってうまくなりませんでした。この後しばらくスピーカーを作る気になれなかったのですが、BHBSというタイプのスピーカーがあることを知り作ってみました。機種はZ701-FE103 solでした。制作するのはけっこう大変でしたが、音は前のに比べて格段によくツイーターを足して聞いておりました。私の聞くジャンルは主にクラシックでちょっとジャズを聞いたりしていて、このスピーカーで満足していたのでもう作るつもりはありませんでしたが、家内がBTSを良い音で聴きたいと言い出し、今のスピーカを譲ることにしました。またちょうどクラシックに良いスピーカーのことをメールで見ましたので今回Z1-Livornoを作成してみました。制作に関しては箱が小さいことと、ダボ付きであったので非常にスムースに作ることができました。そして音ですが、全体に音が澄んでいて低音はキレが良く重厚で大変満足です。小編成のバロック、ピアノ・ソロなんかは演奏の場所にいるような没入感があります。本当にこのスピーカーは購入してよかったと思っています。
標準の1μを1.6μに変更してベストに
私のスピーカー構成は特殊で、Z800-FW168HR型を中心にして、低域にFW168HRを500㎐以下で追加し、さらに中域にケプラーコンのMonacor 13cmウーファー( SPH135KEP)を追加してサンドイッチ状に使用しているものです。FW168HR2本をZ505-Trentoのような同一ボックスにし、13cmとツイーターを別のボックスに入れて逆さまにセッティング。これにZ501を載せた形です。1.6μとすることにより、素晴らしい効果が出て、超高域から中高域、低域までも見事に生き生きと再生させてくれます。
コストパホーマンス最高
初めてのスピーカー製作でしたが、容易に仕上げる事が出来ました。
また、塗装については、木工塗装動画セミナーで、自分では上手く塗れたかなと思います。わかりやすく、動画の中での用具、塗装用品の紹介もあり、初めて作製する者には参考になりました。ただ、刷毛等は持ち合わせの物でしたので刷毛の筋等が少し出て気になりました。肝心な音に関しては、想像以上の出来映えではないかと思います。
同じタイプのONKYO D-412EX と比べて中低音が良い出来映えかなと思います。
Z800-FW168HRとの相性が抜群!
Z800-FW168HRと組み合わせ3way化すると、のびやかな低音はもちろん、高音の伸びも感じられ満足するスピーカーシステムになってます。
最近エージングも進んできて音楽をますます楽しんでいます。主に聞く音楽はクラシックで、室内楽の弦楽四重奏では、ヴァイオリン、ビオラ、チェロの四つの楽器の分離がわかって定位のすばらしさを感じます。大編成の管弦楽では、金管楽器特にホルンの音が素晴らしく、また打楽器のトライアングルやシンバルの音も冴え冴えと聞こえます。
再生機材は今のところMarantzのM-CR612ですが、CD、FM、ネットラジオを楽しんでます。これから、できる範囲で機材を充実していきたいと思います。
ただ、難点を言うと、Z505を製作するにあたり、その大きさと重量に年配の私(69歳)としては大変でやっと製作できたというのが本音です。しかし、製作できてうれしく思います。
大変なノウハウの無料公開に驚きました。
RPIとDACでハイレゾの室内楽を聞いています。手持ちの古いスピーカーとA級再生のできるアンプで聞いていますが小型の良いスピーカーに興味を持っています。木工の道具類は手持がありますので、公開頂いたノウハウを勉強させて頂き、自作に取り組もうと思っています。
まさに、ハイエンド
数年前から、こちらのキットの購入を検討しており、やっと買えました。
fostex GX100 を使用していたのですが、比較すると・・・
いや、比較にならないくらいの歴然とした差を感じました。
簡単に言うと、GX100を大きく鳴らすと、音が歪んでくすんでしまいますが、Z800では、まったく感じません。
解像度が高く、楽器それぞれの音をしっかりと鳴らしてくれます。
音の表現、好みに関しては、アンプやDACで変わるので割愛しますが、
これだけのものだと、それなりの物にしたくなります。
個人的にはソウルノートA2とハイエンドAVアンプが欲しくなりました。
兄が以前使ってた70万のスピーカーと比較しても負けてなく、それ以上(環境やアンプは雲泥の差なのに)と感じました。
塗装は水性うるしで仕上げました。手放すことはないので、雑な仕上げです。
組み立てて感じたことは、スピーカーケーブルの皮むきは、大山さんが使ってるのと同じものを使うことをお勧めします。
電線用のワイヤストリッパーでは、より線を切ってしまうことが多く、工具とケーブルを買い直しました。後、はんだは、音楽専用のを使い、こては、温度が400度以上になるものを使用した方がよいです。
最後に、この値段で販売してくれてる音工房Zさんに感謝しますし、本当にお勧めです。
口径を意識させない雄大なサウンドが
【Z1000-Bergamo】
この新しいBHBS(バックロードバスレフと名付けられている)の試聴会でしたが大変面白かったです。
HPやブログの方に詳しく解説がありますが口径からすると考えられないようなサウンドが出てきます。
特注ユニットとこの特別なエンクロージャーで雄大なサウンドが出てきますね。
仕上げも非常に美しいです、敢えて問題点があるとすればユニットのサイズからくる耐入力でしょうね。
大きなパワーを入力すると壊れるかもしれませんが、あまりにも充実した低域が出てきたのでついつい音量を上げてしまいましたがその時は大丈夫でした、つまり出てくるサウンドからはサイズの事を意識しなくなるという事です、それくらいインパクトがありました。
比べると13㎝2wayのZ1-Livornoはごく普通に聞こえました、比べると地味な感じでしたね。
比較せず単体で鳴らしている分には美しいサウンドが聞こえてくると思いますが、比較試聴するとこのBHBSより能率が低いため少し地味に聞こえましたが、音量を合わせながら聞くと最初感じたほどの音質差は感じなくなりました。
それでも低域の伸びや質感、量感はZ1000-Bergamoの方が遥かに優れているように聞こえましたね。
今回試聴会に参加した目的にZ1-Livornoを再度試聴してみたいという理由もありました。
前回参加した時にそのサウンドが気に入ったので13㎝のウーファーであれだけのサウンドが出るならという事で同じ口径のウーファーを持ったものを自作してみました。
バスレフの最適容積はどれくらい必要かという事を念頭に検索してゆくとQts0.3前後のユニットを使った物で最大平坦を目指すというサイトにたどり着き制作してみたところ思いのほか低域が下に伸びたものが出来たので比較試聴したいとう邪な考えが思いつき参加させていただきました。
持参したソースでZ1000-Bergamoと自作の物を比べる(自作品は自宅で試聴環境が違う)といい勝負をしているという印象を持ちました。
13㎝ウーファーのバスレフでこれだけの低域の伸び、量感、質感が得られるなら、音工房Zがあれだけの試作や試聴を繰り返して製品をまとめ上げるなら13㎝のウーファーのバスレフでもZ1000-Bergamoに匹敵するようなシステムが作れるような気がしてなりません。
脱線しましたが今回の試聴会で色々なサウンドを聴き比べる事が出来、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
期待に違わない驚愕の性能でした!
1. 視聴環境と購入の動機
Sony HDD Audio Player HAP-S1(2THDに換装、主にCDリッピングで3万曲収納)→ DENON DA-310USB ヘッドホンアンプ→パワーアンプNobsound中華製→スピーカーDALI Zensor-1
50年代Jazz、新しいものではPiano Trio、Vocal中心で満足していましたが、最近クラッシックを聴き始めたところスピーカーの力不足に愕然。交響曲は貧弱、Violinの高音は耳障り。替えるしかないと10万円以下で物色しましたが買えば後悔するリスクが大きいと感じ悩んでいたところネットでZ1-Livornoを発見。確信できたので3/30即注文、翌日到着、親切なキットで作りやすく1日で完成、これまで調整をしてきました。
2. セッティングの苦労と音質の感想
ユニットの質の良さはすぐわかりましたが、低音は出るものの不自然、また強い音が濁る時があったり、これはセッティングの問題なのだろうといろいろ試しました。最終的には、昔買ったYAMAHAのガタつかない重みのあるスピーカー台にわりと重厚な単板を密着させその上にスピーカーを直置きすることが最善となりました。インシュレーターをはさむと全然だめで直置きが良いのは不思議です。
音質の感想ですが、音の明瞭さ、立ち上がり、楽器の分離、音場、厚み、立体感、演奏の表現力などZensor-1をはるかに凌駕しました。サイズと価格からすれば驚きの高水準です。
3. スーパーツィーターの追加と大きな効果
スーパーツィーター無しでも充分ですが、Violinの高音再生がより良くなるのではという期待で、価格も手頃だし、4/13にキットを購入しました。0.82μFコンデンサーで繋がりも問題なく、Violin Concertoの高音の綺麗な伸び、見事です。スーパーツィーターが乗っかっていることで見た目も良くシステムの拡張感があって気分良く聴けます。
4. 感謝
昔、FE103で正方形のバックロードホーンを何本か作ったことがあるので、自作の有利性はわかっていたのですが、今回このような素晴らしいキットを提供いただけたこと、そして大幅なグレードアップができたことに感謝です。クラッシックの再生が目的でしたが、このスピーカーはどんなジャンルでもOK、保有している古い音源が蘇った感じで、いろんな曲を改めて楽しく聴くことができ嬉しい限りです。あとは塗装で見映えよくしようと思っています。本当にありがとうございました。