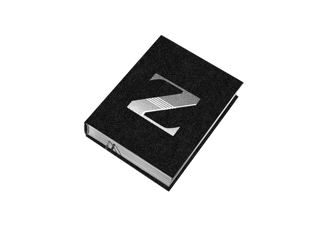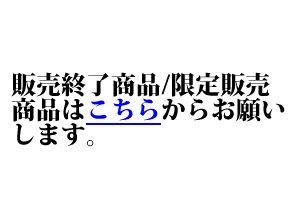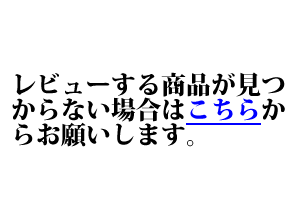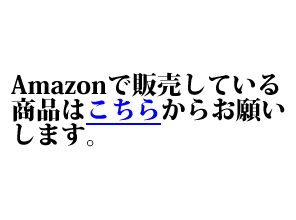レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。
現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)
フュージョン系ニアフィールドスピーカー
【Z700W-OMMF4MICA】
Z700W-OMMF4MICA(Wスピーカー、シングルスピーカー)、Z1-Livornoキットの比較試聴会です。「音場感」というワードに惹かれて参加させていただきました。
当初、ソースがフラメンコやフュージョンばかりで、その際はZ700W-OMMF4MICAのWスピーカーの効果覿面。確かに鮮鋭さではシングルだけれど、音の豊潤さの違いは歴然。有無を言わさずWに軍配。一方、Z1-Livornoと比べると大口径の差か、Livornoの余裕感が如実に現れた。Livornoはホールで、Z700W-OMMF4MICAはコンパクトなライブハウスで、といった鳴りの違いが顕著だった。私が持参したソースはチェロのソロとオーケストラだったが、チェロは広がり感では劣るもののLivornoのもたつきの方が目立つ結果に。そしてオーケストラは物足りなさが。
総評としては、「コンサートホールのような壮大な音場空間」ではなく「ライブハウス感」であり、クラシックよりフュージョン、といった印象。私が過度に「音場」を期待しただけに「?!」でしたが、気軽に元気な音を楽しめるし、スピーカーの増減や前後入れ替えなど、楽しみに事欠かないセットだなという印象です。
素人の僕でもわかりやすい文章で助かりました
レポートを参考に作ってみようと思います。
ありがとうございます。
Z700W-OMMF4MICA 前後にユニットを配置した音の広がりは面白い
【Z700W-OMMF4MICA】
前後から音が出るという面白いシステムに興味を持ち、12/17の試聴会(13時~)に参加しました。
試聴会では前側にOMMF4MICAが、背面にZ-Modenaのユニットが完成品版に装着されたものと、背面を塞いで前面にOMMF4MICAが付いたキット版の比較ができました。
OMMF4MICAのキャラクターが高域強めで元気のいい、明るくキレのいい音なので好みはここで決まります。私は好きな音です。
前面だけのOMMF4MICAシングルではそのキャラクターが際立ち、音像の定位もよく、6cmユニット1発とは思えない低音を聴かせてくれますが、背面にZ-Modenaを追加した方を聴くとしっかり低音が出るので1発の方は少しもの足りなく感じます。
では肝心の前後配置でどういう聴こえ方だったか。
定位をあまり気にしない音源ではふわーっと広がる感じの音場が魅力的で、前1発に切り替えると寂しく感じます。
しかしふわーっと広がる音場は臨場感のあるものではなく、効果音的な感じで音像定位は1発シングルより後退します。
この効果音的というのは昔流行ったDSPでコンサートホールの雰囲気を出すような感じです。
「臨場感」と言ったのは、後述するコンサートライブの音源で残響音がホールの端の方に消えていくような空間を感じるとか、本当に目の前で歌っていると感じるようなリアリティを含めてのことで、そういう臨場感を感じるスピーカーや音源は多くありません。
一つ懸念しているのは背面から出る音は背面の環境(壁との距離や置いてある物など)の影響が大きく出て、設置環境次第で変わるのではないかということ。
背面ユニットの効果を自在に調整できれば定位感や音場感を好きなようにできるので、背面ユニットの音量を調整できるアッテネーターかあるいは物理的な減衰器があればいいなと思ってしまいました。
或いは背面はスコーカーの低域カット程度の時定数で、中高域だけでもいいかもしれません。
持ち込んだCDとその印象は以下です。
——————————————
1.鬼太鼓座の「三国幻想曲」
これは試聴会で毎回使用しますが、大太鼓の鳴り方で低音の質をみます。
悪くない、けどやはり6cmユニットなので腹に来るほどではありません。
2.玉置浩二 2015年旭川コンサートライブの「しあわせのランプ」
このCDは我が家のFE103をダブルバスレフで作ったスピーカーではギターの弦をはじく音やボーカルが極めて生々しく、残響音はホールの隅に消えていくような空間を感じる優れた録音です。
残念ながらそういう臨場感は前後にユニットを配置した方で感じることはなく、前面だけの方でもあまり感じませんでした。
或いはOMMF4MICAユニットが原因かもしれませんが、このCDの音質の良さを全く感じなかったのが気になります。
ちなみに我が家ではZ-1でもこのCDの録音の良さを表現できています。
3.聴きなれた女性ボーカル、カーペンターズのNow and Thenからマスカレード
ユニット(OMMF4MICA)のキャラクターがわかります。
キレのいい元気な音、残念ながらふくよかさや声の色気は表現してくれません。
——————————————
以上はあくまで私の印象です。
ひょっとしたらJazzなどは得意なスピーカーかもと後になって思いましたが、今回Jazzの音源は試していません。
Z700W-OMMF4-MICAは演奏者から聴きえる音に近いかも…
【Z700W-OMMF4MICA】
12月17日の13時の試聴会に参加させて戴きました。
当日のスピーカーは1番に完成品の後ろにModenaをつけたもの、2番にキットの後ろに蓋をつけたものがセットされていました(当然ながら前側はMICAがデフォルトですが…)
音工房さんが準備されていた音源では非常に反応の良い点が理解することができました。
しかしながら音源の編成が多い訳では無いので音色の基準になる自分の知っている音が探れないのでハイあがりを強く感じる事は無く、2番の後ろ蓋のほうが少し弱い程度で、1番が良さそうだなといった感想でのスタートとなりました。
各自持ち込み音源を鑑賞する時間帯となり、他の方の音源でカーペンターズを聴かせて頂きました。
当時まさにオンタイムで散々聴いていた名盤ですから耳がしっかり覚えております。
その記憶と比較しますと定位的には2番なのですがかなりハイ上がりでカレンの胸声アルトには聴こえませんでした。
1番はかなり良いのですが定位的には少し?が頭の中に巡ってしまいました。
自分の持ち込み音源の際には2番のスピーカーをBergamoのキットに替えて貰いました。
1つ目はボブミンツァーのビッグバンドでDMPレーベルの前に東芝EMIで出したThe Horn Man Bandの
「I Hear A Rhapsody」で鑑賞しました。
こちらの曲はDMPのステレオマイク1本撮りでは無いですが1番スピーカーは見事な再現をしてくれました。
自宅のZ701-OMMF4でも良い再現をしていましたが、それよりも良い場面も感じられました。
感じとしてはDMPレーベルの宙吊り1本マイクを取り巻いたホーンセクションの音源を散々聴いていますので、その回り込んだ音にも近い感じですがそんなに回り込んではいなくて…中で一緒に演奏している感じも少し致しました。
途中で2番スピーカーに換えましたがボリュームを2目盛上げて聴かせていただきました…今回のスピーカーの能率の良さも比較してわかりました。2番も良かったですがビッグバンドを愉しむにはレスポンス、楽器の分離性で今回のMICAかなりおすすめだと思いました。
2つ目はゲイリースマリアンのバリトンサックスのコンボによるライブ「Cindy’s Tune」で鑑賞しました。
各楽器の音色を確認する為でしたが全く不安がございませんでした。
音工房さんの開発ブログを見る前に当方でも7.5リッターのバスレフ箱にMICAを入れたりZ701-OMMF4に入れたり下半分にMICAを入れたり試してみましたが、MICAは能率が良い点とハイ上がりなので、入れ換えを繰り返すと元気の良い点が気になってしまい金属のOMMF4がかわいそうになってきました。当時金属のOMMF4は凄いと思いましたが…。自宅にてMICAのハイあがりを解消するには至らず、Z701-OMMF4の下半分にMICAを入れてコンデンサーを色々試しています。
ビッグバンドを愉しめるものを探していましたので強く購入に向けて傾いております。
今回のキット購入にむけて当方の現実的な利用法ですが…フロントは当然MICAで、リアは余分にある金属のOMMF4にてスタートすることになると思います。バーチのサブバッフルか3Dプリンターによるサブバッフルが市販されていますが本体に鬼目ナットでModenaの穴をあけておいてサブバッフルの穴を45度ずらせば穴位置1ミリ差を回避できるものと考えております。
ゆくゆくはModenaも買って愉しむ予定でありますので鬼目ナット問題と穴差1ミリ問題は重要と考えております。
この度はZ700W-OMMF4-MICA完成おめでとうございます。
初めての2ウェイスピーカーです
Z800-FW168HR組み立て記
組み立て
仕事の合間に組み立てたので、組み立てに1か月かかってしまいましたが、やっと完成しました。
精巧なパーツと木工用クランプにより、すんなり組み立てることができました。
木工用クランプで締め上げるとボックス中央部の締め付けが甘く若干隙間があるので中央付近に10cmx5cmのコピー用紙6枚を挟み、中央部を押し付けて隙間ゼロにしました。
はみ出したボンドは直ちに濡れ雑巾で拭き取りました。
音出し
音出しの慣らし運転をして2週間が過ぎました。
いろいろなジャンルの曲を聴いています。
我が家の従来の2アンプ3スピーカーシステムとは異なるサウンドです。部屋も14畳間ではなく6畳間に設置したので音が変わるのは想定の範囲です。
14畳間では曲目によっては低音や超高音に物足りなさを感じますが、6畳間のイージーリスニング用なのでこれで十分です。
6畳間ではSTAXのコンデンサーヘッドホンを常用していますが、これからはZ800の出番が増えるでしょう。
この2ウェイスピーカーはバイワイヤリングなので、バイアンプで2つのスピーカーを鳴らすことにチャレンジしたいと考えています。
2022年12月15日
使ってみて "あゝ、びっくりした" の連発!
Z103を2枚購入し、音がどう変わるか早く知りたくて、塗装後回しで先ずはフロアータイプのJBL s4700の後に左右1枚を後の壁と平行に並べて音を聴いてみた。
そしたら、何としたことか出てきた音が2~3割大きな音で、慌ててボリュームつまみで調整し、その後音色がどう変わったのか聞き入ってしばらく席に張り付いてしまった。
私の一番気にしていた低音の出方が一気に倍位に膨れ、メリハリが明確になった。
明確に違う音が…いとも簡単に!
Z103/Bタイプを購入し、Aタイプに続き2度目の購入だったが開梱してびっくり。
何に驚いたか?
木の色が随分白かった!
木の材質はパイン材であったた。ちゃんと商品欄にも書かれていた。しかしクリアーでも少し沈んだ色合いになるだろうからまあいいや、と次に進むことに。
やがてタイプA同様にオスモカラーウッドワックス エキストラクリアーで塗ってみた。
キレイに簡単に仕上がった。が、色合いが随分白い!!
次回購入時は少し色が付いている塗料にしようと決めていた。
そしてしばらくして、今度は再度チャレンジしてみようと追加でBタイプを再購入した。
今度こそと意気込んで着色オイルを購入した。
今回はワトコオイルのミディアムウォルナットに決めた。
最初に裏面及び周囲木口より塗り始めた。速やかに簡単に塗れて色合いもグッド、内心これでよし!とほくそ笑んだ。しかし歓びはここまでであった。
その後、表の乱反射面を細めの刷毛で丁寧に塗り始めたが中央近くになれば溝が段々深くなり、凹面は難なく塗れるが溝の側面は簡単には行かず、結果として何回も刷毛でなぞることになった。
こうして何とか出来上がった。2枚目は少し時間的に短く、3~4枚目はかなりスピーディーに塗れたのはよかった。
4枚とも仕上がって立てて並べてガックリ肩を落とした!
なんだ この出来映えは?
裏面の色合いの倍位の濃さになってしまっていた。又塗りムラや色ムラで滅茶苦茶!
今考えると乱反射面は機械でくり抜いてある関係か溝の面が粗く、その分しみ込みが深いため色が濃くなってしまった。予想外の出来事であった。
まあこれも勉強の内だ、と諦め、又チャンスがあれば一層目はクリアを塗り2層目にこのミディアムウォルナットで試してみようと誓を立てた。
他社の製品に比べて安いので助かっています。
Z103 音響パネルBタイプを合計4商品、購入しました。4枚のパネルは普段、仕事で使っているニカワの接着力を信じて接着し、足はラワン合板の端材で自作しました。完成した音響パネル4枚はスピーカーの後ろに設置。一聴して音のエッジが際立ち音色が明るくなり,
私にとってうれしい変化でした。当分、無塗装のままで十分です。音工房さん,
いい商品をリーズナブルな価格で提供していただきありがとうございました。
いやあ大感激で出てくる音に驚愕!!
まず組み立てからお話します。
木のカット精度が素晴らしく、しかもダボ付ですからボンド付けで大きなヘマをしない限り立派に仕上がってしまいます。
送られてきたキットに付属されている説明書だけで組み立てを進めていくには経験者にとってはこれで役に立つでしょうが私のレベル(スピーカーキット2回目)では不安です。なので特典ページのURL先の組み立て手順を眺めながらが安心感があり着実にできます。工房経験のない私でもこのキットは大変楽に完成しました。
塗装はDIYで自宅内のアチコチでちょこちょこ切ったり貼ったり、又釘やビス留めなどもそれなりに楽しく進める方ではあります。
しかしこのスピーカーボックスへの塗装は初めてで、大山様のビデオ講座も拝見させていただきましたが、とても根気のいる仕事で私の精神力では無理があり、何度も重ねていると塗りムラが発生してしまい、見苦しくなり、結局は簡単な方法で仕上げてしまいました。次回いつか新たな塗装の機会には真剣に取り組み、その詳細を書き記したいと思います。
さて、音の方ですが11月初旬に完成し、初めての音出し時は低音のボンボンする異音が気になりましたが大山様のサポートを得てここはグッと我慢我慢で1ヶ月が経過しました。
約200時間のエージングが完了しましたので本来の個人的なレビューをさせていただきます。
このスピーカーは約1か月前の組み立て後の初めての音出し時にボンボンという音が気になりましたがエージングで見事無くなりました。そして初めての音出し時より、このスピーカーの音はきっと自分の気に入る音になるだろうという直感があり、エージングの毎日が楽しいものでした。
私は低音の出方をいつも非常に気にしています。新しいCDを買った時なども演奏の良し悪しより低音の良し悪しの方が気になってしまいます。
Z1-Livornoの低音は素晴らしいものでした。いろんなジャンルのCDを聴いてみて思ったことは目を閉じてオーケストラの曲をそこそこボリュームを上げて聴いて見ると、ホールの最前列中央の席を思わせました。お世辞ではありません。
一番それを感じた時の音楽はカラヤン指揮のドボルザーク「新世界より」の第1楽章です。1985年2月のレコーディングで、ウィーンフィルハーモニーの演奏です。最初から最後まで私をその場に釘付けされました。堂々たる音、ティンパニーの音は異常過ぎる位リアルに鳴ります。腰を抜かす程の驚き、正に驚愕でした。
クラシックが最も合うのかな?と思いきや、いやいやポップス、タンゴ、歌謡曲、ジャズ、何でも来い、の感じです。
つい最近入手したCDに演歌歌手 神野美伽の「矜持(きょうじ)」というアルバムがあります。2013年のCDですから決して新しくはありませんがこのCDの11曲目に「歌謡浪曲 無法松の一生(度胸千両入り)~ニューバージョン~」を大山様もZ社を取り巻く音愛好家の皆さまも是非一度このCDを手に入れられて、神野美伽の
度胸千両を聴いてみてください。度肝抜かれます!演歌好きでよかった!日本人に生まれてよかった!ときっと思いますよ。
どなたか私のこのレビュー見て、そして神野美伽の度胸千両入りニューバージョンをお聴きになった感想を聞かせてください。大山様もよろしくお願い致します。
とにかくこのZ1-Livornoの音はZ701シリーズの音とは世界が違います。素晴らしい音は低音の出方で良し悪しの大半が決まる、と思えるスピーカーです。
私は低音大好き人間です、と大山様に常に申し上げています。
このスピーカーの悪いところは見あたりませんが、更に欲を言えばもっとズシーンと身体にくい込むような低音が得られるサブウーファーなどのオプションを売り出してください。
尚、補足になりますがZ701のキット購入時にオプションで販売されていたスーパーツィーターをコンデンサーだけ変更してエージングスタート時より使用しています。
このスーパーツィーターの威力もスゴイです。私は73歳で、高音は1万ヘルツどころかもっと下までしか聴こえていない筈ですが、でも明らかにスーパーツィーターの効果は歴然としてありことが分かります。味噌汁に七味を少々振りかけるとぐっと味が締まりますよね。それくらいの違いは十分あります。
Z701がハイ上がりの音だとすればこのZ1-Livornoはロー下がりの音、なんて言ったりなんかして…。
このスピーカーに出逢えてよかった、本当にそう思っています。
大山様、Z1-Livornoのオプションで更なる低音増強を一日も早く販売されることを祈っております。
ミニコンポのスピーカーよりかなり良い音が出ています。
20年ほど前に購入したONKYOのミニコンポ、スピーカーユニットが壊れたので、当商品を購入制作、音といい形といいかなり良いです。満足しています。
今迄の雑誌による情報とは異次元の内容で、大変参考になりました。しかも無料で。
先ず、ブラインドテストの結果には驚きました。
数十倍の価格差が有るにも拘らず、ヒアリングでその差が識別できない人やソースが多かった事は本当に驚きです。 人はブランドと広告、外観、価格、雑誌等のレビュー情報で判断している事が良く分かりましたが、試聴が困難な条件下で実際に機器を購入する際の判断が今まで以上に難しくなってしまった、或いは逆に簡単になったようにも思えました。
次に、工具の使用法については動画で構成されており、まさに「百聞は一見に如かず」で、当方はこれからオーディオラックを自作する予定なので大いに参考になりました。
スピーカの調整テクニックには、即実行できる事が有り試行したいと思っています。
又、部屋の音響測定(見える化)にも非常に興味がありますが、ご紹介のアナライザーが手に入らないようです。 マイクと接続するPCソフトを探す事にします。
当方は2階でヒアリングしているのですが、階下からうるさいと文句をよく言われるので、インシュレーターの解説は切実なレベルで読ませて頂きました。 もう一段掘り下げた記事が欲しいなと思いました。
以上ですが、このような情報提供をして頂いた事に感謝すると共に、もっと多くの人に読んで頂きたいと思います。
フルレンジの名機です。
サウンドステージの構築に優れていて、各奏者の位置が明確に表現されます。また10Cmフルレンジとは思えぬ程豊かな低音を再生することが出来、かつ帯域バランスがとれたナチュラルな再生音であり、長時間聴いても聴き疲れがしません。大型システムにない良さがあり音楽を聴く楽しみが増えました。タモの突板を貼って仕上げましたが、外観もシンプルなデザインで素敵です。
使用機器 CD Player Marants SA11-S2, DAC DCAMPーBIZ製、Power AMP DENON POA-3000
ソース CD ステレオサウンド社 THE ROYAL BALLET 白鳥の湖, ESOTERIC社 エドヴァルト・グリーグ ペールギュント、究極BEST100 AVE MARIA 森麻季カッチーニ:アヴェ・マリア等
最高のスパイス
11月23日(祭日)待ちに待ったZ-502Ver2が我が家に届きました。
はやる気持ちを抑えて慎重に接続。
まず、音出しの感想の前に使用ピーカーの紹介をいたします。
我が家メインのスピーカーはZ703+マークオーディオMAOP7です。
本来はZ703はFOSTEXーFE108SSHP専用の箱ですが、
どうしてもFE108の音が好きになれずMAOP7使うことにいたしました。
結果、予想通り低音の過多のスピ-カーになり一か月余り低音と格闘することになりました。
しかし大山さんのスピカー追及道のブログを熟読しながら調整した結果、
低音のパンチ力が若干弱いながらも中高音の綺麗な響きのスピーカーを作ることができて満足しています。
だがやはり10㎝フルレンジ一発では高音域の艶ややかさ、糸を引くような伸びがやや足りない気がしたのでZ502を購入することにいたしました。
【音出しの感想】
音出しに選んだCDはベートーベンのトリプルコンチェルト:バイオリンとチェロとピアノの協奏曲で奏者はバイオリン/ソフィー ムッター・チェロ/ヨーヨーマ・ピアノ指揮/ダニエル ボエンハイムの巨匠3人.
この作品は3人のソロが入れ代わり立ち代わり演奏される合間をオーケストラが鳴り響き
時には3人がジャズセッションのようなバトルを演じるスリリングでユニークな曲で私の
お気に入りです。
音の印象ですが、もともとMAOP7はかなりの高音域まで出ていましたがややザラついた感じで今一歩でした。Z502を加えるとザラつき感がまったくなくなりバイオリンの音が
シルクのように滑らかで光沢感のある音に変貌したのに感動!
外にもチェロの高音が明るく軽やかになり又やや引っ込んだ音だったピアノが前にでて来て高音がキラキラした感じになり思わずウットリ、後はやや埋もれていたオーケーストラのバイオリンの音が明瞭に聞こえるようになったのでびっくり大感激。
もう一枚のCDはカールリヒターのパイプオルガン演奏のバッハ。これは音が部屋全体に広がりすっぽり包まれるような感じ。オーディオに関心のない妻の一言が「まるで教会で聞いてるみたい」本当にリアルな音です。
【総評】
一言でまとめるとZ502はスピーカの音を格上げする秘伝のスパイスです。
【システム】
アンプ:PSAudio製 /Stellar Strata
CDプレーヤー:マランツ/CD6006
レコードプレーヤー:Trio/KP700D
ヌケの良い中音と高域がクセになります
組み立て当初はナローレンジでこれは失敗したかと思っていたのですが、エージングが進むにつれ、非常に良い音が出るようになりました。今はスーパーツィータZ501と組み合わせています。結局色々試してコンデンサーは1.0μFで落ち着いています。
それから試しに4キロの鉄アレイを乗せてみたのですが、とても音が変わり、低音が締まって奥深い音色が出るようになりました。
クラシック中心に聴いていますが、ヌケの良い中音と高域のクセが逆に私にとっては好みで、女声も目の前で歌っているようなとてもいい感じです。低音も自然で30Hz台まででてます。
またApple TVでApple musicのDolby Atmosの5.1chのメインフロントとしても使っています。リアはZ Livorno、センターはZ601とオール音工房zの製品(あ、サブウーハだけフォステクス)。これが思った以上に素晴らしく、オーケストラや教会音楽など美しい残響が部屋全体を包み込んでくれます。今までにない体験がサブスクで気軽に体験できてお勧めです。ハイレゾよりもむしろ音がよく感じられるほどです。
【商品名】Z702-Modena(V6) 中音域から低音域の再生音がいい
【商品名】Z702-Modena(V6)
amp:FOSTEX AP 20D
DAC:FX-AUDIO FX04J+
USBから再生
ツィータ:エミネンスAPT30
JAZZ:ROCK(1960-1980年代 )
いや~普通です~
ヤフオクでたまたまZ-Modena-MK2を手に入れ、さてさてどうしようかと思っていたところ、ネットでZ701-Modena(V3)の
図面を拾うことができ、これもネットで板材を注文…そそくさとくみ上げてみたところ…
いやいや、これが良い感じに仕上がり愛器としてずっと使っていました
そして御社からZ702-Bergamoの発売のご案内をいただき、即購入させていただきました
12時間エージングして視聴した感想ですが期待どおり「いや~普通~」って感激しました
そして、バスレフポートから中高音が全くもれていない!クリアなはずです
世の中、低音がどうのこうの、ハイレゾで高音が素晴らしいとかオーディオマニアの諸氏が謳ってらっしゃいますが
私は癖のない普通に聴けるスピーカーが欲しくて色々試してきましたが、なかなか見つからず…
Z701-Modena(V3)で何とかというところでした、そしてZ702-Bergamo…愛器になります…きっと
Z701-Modena(V3)とZ702-Bergamoの比較ですが、いつも試聴に聴いているダイアナクラールの’S Wonderful
Modenaは目の前のマイクで、Bergamoは録音室のガラスの向こうのマイクで歌っている感じでしょうか
スパーツイーターは付けたほうが良いと感じました(0.68μF)
なお、機材はお金持ちではないのでRaspberryPi(Volumio3)>MiniBoss(DAC)>FX-AUDIO-TUBE-P01Jになります
ソースは情報量が多いにこしたことがないのでMP3よりFLACとかDSDにしています
【作成後記】
タイトボンドやクランプを使ったことがなかったので悪戦苦闘しました
タイトボンドは付けすぎや作業が遅いと硬化が始まって隙間ができたり傾いたりするようです
また、クランプは締めるまでに時間がかかるし、締め方を均等にしないと歪みの原因になります
説明書の最初「音道板2、音道板3」の取付けで上下のクランプの締め方が悪いと最後の側板が浮いたりダボが合いません
私もカンナで削るはめになり最後の側板のダボは何か所か使用しませんでした
本製品はダボである程度正確性が確保されるのでいつも通り「漬物石方式」でよかったな~と後悔しています
①まず、地板+背板を接着、次に天板を接着してコの字を作ってしまいます(側板を接着しないようにして使うと楽です)
②コの字を側板に接着します(逆側板を接着しないようにして重石を乗せます)
③音道板を全て側板に接着します(逆側板を接着しないようにして重石を乗せます)
④吸音材をつけたら逆側板を接着します(ターミナルは表面処理が終わってから付けます)
※②と③の接着後、接着部の角にホワイトボンドを入れて隙間対策します
※②③④ともバッフル板も使って平面出しと角出しすると確実です
※外側の接着部は接着前にマスキングして、接着後すぐにはみ出しを拭き取ってマスキングを外してしまいます
というのが、もし私がもう一度作るならこうする編でした、ご参考までに・・・
なお、漬物石は2L天然水6本入りを4箱くらい・・・使ったあとは災害時用に
Best CP!
結論:兄貴分の2ウェイバスレフのZ800-FW168HRの実に1/3未満の価格からすれば、これはすごいHigh C/P(多分Best CP)だろうと思います。
購入動機:Z800-FW168HRを突板仕上げして、これをZ505 Trentoの上に載せました。これを里帰りした長女に見せびらかしたら「欲しい!」との有難いお言葉。長女には甘い妻には「長女が欲しがったから」という口実でまた音工房さんから仕入れて作ってプレゼントできます!でもZ800は長女には贅沢というものなので、Z1を仕入れました。
製作:仕上がりはまあまあ。組立て作業自体は、相変わらず高精度のダボ穴加工のおかげでスムーズ。仕上げはZ800で失敗を重ねて修正に苦労したウォルナットの突板貼りに再チャレンジしました。Z800のように複雑な形状ではなく単純な四角の箱なので、角ピンに仕上げれば突板貼りも完璧かと思いきや、木工は奥深いものです、目地払いで電動サンダーを使った際に稜部をダレさせてしまい、調整に手間取りました。また稜部分の突板の合わせは、突板貼り2回目で満を持してやった積りでも難しいものです。突板の裏に貼られた和紙の白い断面がどうしても稜部に出てしまい、結局は仕上げ塗りの時点で顔料系の油性ペンで和紙の白を目立たなくしました。Z1の次のプロジェクトには、貼る難易度は高くなるようですが、和紙無しの突板に挑戦します。外観的には単純な四角の箱なので何かアクセントを付けたく、当初はバッフル面左右の稜に大きなRを付けてこれに突板を貼ることを考えましたが、稜にRを付けるトリマーが安物の上に私の腕がいまいちで綺麗にR取りができなさそう、しかもR9.5にするとR部がダボ穴に被ってしまう計算なので断念。代案で12㎜厚のMDF合板でグリルを作り、これの左右両稜をトリマーでR9.5に加工しました。R加工部分は上からグリルネットを張るには十分な精度で仕上がり、グリルをBOXに固定する為のプラスチック製グリルホルダーの取付けも上手くできましたが、MDF板のスピーカー部逃げの為の穴あけは数度チャレンジしましたが、トリマーの刃物が暴れて真っすぐに綺麗にできません。上からグリルネットを貼れば隠れますが、他の部分がまあまあの仕上がりなので残念です。ここの部分はジグソー加工の方が良かったのでしょう。
音のインプレ:音出しして未だ30時間ほどの為か、ソースによってはヴァイオリンやヴォーカルで刺激的な音が出ることがあります。よく聞く楽曲は、バッハのヴァイオリンコンチェルトやヴィヴァルディの調和の霊感などを在宅勤務中に小音量で聞くのにはじまり、仕事の後は何でもござれで、無伴奏チェロから交響曲系、ジャズ、プログレッシブロックまで。寝る前の仕上げにはウイスキー片手にダイアナクラールや中溝ひろみのジャズヴォーカル、それにカルメン・ハバネラで癒しの時間。
ブレークイン完了後には刺激的な音が取れ、かつビビッド感のある音になってくれるものと期待しています。去年組んだZ800ではブレークインにさほど時間がかからなかったと言うか、最初から耳障りな音があまり出ず、余韻の表現が見事でした。Z1は、High CPのウーハーと箱の設計の秀逸さが要因だと思いますが、わずか10Lのバスレフからは驚くほど低音が出ますが、高音が聞こえ難い私には低音が厚すぎます。先輩諸兄がヴォーカルの定位と表現を絶賛されていますが、確かに定位は良さそうです。Z800との比較はフェアじゃないでしょうが、先に作ってしまったZ800に比べて、音の緻密さとか余韻の美しさは、やはりZ800にはかなわないようです。(このコメントは、Z800+Z505で40万円ほどつぎ込んだ自分に対するExcuseなのかも知れませんが・・・。)
F特:それから、Z800では小音量でもきれいに再生できますが、Z1では音量をもう少し上げないと高音と中低音のバランスが取れない印象です。ただこれは私の耳のF特のせいかも知れません。つまり、もともとメニエール病のせいで軽い難聴があるうえに60歳過ぎて高音が聞こえなくなったので、音量を上げないと耳のF特がフラットにならないような印象になるのかも知れません。(ただ疑問なのは、Z800は小音量でもバランスが取れているように感じるし、細かな音が聞こえます。)因みにZ800とZ1では仕様書上で能率が2dBほどの違いがあるので、同じ音圧で聞こうとすると、Z1の時は2dBほどアンプのゲインを上げれば良いはずですが、実感としては3~4dB上げる必要があるように感じます。何故か?やはり私の耳のF特なのかも知れません。Z1を小~中音量でも美しく鳴らすには、大山社長がスーパーツイーターのページで言われるように、8K~20Kの帯域をスパイス的に加えるためにZ501のようなツイーターを付けてやれば良いのかも知れません。特に私のような難聴/高齢者については。今度試してみます。
Z800+Z505 の1/6以下の投資だと考えれば、やはりZ1はBest CPであることは自信をもって報告できます。今回仕上げたZ1は来月に長女の元に嫁入りします。次には長男のを作ります。
最後まで読んでいただき、有難うございました。
低域のボンつきのこと
メルマガにZ1-Livornoの低域ぼんつきについて書かれていましたので、レビューとして書くのは少々違うかもと思いましたが投稿します。私のZ1-Livornoも低域にボンつきがあり、一時は捨ててしまおうかとも考えたほどでした。なお、現在(音出し後約1年経過)の評価は★4つです。★5つでも良いのですが、これ以上のものが無いわけはないと思っていますので。
主な機材
CDプレーヤー:パイオニアPD-50AE
アンプ:マランツPM8006
音源:CD、SACD 主に交響曲
他の所有スピーカー:Z701-OMMF4、Z601-OMOF101
スピーカーの配置:6畳和室の短辺方向に、約1300㎜の間隔でLとRを、各々600㎜の高さのスピーカー台に乗せています。スピーカーの背面は壁から約300㎜ といったところ。
音出し当初、オーケストラの中の木管楽器が非常にきれいな音だなと感じましたが、コントラバス等の低音楽器が鳴り始めた途端、ボーボーという音でびっくり。バスレフダクトからかなりの空気の出入りがはっきりと見えるようで、手をかざすと団扇に当っているような感じでした。ダクトを外したり他の長さのものと入れ替えても変化なし。
すでに諸兄のレビューを読んでいたので、ダクトにスポンジを入れると良いようなので、安い台所用スポンジを入れて見ました。効果ありで結局、音出しから1年経った今でもスポンジは入れています。今も取り外すと、当初ほどのボンつきはありませんが低域が厚く響きすぎます。使用したスポンジは厚みが十数ミリ、幅60㎜、長さ120㎜程度で、これを短方向に少し丸めてダクトに入れますが、ダクトは完全には塞がず、載せる程度にしています。
スポンジを入れることに抵抗があったので、最初はエージングで良くなると信じて20時間ほど鳴らし続けたり、エンクロージャー内に吸音材を入れてみたり、近所迷惑も顧みず少々大きな音で鳴らしてみたりしましたが、若干の改善があったように感じただけで、ついにスポンジ挿入と相成りました。
さてその音ですが、木管の音のきれいさ、金管の輝き、定位の良さ、雰囲気などZ701-OMMF4より勝っています。さらにスーパーツイーターを追加、付属のコンデンサを使用し、逆相接続し、より解像度が上がったように感じます。ただZ701-OMMF4やZ601-OMOF101より音が小さく、アンプのボリューム位置がZ701-OMMF4で10時の時、同じ程度の音量を得るにはZ1-Livornoでは11時半から12時になります。良い音なので聴きこむうちにさらにボリュームを上げたくなります。近所迷惑の前に家族迷惑ですね。
Z1-LivornoはB&Wの805を目指しそれを凌駕したとのことですが、実は小生、10数年805Sを使用していましたが使いこなせず手放し、その後Z701-OMMF4やZ1-Livornoを購入作製してきました。Z1-Livornoは805Sより良い音で安心して音楽が楽しめます。今後低域がどうなるか見ていきますが、今Z702-Bergamoを作製中です。レビューをみると相当良いようなので、完成後はZ702-Bergamoばかり使うようになり、Z1-Livornoを忘れ去ってしまうかもしれません。さてどうなることか。
ところで、ここに書くことでは無いのですが、Z701-OMMF4のユニットをOM-MF4-MICAに変えたものを大山様は85点と評されていたと思いますが、小生はMICA版の方がOMMF4より良いように感じます。Z701-OMMF4は真夏の太陽でギラギラに照らし出している感じ、MICAのほうは秋のさわやかな陽に照らされたように感じています。それでもZ1-Livornoのほうが良い音ですが。出来ましたらZ701-OMMF4のMICA版キットなど作っていただけると有難く思います。余計なことを書き失礼いたしました。以上
満足できる逸品です
使用機材はアキュフェーズE-560をメインとしてアキュフェーズ製品を主に使用しております。
普段はfmで音楽番組を流しています。
音工房zのスピーカーはZ1-Livornoに続いてZ702-Bergamoは2機種目になります。
Livornoの組み立てはスムーズに問題なく出来あがり、エージングも進み軽やかに鳴っています。
Bergamoも同様に出来るはずと軽い気持ちで作業を進めたところ、思わぬところで作業をストップする事態に至りました。
仮組みのときは気づかなかったのですが、音道板を取り付け最終確認した所、あちこちに隙間が出来ていました。
目で見て確認出来る範囲はボンドで塞ぎましたが、音に与える影響がどれだけあるかは定かではありません。
もう少し慎重に作業を進めるべきであったと反省しております。
この記事をお読みの方でこれから購入、組み立てをされる方はくれぐれも基本に忠実に作業される事を望みます。
さて、肝心の音ですが、エージング始めたばかり2〜30時間経過の感想です。
良くも悪くもLivornoと同様音工房らしさ満点の音です。良い音です。聴き疲れしません。
この2〜3日LivornoとBergamoを同時に鳴らしていますが、音場の広がりが何とも言えず良くなりました。
正に音に包まれる感じです。低域から高域までの繋がりも良くなって音が生き生きしています。
Bergamoのエージングを進めもう少し聴き込んで見たいと思います。
今後も素晴らしい製品が生まれることを願います。
想像以上の音でした
初めてのスピーカー制作。
スピーカー接続部分の部品名も分からず悪戦苦闘。
仕組みが分からず、説明書をプリントアウトして何度も読み直したが、「コイルとコンデンサーがどうしてこの接続になっているのか」理解できず、迷いながら中学生以来やったことのなかったハンダごてを買ってきて作ってみた。
最初の音出しの印象は「低音不足で硬い」。しかし、二日ほどかけて音出しを続けると低音が豊かになってきた。
一月ほど使うと、30年以上使ってきたパイオニアS-99Tを上回る高音と低音を出すようになってきた。これには驚いた。コストパフォーマンスは非常に高い。
なぜ、この大きさと重さで、この音が出せるのか未だに不思議だ。
タイトボンドも余っているし、木工クランプも買ったので、ついでにZ702-Modena(V6)も作ってみたが、これも想像以上の音を出している。
欲が出て、上級機種も作りたい衝動に駆られましたが、それはまたの機会にします。