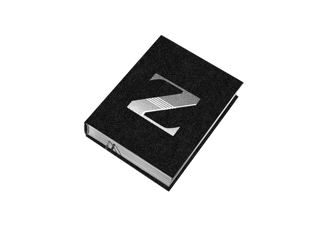自作ハイエンドスピーカー大百科事典 レビュー投稿フォーム
自作ハイエンドスピーカー大百科事典 投稿レビュー
オーディオ熱が冷めつつある今日貴重な存在です。
いつもホットで貴重な情報をありがとうございます。オーディオ熱が冷めつつある今日貴重な存在です。非現実的な価格の製品のみが一流である様な錯覚に陥っているオーディオ評論家たち自身がオーディオ熱に水を注いでいることを知らしめてあげて欲しいと熱望します。
今後も楽しみです。
長岡スピーカーを何個も作りましたが、水害で設計書もスピーカーも流出、このレポートは非常に参考になります。少しずついい好みの音になるよう追い込んでいきたいものです。今後も楽しみです。よろしくお願いします。
大変参考になります。
大変参考になります。毎回プリント・アウトして、分厚いファイルに綴じています。
素晴らしい。天国の長岡先生に届けたいですね。
素晴らしい。天国の長岡先生に届けたいですね。そしてわざと悪びれたつっこみコメントはどんなものなのか聞きたいです。
やりたいことはたくさんありますが、少しづつ試してゆきたいと思います。
昨年の試聴会以降、音工房Zさんのファンです。中古でV601+Markaudio OMMF-5を手に入たた昨年秋に私の音工房Z体験が始まりました。先週Z-Modena mkIIを購入し、V601に組み込もうと思っています。さて、今回のメルマガ記事も堪能いたしました。DIYが苦手で本格的な組み立てへの勇気が足りないのですが、小学生以来45年間のオーディファンとして、今回の記事のような内容をじっくり追体験しながら余生のオーディオ人生を過ごしていきたいとの思いを強くしました。やりたいことはたくさんありますが、少しづつ試してゆきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。
理論的なことだけでなく、動画で見せていただけることが何よりです。
以前、Stereo誌のSPユニット用エンクロージャーを購入させていただきました。
今回の大百科事典も興味深く読ませていただいております。理論的なことだけでなく、動画で見せていただけることが何よりです。「ここは、こんな風にねぇ~。」とその場で見ているかのようなレクチャーがとても嬉しいです。工房まで出かけることはなかなか難しいのですが、実験レポートやブラインドテストのけっか公開等も楽しいです。データ公開に賛同していただけた参加者の方々にも感謝です。また、「音楽を楽しむ」ことを大事にしていることも、CD紹介などからうかがえて工房の皆さんの心意気が伝わってきます。もっと若い頃に音工房Zに出会えていたら良かったです。これからも、興味深い記事の配信を楽しみにしています。 これからもよろしくお願いいたします。
時代と共にアンプもスピーカーも進化していることを痛感しました。
大山美樹音様
お世話になります。
早速資料をご送付していただき、誠にありがとうございます。
膨大な中身でしたが、制作方法については動画がありましたので理解できましたが、調整などについては実際にやってみないと理解ができない内容でした。
現在は数十年前の音響設備(ダイヤトーン3Way、山水アンプ等)で聴いております。
御社のスピーカーをYou tubeでヘッドホーンで拝聴してみましたが、切れの良いすっきりした音で驚嘆しております。時代と共にアンプもスピーカーも進化していることを痛感しました。ものつくりには興味がありますのでチャンスがあれば挑戦してみたいと思っております。
その場合はよろしくご指導お願い申し上げます。
1万円でできるスピーカーを手始めに作成したいと思います。
難しいことが沢山書かれていましたが、じっくり読みたいと思います。1万円でできるスピーカーを手始めに作成したいと思います。ありがとうございました。
レポートを参考にバージョンアップをしていきたいと思います。
大昔に作ったスピーカーを現在も使っています。20cmフルレンジ2本を並列に繋ぎ、ツイーターをつけて使っていますが、フルレンジは今まで2回ほどコイルの断線で交換しています。ツイーターもだいぶ前から断線らしく音が出ないようなので、新しく購入を考えていたところ「自作ハイエンドスピーカー大百科事典」行き当たりました。箱の作りからネットワーク、吸音材等々細部まで丁寧な解説があり、自分が作った当時とは比べようもないほどの情報で、とても参考になります。新しいものを作るつもりはありませんが、いただいたレポートを参考にバージョンアップをしていきたいと思います。これからも楽しみにしております。よろしくお願いします。
ゆっくり読みたいと思います。
概略を読みましたが、ゆっくり読みたいと思います。当方13センチフルレンジでダブルバスレフに挑戦したいのですが箱の基準がわかりません。どうしたらよいですか?将来的にはプラスツイーターも、考えています。